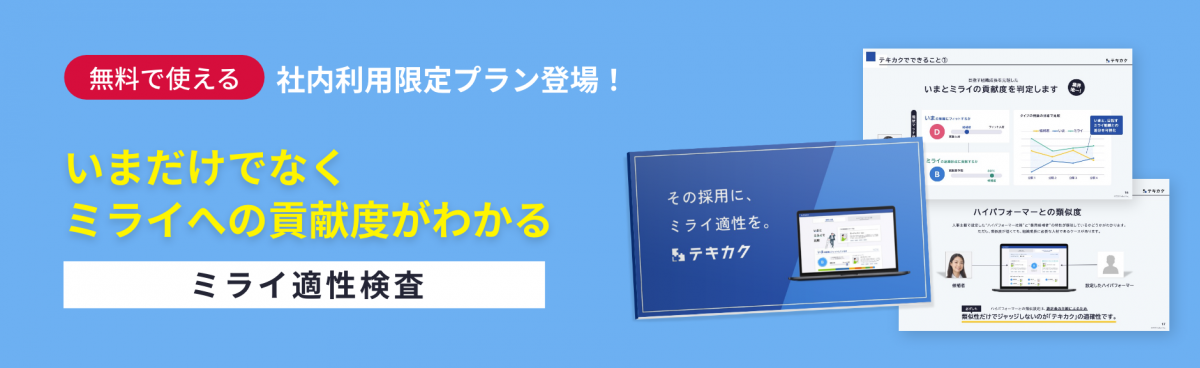近年、多くの企業が「リテンション」に注目しています。リテンションとは「維持」や「保持」を意味する英単語で、人事領域では人材の定着を指します。少子高齢化による人手不足や転職市場の活性化を背景に、人材の確保・定着は企業にとって喫緊の課題となっています。本記事では、リテンションの基本的な意味から、人事領域における具体的な施策、企業にもたらすメリットまで詳しく解説します。
リテンションとは
リテンション(Retention)は、英語で「維持」「保持」を意味し、ビジネスにおいては分野ごとに異なる意味で用いられます。
人事領域におけるリテンション
人事領域におけるリテンションとは、人材の維持を意味します。
人材の確保は採用活動だけでなく、 「いかに優秀な人材を定着させるか」 も重要なポイントです。特に、近年の転職市場の活性化により、従業員がキャリアアップを目的として転職するケースが増えています。企業にとっては、新たな人材を採用するよりも、現在の社員が長く働き続ける環境を整える方が、コスト面や組織の安定性を考慮すると有効な戦略となります。
リテンション・マネジメント
リテンション・マネジメントとは、従業員が企業に定着するための取り組み全般を指します。社員一人ひとりの価値観やキャリア志向に寄り添い、働きがいを提供することが、リテンションの成功につながります。
リテンション・ボーナス
リテンション・ボーナスとは、 一定期間会社に在籍することを条件に支給される特別報酬 のことです。残留報酬または残留特別手当と呼ばれることもあります。
マーケティングにおけるリテンション
マーケティング領域では、リテンションは 「既存顧客の維持」 を指します。一般に新規顧客を獲得するためには、既存顧客を維持するよりも5倍のコストがかかると言われています(1:5の法則)。既存顧客との関係を深め、リピーターを増やすために、ポイント制度や会員プログラム、パーソナライズされたサービスの提供など、さまざまな施策が活用されています。
リテンションが注目される背景
少子高齢化による慢性的な人材不足
日本では少子高齢化が進み、 労働人口の減少が深刻な問題 となっています。内閣府の「令和6年版 高齢社会白書」によると、2023年時点で日本の総人口のうち65歳以上人口が占める割合は29.1%で、この割合は今後も増え続けると予想されています。
(参考資料)令和6年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) – 内閣府
若年層の人口が減る中で、企業は限られた人材を確保し、長期的に活躍してもらうことが重要な課題です。特に、中小企業では採用活動が困難になるケースが多く、リテンション施策の強化が求められています。
転職市場活発化による人材の流動化
近年、転職が一般的になり、 優秀な人材ほどキャリアアップを目的に転職を考える傾向 があります。厚生労働省の「令和6年版 労働経済白書」によれば、転職者数は2019年に過去最高の353万人に達したのち、2020~2021年には感染症の影響で290万人にまで落ち込んだものの、2022年には増加に転じ、2023年は2年連続増加して328万人にまで上りました。
このような状況下で、企業としては、社員が他社に流出しないように、 魅力的なキャリアパスを提供し、働きやすい環境を整える 必要があります。
働き方の多様化
厚生労働省による、令和5年の「新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料」によれば、全国的なテレワーク実施率は2020年に急増し、2022年6月時点では30%に達しています。また副業に関しても、正規雇用者のうち「副業を持っている」または「副業を持ちたいが持っていない」と回答した人は60%以上に上ります。
(参考資料)令和5年「新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料」- 厚生労働省
テレワークの導入や副業の解禁など、 働き方の選択肢が増えている中で、企業は柔軟な勤務制度を整えることが求められています。
リテンションを実施すべき企業の特徴

離職率が高い、または上昇傾向にある
従業員の退職が相次いでいる、または最近になって離職率が上昇している企業は、リテンションマネジメントの強化が不可欠です。
社員が退職を決断する理由としては、「仕事内容に魅力を感じない」「給与や待遇に不満がある」「職場の人間関係に問題がある」といった要因が考えられます。これらの課題が放置されると、離職率のさらなる上昇につながり、企業の成長にも悪影響を及ぼしかねません。
特に、経験豊富な社員の退職が増えると、業務のノウハウが流出し、新しい社員が定着しにくい環境になってしまう恐れがあります。そのため、従業員の退職理由を正しく把握し、改善策を講じることが重要です。
採用活動をしても応募が集まらない
求人を出しても応募者が少ない、または優秀な人材が集まりにくい企業も、リテンションマネジメントの強化が求められます。
求職者が応募をためらう理由として、企業の魅力が適切に伝わっていないことが挙げられます。たとえば、給与や福利厚生、職場環境が競合他社と比較して魅力に欠けている場合、求職者はより条件の良い企業を選択するでしょう。
このような状況では、社内の人材も同様に自社に対して不満を感じている可能性があります。改めて自社に目を向け、リテンション施策を強化することで、従業員満足度を向上させることが必要とされているかもしれません。社内の環境を改善し、社員の定着率を高めることで、企業の評判も向上し、結果的に採用活動にも良い影響を与えるでしょう。
会社の体制や外部環境が大きく変化した
組織改革や経営方針の変更など、企業の環境が大きく変わった際には、それまで問題にならなかった不満が顕在化することがあります。
たとえば、以下のような変化があった場合、従業員の不安や不満が高まり、離職率が上昇するリスクがあります。
- 企業の買収や合併により、社内文化や人事制度が変わった
- 業務の効率化を目的とした人員削減や配置転換が行われた
- 副業の解禁やリモートワーク導入など、新しい働き方に対応する制度が整っていない
従業員にとって、環境の変化はストレスの原因となり、場合によっては転職を検討する要因になります。そのため、企業は変革の過程で従業員の声を積極的に聞き、適切なフォローを行うことが重要です。
リテンション施策が企業にもたらすメリット
採用・育成コストの抑制
企業が新しい人材を採用するには、求人広告の掲載費、採用担当者の業務負担、面接にかかる時間など、さまざまなコストが発生します。さらに、新入社員が業務を習得し、一人前に育つまでには時間と教育コストがかかります。社員が離職を選ぶことになれば、こうしたコストが無駄になってしまいます。
しかし、リテンション施策を強化し、既存の社員が長く定着するような環境を整えれば、採用の頻度を減らすことができ、結果的に下記のようなコストの削減につながります。
- 採用活動のコスト削減(求人広告費、人事担当者の業務負担の軽減)
- 教育研修コストの削減(新入社員研修、OJT研修にかかる費用や時間の節約)
ノウハウ蓄積・流出防止
企業の競争力を高めるためには、社員が持つノウハウや専門知識が組織内に蓄積されることが重要です。しかし、離職率が高い企業では、社員が培った知識や経験が社外に流出しやすく、組織の成長に悪影響を与えることがあります。
リテンション施策を実施し、従業員が長く働ける環境を整えることで、業務に関するノウハウが社内に蓄積され、企業の競争力が向上します。また、経験を持つ社員が社内に多くいることで、新入社員の教育やOJT(On the Job Training)をスムーズに行うことが可能になります。
社員のモチベーションアップ
従業員が企業に対して満足していなければ、仕事のモチベーションが低下し、生産性も下がってしまいます。しかし、リテンション施策を適切に実施することで、社員が「この会社で働き続けたい」と思える環境を作ることができ、モチベーションの向上につながります。
例えば、公正な評価制度や昇進の機会、ワークライフバランスの向上など、社員の働きやすさを考慮した施策を取り入れることで、仕事への意欲が高まり、生産性も向上します。また、社員同士のコミュニケーションを活性化させることで、チームワークが向上し、職場の雰囲気が良くなることも期待できます。
企業のブランド価値向上
社員の定着率が高い企業は、働きやすい環境が整っているという評価を受けやすく、企業のブランド価値向上につながります。特に、SNSや口コミサイトでの評判が企業の採用活動に影響を与える現代では、「社員満足度が高い企業」として認知されることが、優秀な人材の採用にもつながります。
また、社内の雰囲気が良い企業は、社員の紹介による採用(リファラル採用)も増えやすく、結果として優秀な人材を確保しやすくなるというメリットもあります。
業績向上と持続的な成長
リテンション施策を適切に実施することで、従業員の満足度が向上し、業務の効率化や生産性向上につながります。その結果、企業の業績向上にも直結し、持続的な成長が可能になります。
例えば、長期的に働く社員が多い企業では、業務の安定性が増し、チームの協力体制が強化されるため、プロジェクトの遂行能力も向上します。さらに、社員が安心して働ける環境が整うことで、新しいアイデアやイノベーションも生まれやすくなります。
リテンション施策の具体例
金銭的報酬
ボーナス
ボーナスは、会社の業績や勤続年数などに基づいて支払われる臨時給与です。従業員のモチベーションとして一般的なものではありますが、会社全体の業績や経営状況によって変動せざるを得ないものであることには注意が必要です。
インセンティブ
インセンティブとは、規定の報酬とは別に、従業員の成果に応じて支給される報酬金を意味します。インセンティブを支給することで、従業員の成果を奨励し、モチベーションを向上させることにつながります。
ストックオプション
ストックオプションとは、従業員があらかじめ決められた価格で、一定期間内に一定数の自社の株式を購入できる権利です。企業の成長とともに社員が利益を得られる仕組みを作ることで、長期的な定着を促します。
適正な人事評価・給与体系構築
社員の努力や成果を正当に評価し、納得感のある給与体系を構築することで、離職の防止につながります。
福利厚生
住宅手当や育児支援、健康サポートなど、社員が安心して働ける制度を整えることで、定着率を向上させます。
非金銭的報酬
社内コミュニケーションの活性化
働くうえで、職場の人間関係は重要な要素であるため、悪化すれば離職につながる危険性があります。1on1ミーティングやアンケート、各種サーベイを採用することで、従業員の声に耳を傾け、社内コミュニケーションの活性化に努めましょう。
スキルアップ・キャリア形成の支援
従業員に長期的に自社で働いてもらうには、従業員が会社を通じてスキルアップし、キャリアを形成できるような体制を整えることが重要です。研修制度やスキルアップ支援を充実させることで、社員が成長を実感し、長く働き続ける意欲を高めることにつながります。
働きやすい就業環境整備
従業員が働きやすい就業環境を整備することは、リテンション施策としても有効です。働きやすい環境が整備されていない企業の場合、子育てや介護などのライフイベントによって、働き続けられなくなってしまう従業員が出てきてしまう可能性があります。テレワークやフレックスタイム制など、従業員の望む働き方ができるように環境を整えることで、従業員がワークライフバランスを実現できるようになり、ひいては長く自社に務められるようになるでしょう。
まとめ
リテンション施策は、単に離職を防ぐだけでなく、企業の成長を支える重要な戦略の一つです。採用・育成コストの削減、ノウハウの蓄積、社員のモチベーション向上、企業のブランド価値向上、業績向上など、多くのメリットがあります。
企業が持続的に成長し、競争力を高めるためには、短期的な視点ではなく、長期的な視点でリテンション施策を計画・実施することが重要です。社員が「この会社で働き続けたい」と思えるような環境を作り、企業と従業員がともに成長していける関係を築くことが、これからの時代に求められています。