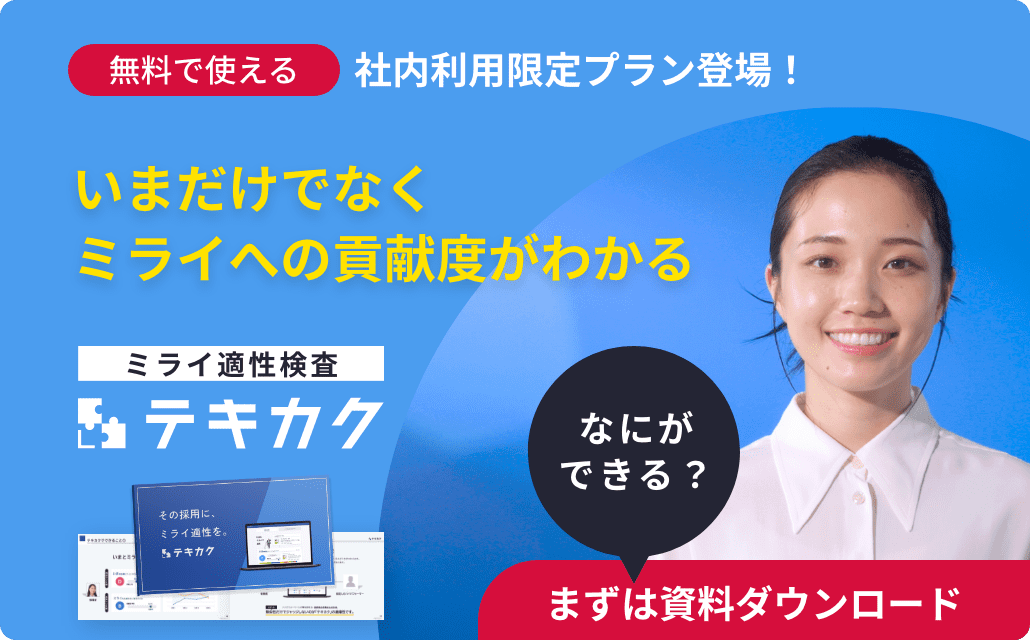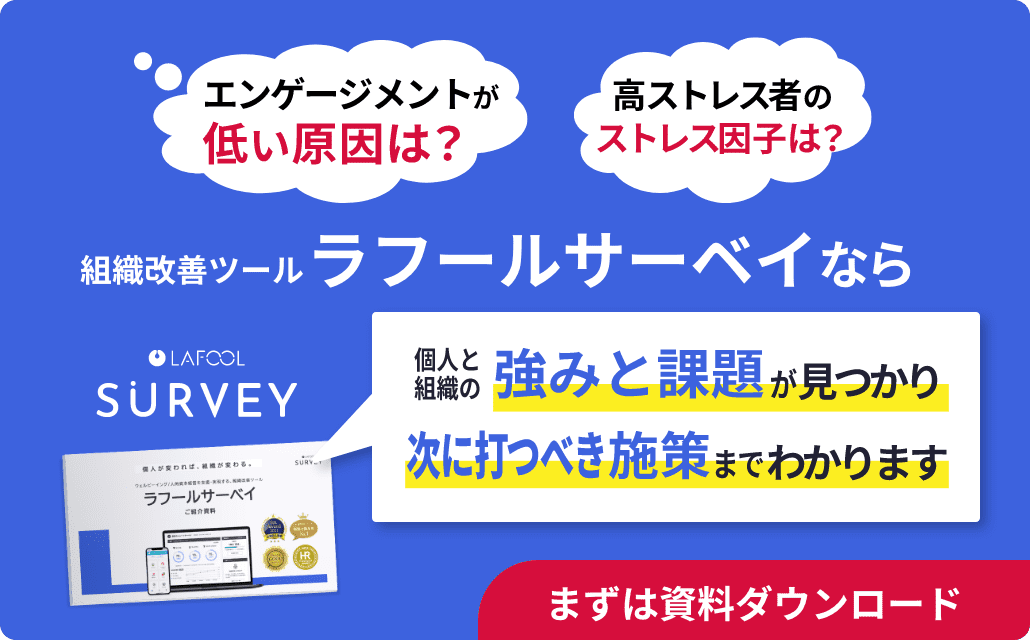人事評価制度には様々な種類や目的があることをご存知ですか?運用の成功には自社に適した制度を見極めることが重要です。その一方で、 「なんとなく種類は思い浮かぶけど、他にもあるなら知っておきたい」 「他社の導入事例を知って、自社の制度の見直しを行いたい」 このようなことを検討している方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、人事評価制度の様々な目的や種類、それぞれのメリット・デメリットをまとめて紹介します。また、人事評価制度を廃止した企業や独自の評価制度を導入している企業事例も併せて解説していきます。人事評価制度の見直しや導入を検討している方の参考になれば幸いです。
1. 人事評価制度とは?
内閣官房によれば、「人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」を意味します。すなわち人事評価制度とは、従業員のパフォーマンスや企業への貢献度を評価し、待遇や報酬などの処遇に反映させる仕組みのことです。
(参考)内閣官房「人事評価」
人事考課との違い
「人事評価」と「人事考課」は共に社員を評価することを指し示し、同じ意味として使用されることの多い言葉です。
両者が使い分けられる場合、「人事考課」が昇進や給与などより限定した範囲を示すのに対し、「人事評価」はより広く人事にかかわる判断を指し示しています。
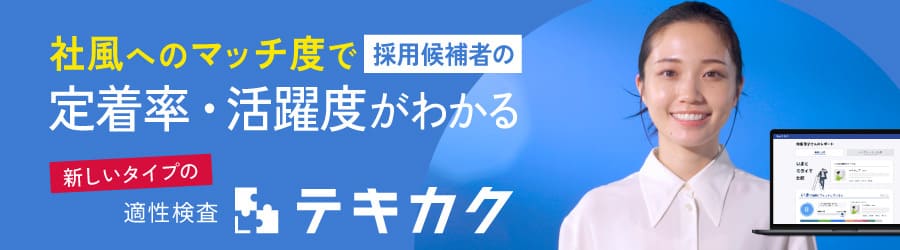
2. 人事評価制度の導入目的
人事評価制度は、単なる職員の業績を測る仕組みではありません。
採用・昇進や給与決定といった人事管理の基盤として機能するだけでなく、社員一人ひとりの成長を後押しする「人材育成の手段」としての役割も担っています。さらに、評価のプロセスを通じて上司と部下が対話を重ねることで、組織全体で目標や課題を共有しやすくなり、業務の改善や働き方の見直しにもつながります。
こうした取り組みの積み重ねにより、組織の活性化や効率的な運営を実現することが、人事評価制度の大きな目的だといえるでしょう。
(参考)内閣官房「人事評価」
誰もが働きがいを感じられる人事制度に必要な要素とは?
以下の資料では、
- 働きがいのある職場とは
- 人事制度でエンゲージメントを高めるには
- 人事制度を活用した他社事例
についてまとめましたので、ダウンロードしてぜひお役立てください。

3. 主な人事評価制度の種類

人事評価制度の評価方法には様々な手法があり、それぞれメリットやデメリットも異なります。以下では代表的な3つの評価方法について、概要とメリット・デメリットを紹介します。
- 目標管理制度(MBO)
- コンピテンシー評価
- 360度評価(多面評価)
目標管理制度(MBO)
MBOはManagement By Objectives and self-controlの略称で、組織マネジメントの概念として経営学者のドラッカーによって提唱されました。社員自らが目標設定を行い、上司は達成に向けた社員の主体的な活動をサポートし目標の達成度合いに対する評価を行います。MBOは社員の主体的な行動に重きを置くことで、社員の職務遂行能力の向上にも期待できます。
MBOには以下のメリット・デメリットが挙げられます。
- メリット 社員の能力開発や人材育成につながる
- デメリット 高い評価を得るために目標を低く設定してしまう
コンピテンシー評価
コンピテンシーとは高い業績を上げる人材の行動特性であり、その行動特性を基準におき評価を行うことをコンピテンシー評価と呼びます。評価項目が具体的な行動特性であるため、社員にとっては目標に向かって取り組みやすいのが特徴です。
コンピテンシー評価には以下のメリット・デメリットが挙げられます。
- メリット 評価基準が明確であるため公平な評価が可能
- デメリット 評価基準とする行動特性が必ずしも成果を上げるとは限らない
360度評価(多面評価)
360度評価は、上司だけでなく同僚や部下、同じ企画を担当するメンバーなど業務上関わりのある多方面の社員が対象者を評価します。偏りのない360度方向から下される評価には、対象者に高い納得感を与えられる効果が期待できます。
360度評価には以下のメリット・デメリットが挙げられます。
- メリット 納得を得られる評価内容で改善に取り組みやすい
- デメリット 高い評価を得るための行動に偏る可能性がある
その他の評価制度
前述のとおり、人事評価制度には「業績評価」「能力評価」「情意評価」の3つの評価があり、評価するための手法も多岐にわたります。
上記にあげた評価制度のほか、最新の制度もいくつか紹介します。
リアルタイムフィードバック
リアルタイムフィードバックとは、従業員の働きぶりに対して即時にフィードバックを行う手法のこと。こまめにフィードバックをすることで、課題に対してスピーディに対応ができ、社内コミュニケーションの活性化にも役立ちます。
バリュー評価
バリュー評価とは、企業の行動規範をどれだけ実践できているかについて評価する制度です。「行動評価」や「プロセス評価」とも呼ばれ、仕事の成果だけでなく過程も評価対象に含まれています。
ピアボーナス
ピアボーナスとは、従業員同士で報酬を送りあえる制度です。金銭的な報酬の場合もありますが、「称賛のメッセージ」や「社内ポイント」といった非金銭的な報酬であることが一般的です。
OKR
OKRとは「達成目標(Objectives)」と目標の達成度を測る「主要な成果(Key Results)」を設定することで、組織としての目標達成を目指す管理手法。目標は社内やチーム全体に共有され、60~70%の達成水準を目指すことが特徴です。
4. 人事評価制度の作り方
人事評価制度を導入する際は、次のようなステップに沿って進めるのが一般的です。
① 自社の人事課題を洗い出す
まずは、自社の現状を把握することから始めます。
自社に現在どのような課題があるのか、例えば「社員が自身は適切に評価されていないと感じ、モチベーションが低下している」「社員のスキルや適性が把握できておらず、人材配置がうまくいっていない」といった問題点を整理します。
② 導入目的を明確にする
課題を踏まえて、自社において制度を導入する目的を定めます。
これは制度設計の判断基準になるだけでなく、「なぜ人事評価制度が必要なのか」を社内に説明する根拠にもなります。目的は、人材育成や従業員満足度向上、業績改善といった組織の方向性に結びつけて設定すると効果的です。
③ 他の人事制度との連携を決める
等級制度(社員のランク付け)や報酬制度(給与・賞与・退職金など)との関係性を整理しましょう。人事評価はこれらと密接に結びつくため、バランスの取れた制度設計が求められます。
④ 評価項目・評価基準を設計する
評価の対象とする項目を決めます。一般的には以下のような観点が使われます。
- 業績評価:成果や数字による評価
- 役割評価:与えられた役割への貢献度
- 職務評価:担当業務の難易度や責任範囲
- 能力評価:スキルや知識の活用度
- 行動評価:成果につながる具体的な行動
- コンピテンシー評価:成果を出す社員に共通する行動特性
- 360度評価:上司・同僚・部下など多方面からの評価
- 年功評価:勤続年数や長年の貢献度
また、評価期間(3カ月や6カ月ごと)や、「絶対評価」と「相対評価」のどちらを採用するかも合わせて設計しましょう。
⑤ 評価結果の待遇への反映方法を決める
評価をどのように給与や昇進に反映させるかをルール化します。
等級制度と報酬制度を組み合わせるケースが多い一方、あえて序列をつけない「ノーレイティング」を導入する企業も増えています。後者の場合は、上司の裁量に基づいた対話を重視する運用が一般的です。
⑥ 評価者(管理職)を教育する
制度の公平性を保つためには、評価者となる管理職への研修が不可欠です。
評価の偏り(人事評価エラー)を防ぎ、公正な評価ができるよう教育を徹底しましょう。
評価マニュアルの整備も効果的です。
⑦ 社員への周知と運用開始
評価者の準備が整ったら、社員に制度の内容と意義を周知します。
これにより「会社はどの基準で評価するのか」が明確になり、従業員も目標設定や行動計画を立てやすくなります。
⑧ 定期的な振り返りと改善
制度は導入して終わりではありません。
定期的に運用状況を振り返り、必要に応じて改善を加えましょう。従業員満足度調査と連動させることで、制度の効果を客観的に評価できます。
5. 人事評価制度の運用でよくある問題と解決策
人事評価制度を運用するにあたって、よくある問題点とその解決策をご紹介します。
評価者同士の目線が合っていない
評価者によって評価基準にばらつきがあると、公平な評価はできません。評価に偏りが起こる原因には、一部の特徴によって評価が歪められる「ハロー効果」や、評価者自身と部下を比べることで起こる「対比誤差」など、無意識的な感情や心理が影響していることがあります。
明確な評価基準を設けることはもちろん、評価者向けの研修を行い、評価に必要なスキルを身に着けてもらいましょう。
評価制度の運用自体が目的となってしまう
評価プロセスを回すことで従業員のキャパシティが一杯になり、運用自体が目的化してしまうこともよくあるエラーです。人事評価制度があっても、形骸化しては意味がありません。近年では、人事評価に役立てられるクラウドサービスが多数登場しています。このようなサービスを利用することで、人事の負担を大幅に軽減できるでしょう。
目的がはっきりしていない
「そもそも何のために人事評価を導入するのか」という点が明確になっていないと、適切な人事評価制度の導入はできません。人事評価制度の目的は、自社のビジョンや価値観を踏まえたうえで決定するのがポイントです。目的がはっきりしていると、従業員側も努力の方向性をイメージしやすくなります。
6. 評価制度策定のための3つの判断ポイント
ここからは、評価制度を導入する際のポイントを3点ご紹介します。
自社のビジョンに合っているか
自社のビジョンや企業風土にあっていない評価制度では、適切な効果が得られません。たとえば、経営方針の全社共有を重視したい場合と、適正な人材配置を目的にしている場合では導入すべき評価制度が変わります。人事評価制度の導入の前に、実際の評価結果を想定したシミュレーションを実施し、求める効果が得られるかをチェックしましょう。
メリット・デメリットを把握しているか
前述のとおり、評価制度にはそれぞれメリット・デメリットがあります。たとえば、複数の立場の人が行う360度評価の場合、多くの人から納得感が得られやすい一方、高い評価を得るために行動が偏ってしまうこともあるでしょう。それぞれのメリット・デメリットを把握し、自社にあった評価制度を取り入れることが大切といえます。
導入に必要な手順を踏めるか
評価制度の導入には、全体像の構想から処遇に反映する仕組みの策定、従業員への説明会の実施、評価者の研修など多くのプロセスが必要です。
評価制度の導入に際して、時間的・人的リソースが十分に割けないのであれば、運用する前に問題が発生する可能性が高いでしょう。それぞれのプロセスをしっかり調査したうえで、導入可否を判断することも大事なポイントです。
7. ユニークな評価方法を導入する企業事例2選
様々ある評価方法の中でも、ユニークな方法を導入している企業がこちらです。
- 株式会社メルカリ/OKR
- アソブロック株式会社/年俸宣言制度
1つずつ内容を紹介します。
株式会社メルカリ/OKR
OKRとは企業における目標の設定・管理方法で、Objectives and Key Resultsの略称です。OはObjectives(目標)、KRは Key Results(主要な成果)を意味し、日本語でOKRは「目標と目標達成に必要である主要な成果」という意味合いを持ちます。具体的には、社員全員が同じ方向性を目指し、明確な優先順位を持って取り組むべき業務を進行する仕組みです。OKRは従来の方法に比べ、目標設定・進捗の確認・評価の頻度が高く、短いサイクルで回していくことが特徴の1つです。
そして株式会社メルカリでは、3ヶ月という短期間でOKRのサイクルを回しています。スピード感を持った組織の成長を目的としており、変化が激しいIT業界では機会損失を減らす効果が期待できます。OKRの設定においては「ワクワクする」内容を心がけることで、チャレンジングな企業文化を生み出しました。OKRは企業が目指す方向性に基づいた設定によって、企業の発展や風土を築くきっかけとなるでしょう。
アソブロック株式会社/年俸宣言制度
年棒宣言制度は自分の価値を自ら設定する、アソブロック株式会社独自の制度です。導入の背景には、会社の売上を目指す前に自分の価値を上げていく意識を根付かせ、個人の成長を促す目的があります。また年棒を自ら設定することは、給与に伴った社会保険料など社会の仕組みや自分の適正の実感につながります。そのため社員は納得できる範囲の最高額を貰う意義を理解でき、過剰な欲求は起こらないと言います。
そしてこの制度によって社員は自分と向き合う機会が増えるため、個人で内省するセルフマネジメントのスキルが必要となります。内省する機会を会社が仕組みとして作ることで、自分と向き合い考える能力の向上が期待されています。
8. 人事評価制度を廃止!ノーレイティングを採用した企業例
従来の人事評価制度を廃止し、新たな制度を採用する企業が増えていることをご存知ですか?新たな制度であるノーレイティングの概要とともに、以下の通り紹介します。
- ノーレイティングの概要
- 人事評価制度の廃止事例2社
ノーレイティングの概要
ノーレイティングはアメリカで生まれた概念であり、順位付けをしない新たな人事評価制度です。従来のように定期的に評価を下しランク付けを行うのではなく、リアルタイムで目標を設定しその都度フィードバックを行う特徴を持ちます。
【廃止事例1】アドビシステムズ株式会社
アドビシステムズ株式会社では、従来の人事評価制度を廃止し、上司が部下との継続的な面談を通し日々の成長を評価していく「チェックイン制度」を導入。面談の頻度や上司が投げかけるべき質問は定められておらず、面談では目標に対する達成点や改善点をその都度話し合います。導入の背景には、評価の不透明性や評価を下す負担といった、評価制度に対する社員が不満がありました。上司と部下のコミュニケーションの活性化や評価制度の効率化を重視した制度の導入によって、社員満足度は約30%もの向上を達成。
上司と部下の深い関係性の構築によって、評価内容に高い納得感を与えられ、社員の満足度を向上させています。
【廃止事例2】P&G株式会社
P&G株式会社も従来の人事評価制度を廃止し、様々な立場の社員にフィードバックを求められる「コーチング・フィードバック」というシステムを導入。このシステムはP&G株式会社が持つ「Feedback is a gift(自分が受けたフィードバックは大切な贈りものと考える)」という考え方によって社内で浸透しています。幅広い人々にコーチングやフィードバックを求めることで、自分自身に気づきを与え、考えや成果をより良いものとする効果が期待できます。また求められた社員は素直なフィードバックを行うことで、人材を育てるきっかけや意欲を感じられます。情熱を持った上司が誕生することで、次々と社員の成長が促され、企業としても大きな発展につながります。
ノーレイティングのデメリット
新しい評価制度として注目を集めるノーレイティングですが、以下のようなデメリットもあります。
管理職の負担になりやすい
ノーレイティングでは、定期的な面談が必要なため、上司の負担が増える傾向にあります。部下が多ければ多いほど、面談による時間的なコストや手間が増大します。
フィードバックしていくためのスキルが必要になる
ノーレイティングでは、状況に応じた目標設定やアドバイスが求められるため、高いマネジメント能力が必要です。上司のスキルが低ければ「正当な評価が受けられない」といった不満にもつながりかねません。公平な評価制度の設計とあわせて、上司のマネジメント教育も必須になるでしょう。
9.人事評価の運用に役立つツール
ラフールサーベイは、「社員の状況の把握・分析」や「職場/チームの状況に応じた改善策提案」をしてくれる、人事評価の運用に最適なサーベイツールです。人事評価を実施する前後のタイミングでサーベイを実施することで、簡単に効果測定を行うことができます。
また、従来の社内アンケートなどでは見えにくい心の状態などを可視化することで、社員が安心して働ける環境づくりのお手伝いをします。社員が安心して働ける環境づくりは、企業の成長・拡大のための土台となります。まずは、社員一人一人にとって居心地の良い職場を整え、人材の定着と組織改善に繋げましょう。
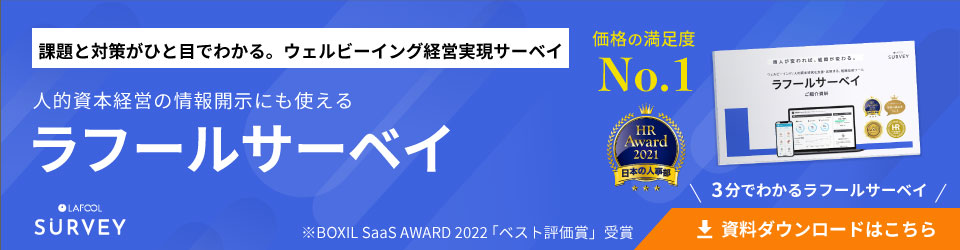
ラフールネス指数による可視化
組織と個人の”健康度合い”から算出した独自のラフールネス指数を用いて、これまで数値として表せなかった企業の”健康度合い”を可視化できます。また、他社比較や時系列比較が可能であるため、全体における企業の位置や変化を把握することも可能。独自の指数によって”健康度合い”を見える化することで、効率良く目指すべき姿を捉えることができるでしょう。
直感的に課題がわかる分析結果
分析結果はグラフや数値で確認できます。データは部署や男女別に表示できるため、細分化された項目とのクロス分析も可能。一目でリスクを把握できることから、課題を特定する手間も省けるでしょう。
課題解決の一助となる自動対策リコメンド
分析結果はグラフや数値だけでなく、対策案としてフィードバックコメントが表示されます。良い点や悪い点を抽出した対策コメントは、見えてきた課題を特定する手助けになるでしょう。
154項目の質問項目で多角的に調査
従業員が答える質問項目は全部で154項目。厚生労働省が推奨する57項目に加え、独自に約87項目のアンケートを盛り込んでいます。独自の項目は18万人以上のメンタルヘルスデータをベースに専門家の知見を取り入れているため、多角的な調査結果を生み出します。そのため従来のストレスチェックでは見つけられなかったリスクや課題の抽出に寄与します。
19の質問項目に絞り、組織の状態を定点チェック
スマートフォンで回答ができるアプリ版では、特に状態変容として現れやすい19の質問項目を抽出。質問に対しチャットスタンプ風に回答でき、従業員にとっても使いやすい仕組みです。こちらは月に1回の実施を推奨しており、組織の状態をこまめにチェックできます。
適切な対策案を分析レポート化
調査結果は細かに分析された上で適切な対策案を提示します。今ある課題だけでなく、この先考えられるリスクも可視化できるため、長期的な対策を立てることも可能。課題やリスクの特定から対策案まで一貫してサポートできるため、効率良く課題解決に近づくことができます。
部署/男女/職種/テレワーク別に良い点や課題点を一望化
集められたデータは以下の4つの観点別に分析が可能です。
- 部署
- 男女
- 職種
- テレワーク
対象を絞って分析することで、どこでどんな対策を打つべきか的確に判断できるでしょう。また直感的にわかりやすいデータにより一目で課題を確認でき、手間をかけずに対策を立てられます。
10.まとめ
人事評価制度は設定した基準に沿った評価で社員の処遇を決定する制度です。会社の方針によって目的や種類を設定でき、導入することで人材育成の効果も期待できます。今回は目的や種類、企業の導入事例など制度の導入や見直しに役立つ内容を紹介しました。
ラフールサーベイでは18万人以上のデータをもとに、従来のアンケートでは見えにくかったリスクや課題を多角的に抽出し可視化することができます。
人事評価制度とサーベイツールをあわせて導入することで、社員のメンタル面のサポートも手厚く行えるので社員のエンゲージメントを高めることが期待できます。
サーベイツールをお探しの方は、ぜひラフールサーベイを検討してみてください。