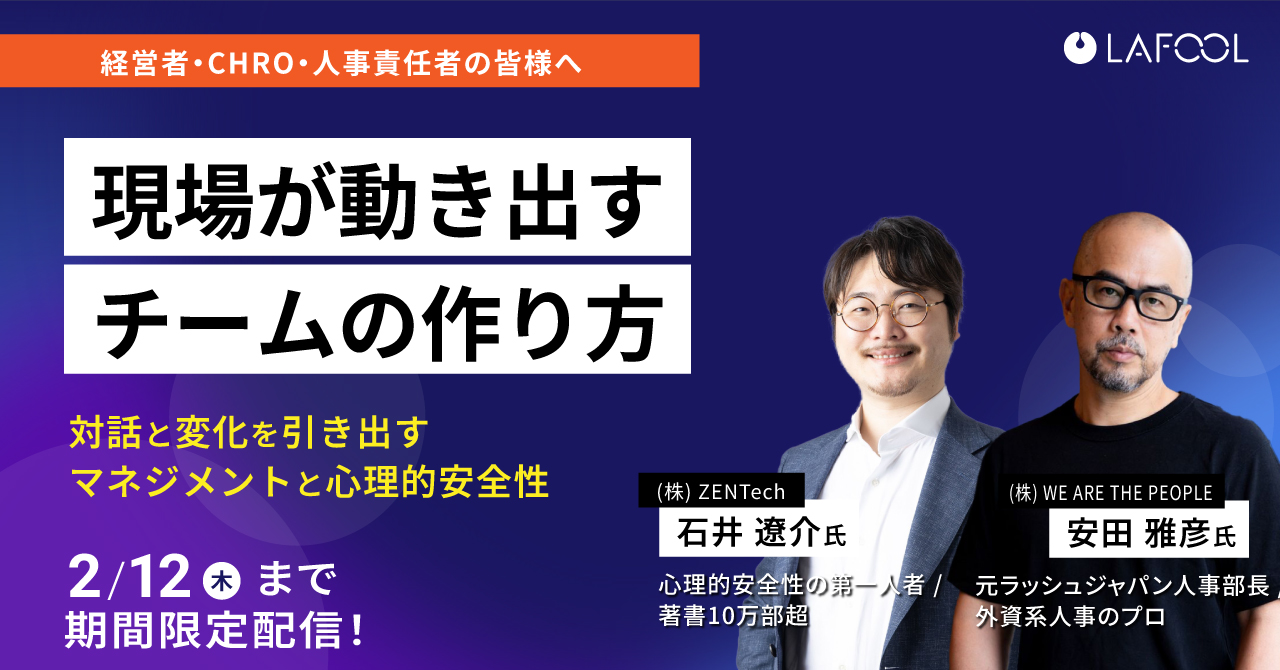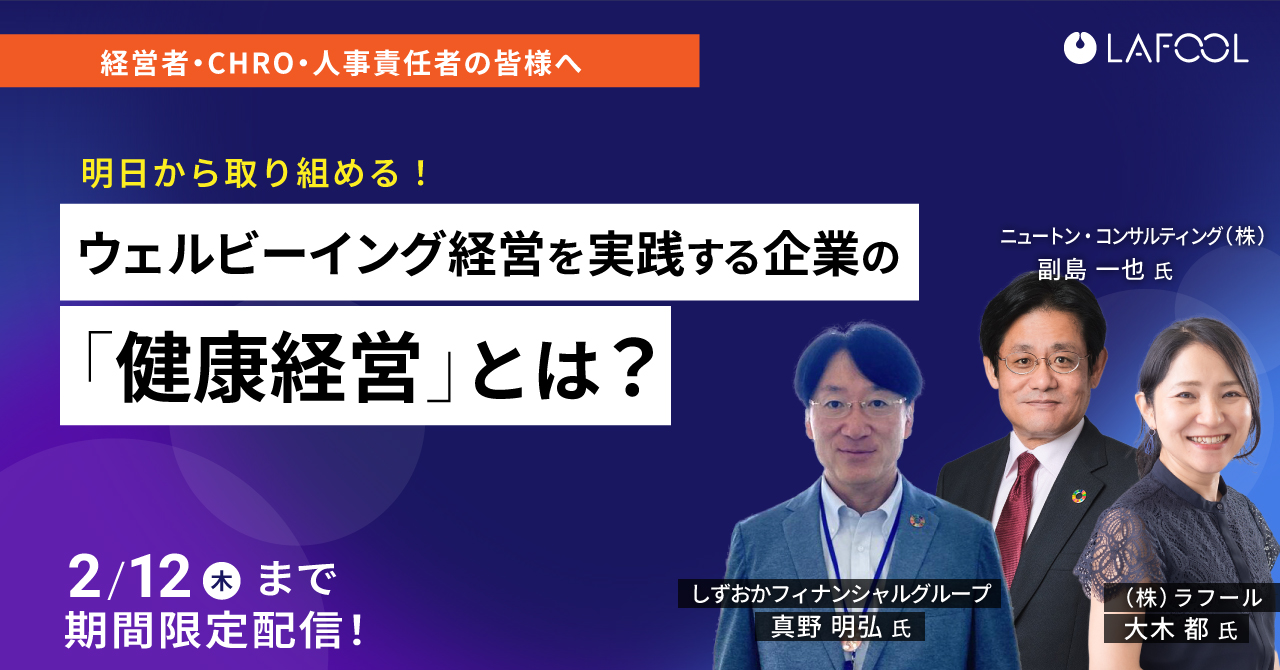「人材版伊藤レポート」とは、2020年9月に経済産業省が発表した報告書「持続的な企業価値向上と人的資本に関する研究会」による報告書のことです。
近年注目される人的資本経営が脚光を浴びるきっかけとなったレポートで、実際に企業が導入する際に参考となる視点や要素、事例が盛り込まれています。
この記事では、人的資本経営の基本事項を確認しながら、「人材版伊藤レポート」の内容をポイントを押さえて解説します。
1.人的資本経営とは?
人的資本経営とは、人材に焦点を当てた、近年注目されている新たな経営のあり方です。
経済産業省によれば、「人的資本経営とは、人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」を意味します。
引用元:経済産業省| 人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~
従来、日本企業は、人材を「資源」や「コスト」として捉えてきました。対して、人的資本経営の考え方では、人材を「資本」や「投資」と捉えます。これまでの考え方と大きく違うポイントは、人材の価値を伸び縮みするものと理解し、人材をただ管理・消費するのではなく、「資本」と捉えて投資を行う点です。こうした人材戦略により、企業の中長期的な価値向上が見込まれます。
すでに欧米では、経営戦略と人材戦略を統合した経営手法が主流となっています。
企業の人材に対する関心がますます高まっている中、「人材」を重視する経営スタイルは、特にこれからの時代に適合した取り組みであると言えます。
2.なぜ今、人的資本経営が重要なのか?
「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」で座長を務めた伊藤邦雄氏は、人的資本経営が重視する背景にある主要な点として、「無形資産の重要性」と「人材の軽視・メンバーシップ型雇用の限界」を挙げています。以下では要点をまとめて解説しています。より詳しく知りたい方は、経済産業省が公開している講演動画も参照してみてください。
引用元:経済産業省主催「人的資本経営という変革への道筋」より「基調講演『人的資本経営の意義について』(一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤氏)」
2-1.無形資産の重要性
1990年代以降、世界では企業の競争力の源泉が、実物的な生産設備などの「有形資産」から研究開発や人材などの「無形資産」へと大きくシフトしました。特に米国では、1993年頃以降、無形資産への投資が有形資産への投資を上回るようになり、成長企業は無形資産への投資によって自社の企業価値を増大させてきました。
一方、日本では1990年のバブル崩壊以降、「失われた10年」が続きました。この期間、多くの企業が設備投資や財務再建に追われ、無形資産、特に人材への戦略的投資が後回しになりました。その結果、グローバルな無形資産競争で大きく後れを取ることとなり、経済成長の停滞を招いたのです。
2-2.人材の軽視とメンバーシップ型雇用の限界
日本企業では伝統的に「人材は大切だ」という価値観が語られてきました。しかし実際には、社員個人への深い理解や、戦略的な育成・活用には至っていない例が多く見られます。
とくに「メンバーシップ型雇用」(=長期雇用を前提とする、職務を定めずに人材採用を行い、人に合わせて役割を割り当てる制度)は、現代の多様化・変化の激しい環境ではその限界が露呈しています。企業は「社員は簡単には辞めない」という楽観的な前提で人材マネジメントを設計しており、OJTを中心とした属人的な教育や、企業における人材領域への曖昧な態度が温存されてきました。
加えて、従業員のやりがいやウェルビーイングへの配慮も不十分でした。「社員がかわいそうだから」といった情緒的な理由で低採算事業を存続させるような判断が、結果的に人材の最適化を妨げてきた側面もあります。
3.伊藤レポートとは?人的資本経営との関係
「伊藤レポート」とは、2020年9月に経済産業省が発表した報告書「持続的な企業価値向上と人的資本に関する研究会」によるものです。
経済産業省は、2020年1月から「人材戦略に関する経営陣・取締役・投資家それぞれの役割や、投資家との対話の在り方、関係者の行動変容を促す方策等を検討する」ことを目的として、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」を開催しました。
同年9月に、研究会で座長を務めた一橋大学名誉教授の伊藤邦雄氏による報告書が公表されました。通称「人材版伊藤レポート」と呼ばれ、大きな注目を集めています。
全49ページのレポートは、以下の3章で構成されています。
- 第1章 持続的な企業価値の向上と人的資本
- 第2章 経営陣、取締役会、投資家が果たすべき役割
- 第3章 人材戦略に求められる3つの視点と5つの要素
レポート内では、今後の理想とされる人材戦略として「3P(Perspectives:視点)・5F(Factors:要素)モデル」を提唱しています。
引用元:経済産業省| 人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~
伊藤レポートが発表された背景
伊藤レポートの背景には、近年の日本における社会・産業構造の変化があります。
①産業構造の変化と、人生100年時代の多様な働き方
近年企業は、第四次産業革命をはじめとした産業構造の急激な変化のみならず、少子高齢化、人生100年時代の到来、さらには個人のキャリア観の変化の波の渦中に存在しています。
特にこの数年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、働き方の変化が強く求められるようになりました。従業員の働きやすい環境、多様な選択ができるよう、リモートワークを取り入れたり、従業員のニーズに柔軟に対応できる制度を設ける必要があります。
加えて、企業価値の向上を目指すうえでは、多様な人材が参加することによるイノベーションや価値の創造が重視されています。
変化する環境の下において、企業価値を生み出すための大きな役割を果たし得るのが、人材への投資と言えるでしょう。
②表裏一体となる企業の経営戦略と人材戦略
さまざまな経営課題を解決するためには、企業の存在意義(パーパス)に立ち戻り、人材戦略と経営戦略を同期させる必要があります。そのためにも人材の確保・育成、イノベーションを生み出す環境の整備など、人材に対する投資がますます重要になっていきます。
③ESG投資における「S」への注目
人的資本経営は、ESG投資の判断を下すうえでも注目されています。
ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとった言葉です。経済成長が進む中で、気候変動をはじめとする環境への負荷や、労働環境等に関する社会的課題、さらには企業による不正などのガバナンス(企業統治)の問題が顕在化してきました。「こうした課題の解決に向けて努力する企業こそが、持続的に成長する企業である」という考えに基づき、投資家たちは「ESG」の視点を投資の判断に組み込むようになりました。
ESGの中でも、特に S(ソーシャル)要因が人的資本経営と密接に結びついています。人的資本経営は投資家たちからも注目される要素となったのです。
4.「伊藤レポート」が提言するステークホルダー別の役割・アクション
伊藤レポートには、経営陣・取締役・投資家の3つの視点から求められるアクションが重要だと語られています。

①経営陣
①-1.企業理念、企業の存在意義(パーパス)や経営戦略の明確化
企業の社会的な存在意義を明確にすることによって、競争優位性を明確化することにもつながります。またリモートワークの環境下でも、従業員が企業理念を理解することで、業務に従事しやすくなります。
また、経営陣が経営戦略における達成目標を明確にすることは、人材戦略の目標を具体的アクションにつなげるうえで必要不可欠です。
①-2.経営戦略と連動した人材戦略の策定・実行
経営陣は、経営戦略上重要な人材アジェンダを特定することが求められます。そして重要な人材アジェンダごとに、目指すべき将来の姿(To be)を定性的な指標ではなく、定量的な KPI を用いて設定する必要があります。さらには設定したKPIについて、現在の姿(As Is)を正確に把握した上で、理想と現状のギャップを定量化し、そのギャップをどのように埋めていくかといった人材戦略を策定・実行することが求められます。
①-3.CHRO の設置・選任、経営トップ 5C の密接な連携
経営陣は、CEO(最高経営責任者)の戦略パートナーとなるCHRO(最高人事責任者)を設置する必要があります。CEOを筆頭に、CSO、CHRO、CFO(最高財務責任者)、CDO(最高デジタル責任者)の経営陣が、密に連携を取りながら、経営戦略を実行することがポイントです。
①-4.従業員・投資家等への積極的な発信・対話
経営陣は、自社の企業理念や存在意義、人材戦略について、従業員に積極的に発信を行い、対話すべきとされています。同様に、経営陣は投資家に対しても、自社の人材戦略と経営戦略の連動や人材戦略の取り組みの進捗に関して、情報を可視化し、発信・対話することが求められています。
②取締役会
②-1.人材戦略に関する取締役会の役割の明確化
経営陣が査定した経営戦略、事業ポートフォリオが人材戦略と連動しているかなどを確認していくことが、企業の成長にとって重要です。取締役会は、企業の人材戦略を承認し、監督・モニタリングするという役割を負っています。
②-2.人材戦略に関する監督・モニタリング
経営陣が策定した人材戦略が経営戦略と連動しているか、企業価値の向上につながるかを確認したうえで承認を行い、人材戦略の議論をあるべき方向に導くことが取締役会の責任です。また実行過程においては、定期的にKPIを用いながら、人材戦略の実行状況について経営陣と議論することも必要となります。
CxO(企業における「最高〇〇責任者」の総称)や将来の幹部候補など、企業経営にとって重要な人材の後継者計画が適切に策定・運用されているかを監督することも、取締役会に求められる点です。加えて、人材戦略の実行プロセスで醸成される企業文化の定着化についても議論すべきとされています。
③投資家
③-1.中長期的視点からの建設的対話
持続的な企業成長のために、機関投資家は人材戦略に関する知見を高め、積極的に対話を行うことが推奨されています。ESG要因の中でも近年ではS(ソーシャル)が注目され、S要因の高さが、企業の株価パフォーマンスに影響しているとも言われています。こうした観点から経営陣との建設的な対話を行うことが、投資家に求められるポイントです。
③-2.企業価値向上につながる人材戦略の「見える化」を踏まえた対話、投資先の選定
投資家は対話や議論を通して、投資先企業の経営戦略・人材戦略を把握した上で、持続的成長が見込まれる投資先を選ぶことが求められています。
5.「伊藤レポート」が提言する3つの視点
【視点①】経営戦略と人材戦略の連動
企業価値を向上させるには、経営戦略・ビジネスモデルと人材戦略は表裏一体で、企業に適した人材戦略を考えることが求められます。経営戦略を意識しながら、人材ポートフォリオの充足を行ったり、人材アジェンダについて、具体的な戦略・アクション・KPIを考えたりすることが有効です。
【視点②】As is-To beギャップの定量把握
人材アジェンダにKPIを用いて、現在の姿(As is)と理想の姿(To be)を定量的に把握し、人材戦略と経営戦略の連動について評価します。投資対効果に関しても定量的に把握し、ステークホルダーに開示・発信していくことが重要です。
【視点③】企業文化への定着
企業理念、企業の存在意義(パーパス)、持続的な企業価値の向上に繋がる企業文化を定義し、従業員の会社へのエンゲージメントを向上させることが求められます。社員の企業文化の定着に向けて人材戦略を策定し、経営者が活発に発信することが必要です。
6.「伊藤レポート」が提言する5つの共通要素
【要素①】動的な人材ポートフォリオ
経営戦略を実現させるためには、将来的な目標から逆算して、人材を質・量の面において、充足・最適化させる事が必要です。
将来的な目標を明確にし、そこから逆算して必要となる人材要件を定義することが求められます。
【要素②】知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
持続的な企業価値向上のためには、個人の知・経験を尊重し、社員の多様な専門性・価値観を取り込むことが重要です。特に経営層の多様性スコアを上げることは、同時に売上高に占めるイノベーションの割合を上げることにもつながります。
【要素③】リスキル・学び直し
企業が社員のリスキル・学び直し・スキルシフトの促進をし、個人のスキル獲得に対して支援・投資することは、より一層重要になっていきます。
雇われる側だけではなく、雇い主側である経営陣も率先して自らのスキル・専門性を高めていくことが求められていきます。
【要素④】従業員エンゲージメント
従業員自身が仕事にやりがいを感じ、自発的に業務に取り組むことが求められる中、経営者側は社員のモチベーションを上げる環境づくりを積極的にするべきです。
両者が対等な関係の下で積極的に対話し、オープンな関係を築いていくなど多様な個人としっかり向き合うことが、企業における価値創造の最大化につながります。
【要素⑤】時間や場所にとらわれない働き方
新型コロナウイルスの感染拡大により、社員個人に合った働き方や、働く環境を設定していくことが、事業継続において重視されてきています。
リモートワークや在宅勤務を単に取り入れるのではなく、そのような環境下でも、円滑なコミュニケーションや、人材のマネジメント方法を育成することが課題となっています。
7.伊藤レポート2.0とは?
2020年に公表された「人材版伊藤レポート」は、多くの企業に人的資本経営への意識変革を促しました。その後、企業の関心はさらに高まり、より実践的な取り組みへの要請が高まったことから、2022年5月、経済産業省は「人的資本経営の実現に向けた検討会」の報告書兼実践事例集として、通称「人材版伊藤レポート2.0」を公表しました。
7-1.伊藤レポート2.0の背景
経営環境の変化と企業の対応課題
この2年の間に、企業を取り巻く環境は大きく変化しました。デジタル化や脱炭素社会への転換、さらにコロナ禍による人々の価値観の変化は、従来型の人材マネジメントに再考を迫るものでした。こうした変化に伴い、「経営戦略と人材戦略の一体化」がこれまで以上に困難になってきたという課題も浮上しています。
世界と日本の対応差
一方、海外では人的資本に関する情報開示の機運がさらに高まっています。日本でも、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードにおいて、人的資本に関する記載が盛り込まれたものの、具体的な実行に移す段階では多くの企業が模索状態にありました。
7-2.伊藤レポート2.0の位置づけと特徴
こうした背景を踏まえ、経済産業省は「人的資本経営の実現に向けた検討会」を設置し、「人材版伊藤レポート2.0」を公表しました。本報告書では、前回の提言を土台にしながらも、人的資本経営をいかに現場で具体化し、実践するかという視点が重視されています。
また、レポートには企業の取り組み事例も多数紹介されており、単なる理念提示にとどまらず、実務者が自社に応じた施策を検討するうえでのヒントが散りばめられています。
「人的資本」の重要性が再認識できると共に、具体的な企業事例や調査結果も豊富なため、各企業において人的資本経営を実践する際のアイディアの引き出しとしても活用できます。
8.伊藤レポート3.0とは?
さらに2022年8月、経済産業省は「伊藤レポート 3.0(SX 版伊藤レポート)」を公開しました。こちらは、「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」の報告書となっており、SX実践の重要性を踏まえてSXの実現に向けた具体的取り組みを整理したものです。
SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを同期させ、そのために必要な経営・事業の変革を行い、長期的かつ持続的な企業価値の向上を図ることを意味します。
参照元:経済産業省|「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス2.0」を取りまとめました
9.まとめ
「人材版伊藤レポート」は人的資本経営をさらに掘り下げ、実践していく方法が記載されています。経営戦略と人材戦略をどう連動し、人的資本経営へ導くか、具体的なアイディアが盛り込まれたガイドになります。人的資本経営を取り入れるためのモデルケースがいくつか提示されているため、多くの企業にとって参考になることでしょう。
「人材版 伊藤レポート」を通して、人的資本経営の理解をさらに深め、自社の取り組みに活かし、企業価値向上に繋げてみてはいかがでしょうか。