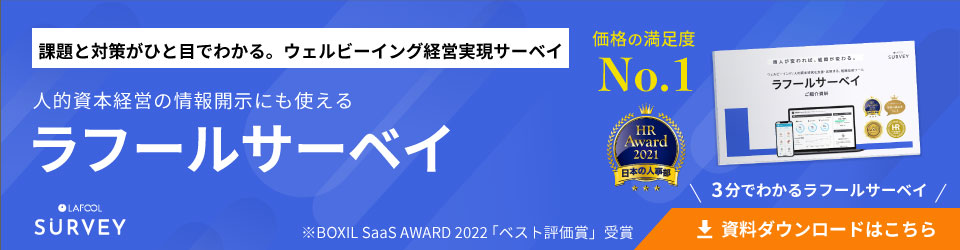近年「エンゲージメント」という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか?
VUCA時代と呼ばれる予測不能な現代において、企業が持続的に成長していくためには、社員一人ひとりが高いエンゲージメントを持ち、自律的に業務に取り組むことが不可欠です。
「エンゲージメントが重要だとは聞くけれど、具体的に何をすれば向上するのか」「どのようにすれば、エンゲージメントを組織全体の力に変えられるのか」と疑問を感じている人事担当者の方も少なくないでしょう。
本記事では、そもそもエンゲージメントとは何かという基本から、エンゲージメントが低いとどうなってしまうのか、そして明日から実践できる具体的な向上戦略まで、人事担当者の皆様が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
エンゲージメントを向上させ、組織を活性化させるためのヒントをぜひ見つけてください。
エンゲージメントとは
ビジネスシーンにおけるエンゲージメントとは、「企業と従業員の関係性」「自社と顧客の関係性」のことを指します。
ここでは従業員エンゲージメント、顧客エンゲージメント、従業員満足度やロイヤリティとの違いについて解説します。
従業員エンゲージメントとは
従業員エンゲージメントとは、従業員が仕事に対してポジティブで充実した心理状態であることを意味します。
- 仕事に対して誇り・価値を感じている
- 企業に対して信頼感・愛着を感じている
- 企業の目的達成のために自主的に貢献している
企業側は従業員の貢献に対して報酬、補償を約束します。
このように、お互いが貢献し合える関係性を、従業員エンゲージメントと呼びます。
エンゲージメントとロイヤリティの違い
エンゲージメントに似た言葉に、「ロイヤリティ」という言葉があります。
ロイヤリティは、英語で「loyalty」と綴り、日本語に翻訳すると「忠誠・忠実」という意味です。
企業における「ロイヤリティ」とは英語の意味のとおりで、従業員の企業に対する忠義心を意味します。
従業員エンゲージメントは企業と社員が同等な立場であるのに対し、ロイヤリティは主従関係を前提とする、といった違いがあります。
エンゲージメントと従業員満足度(ES)は違うもの?
「従業員満足度(ES)」も、エンゲージメントと同じような場面で使われる言葉です。しかし、それぞれの言葉が意味するところは微妙に異なります。
「従業員満足度(ES)」とは、その名のとおり従業員の会社での満足度を指す言葉で、業務内容や人間関係、職場環境などに従業員が満足しているかを表します。
従業員満足度は従業員から会社への一方的な評価のことで、具体的には、給与が高い・福利厚生が整っているなどが上げられるでしょう。
対してエンゲージメントは、従業員が満足しているだけでなく、企業に対してもしっかりコミットしてくれている状態であることを指します。
なぜ今、従業員エンゲージメントが重要視されるのか?
近年、労働人口の減少により優秀な人材の確保が難しくなり、企業間での人材獲得競争が激化しています。
働き方や価値観が多様化し「やりがい」や「ワークライフバランス」を重視する人が増加しており、転職も一般的になった今、従業員エンゲージメントの重要性はかつてないほど高まっています。
エンゲージメントを高めることで、離職率の低下や生産性の向上、イノベーションの促進といった具体的なメリットが得られます。
社員が仕事や組織に深い愛着を持つことで、企業文化も活性化し、社内外から「働きたい」と思われる魅力的な組織へと進化できるのです。
エンゲージメントが低いとどうなる?
従業員の離職につながる
企業に対する従業員のエンゲージメントが低い場合、従業員の離職に直結してしまいます。
なぜなら、現代は個人が自律的にキャリアを設計する時代だからです。
終身雇用・定年まで勤め上げるという働き方・価値観は変化しており、転職・独立することが当たり前となっています。
従業員にとって会社を離れることに対するハードルが以前よりも下がっており、信頼感・愛着の感じられない企業からは離職してしまう可能性が高いです。
業績の低下
企業への従業員のエンゲージメントが低下すると、企業の業績に影響を及ぼしかねません。
なぜなら、エンゲージメントが低い状態というのは、業務にやりがいを感じていない状態だからです。
業務にやりがいを感じられず、ただの作業として捉えてしまうと、結果的に生産性が下がります。
特にクリエイティビティを求められる職種では、エンゲージメントの低下は業績の悪化に直接的な影響を与えるでしょう。
従業員のエンゲージメントを高めるために必要なこと

従業員のエンゲージメントを高めるためには、以下の4つの要素を複合的かつ継続的に取り組むことが重要です。
社内の現状を把握する
まず、従業員ひとりひとりの価値観や考え方など、現在の状況を把握する必要があります。
「仕事に対してやりがいを感じているか」「私生活と仕事のバランスについてどう考えているか」など、従業員が仕事や企業に対してどういった認識を持っているのか社内アンケートを行うのがおすすめです。
研修・教育を実施する
定期的な研修や教育は、従業員の意欲向上や業務の効率化にも繋がります。
指導する側の従業員にも重要な気づきをもたらしたり、さまざまな変化が期待できるでしょう。
指導する側の従業員が成長することで、新入社員の悩みや不安を取り除くための対応ができるようになり、離職防止にも繋がります。
人事評価制度の整備
公平で納得感のある人事評価制度は、従業員のモチベーションとエンゲージメントを大きく左右します。
どのような行動や成果が評価されるのかを明確にし、従業員が納得できる公平な評価基準を設けることが重要です。評価プロセスも透明化し、ブラックボックス化を防ぎましょう。
評価結果を伝えるだけでなく、なぜその評価になったのか、今後どのような行動が期待されるのかを具体的にフィードバックすることが不可欠であり、特にポジティブな側面を伝え、成長を促す「ポジティブフィードバック」は、従業員のモチベーション維持に効果的です。
報酬が成果や貢献に見合っていると感じられることはエンゲージメントの基盤となるため、柔軟な報酬制度や福利厚生の見直しも検討すべき点です。
従業員の成長支援とキャリアパスの提示
従業員が自身の将来像を描き、その実現に向けて会社が支援する姿勢を示すことは、長期的なエンゲージメントを育みます。
従業員一人ひとりのスキルや志向性・適性を踏まえ、具体的なキャリアパスを提示します。
定期的なキャリア面談を通じて個人のキャリアプランを具体化し、それに対する会社の支援策を伝える個別のキャリアパスの提示と支援が必要です。
既存業務の中での挑戦機会の提供や新たなプロジェクトへの参画、ジョブローテーション、メンター制度の導入など、従業員が様々な経験を通じて成長できる多様な成長機会の提供も重要です。
会社が一方的にキャリアパスを示すだけでなく、従業員自身が主体的にキャリアを考え、形成していく「キャリア自律」を促すための支援も行いましょう。
従業員が働きやすい環境をつくる
エンゲージメントを高めるには、各従業員の特長を活かした配置がされているか、長時間労働が常態化したりしていないか、すべての従業員が健全に働けているかが重要です。
職場の雰囲気を良好に保つことも大切で、社内でのコミュニケーションを活性化させられるような取り組みを実施する必要があります。
リモートワークやフレックスタイム制度の導入といった柔軟な働き方は、従業員がワークライフバランスを保ちやすくし、ストレス軽減と満足度向上に繋がります。
エンゲージメントを高めるために欠かせない4つのポイント
1. 経営層の本気の関与が不可欠
従業員エンゲージメントの向上は、人事部門だけが担う課題ではありません。
最も重要なのは、経営層がその重要性を深く理解し、取り組みに積極的に関与することです。
トップがエンゲージメントを経営戦略の柱と位置づけ、自らが率先してその姿勢を示すことで、全社的な取り組みとして浸透しやすくなります。
例えば経営会議での進捗状況の共有、従業員への直接的なメッセージ発信、エンゲージメントに関する研修への参加などが挙げられます。
経営層の本気の姿勢は、従業員に対して「会社は私たちのことを真剣に考えている」という信頼感を与え、エンゲージメント向上の強力な推進力となるでしょう。
2. 一度で終わらない継続的な改善が重要
従業員エンゲージメントは、一度施策を実施すれば完了するものではありません。
組織の状況や従業員のニーズは常に変化するため、エンゲージメント向上への取り組みは一度で終わらせず、継続的に改善していくことが極めて重要です。
エンゲージメントサーベイなどを定期的に実施し、現状を把握するとともに、施策の効果を検証し、課題が見つかれば柔軟に見直していく「PDCAサイクル」を回す必要があります。
例えば特定の施策が期待通りの効果を上げなかった場合でも、そこで諦めるのではなく、その原因を分析し、新たなアプローチを試みる姿勢が求められます。
このように継続的な改善を重ねることで、組織は常に最適なエンゲージメント施策を見つけ、進化し続けることができるでしょう。
3. 従業員への丁寧な説明と巻き込みがカギ
エンゲージメント向上の取り組みを進める上で、従業員の理解と協力は不可欠です。
そのためには、「なぜエンゲージメントに取り組むのか」「どんな効果があるのか」といった目的を従業員へ丁寧に説明し、納得感を持ってもらいましょう。
単に施策を押し付けるのではなく、会社が従業員一人ひとりの働きがいや成長を本気で考えていることを伝え、共感を呼び起こしましょう。
また現場の声を聞いて施策内容に反映させることで、従業員は「自分たちの意見が尊重されている」と感じ、当事者意識を持って協力してくれるようになります。
アンケートや座談会、意見交換会などを通じて、積極的に従業員を巻き込みながら進めることが成功へのカギとなります。
4. 人事担当者の役割
従業員エンゲージメント向上における人事担当者の役割は、非常に多岐にわたります。
単に施策の企画や実行に留まらず、従業員一人ひとりと向き合い、信頼関係を築くことが求められます。
具体的には、1on1ミーティングやキャリア面談を通じて従業員の悩みや期待に耳を傾け、適切なサポートを提供します。
また、各部署のマネージャーやリーダーと密接に連携し、部署ごとの課題を共有して共に解決策を検討する「橋渡し役」としての役割も重要です。
経営層と現場の間に立ち、双方の意図を正確に伝えて円滑なコミュニケーションを促進することで全社的なエンゲージメント向上を強力に支えることができるでしょう。
組織の強みと課題を可視化する 組織改善ツール「ラフールサーベイ」
「あの社員、最近元気がない気がする…」「コミュニケーションをもっと取った方がいいのかな?」とお悩みの管理職や経営者の方も多いのではないでしょうか。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」は、1億2000万以上のデータを基に、従来のサーベイでは見えにくかった「なぜエンゲージメントが低いのか?」「高ストレス者のストレス因子は何?」といった低スコアの要因を可視化することができます。メンタル・フィジカルに関するデータはもちろん、eNPSや企業リスクなど組織状態を可視化する上で必要な設問を網羅しています。そのため、今まで気づかなかった組織の強みや、見えていなかった課題も見つかり、「次にやるべき人事施策」を明確にすることができます。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」について、詳しくは以下のWebサイトをご覧ください。

エンゲージメント向上に取り組む企業事例
スターバックスコーヒージャパン株式会社
スターバックスは、従業員を単なる「店員」ではなく「パートナー」と呼び、相互に尊重し合う文化を徹底しています。
エンゲージメントが高い理由の一つは、従業員の自主性を重んじる点にあります。
具体的な接客マニュアルを最小限にとどめ、従業員が顧客一人ひとりに合わせたサービスを提供することを推奨しています。
ドリンクカップへの手書きメッセージなども、従業員の自発的な行動から生まれたものです。
個人の成長目標を支援し、適切なフィードバックを行う人事考課も定期的に実施することで従業員は自身の貢献が評価され、会社と共に成長できる実感を得ています。
これにより、従業員の仕事への主体性や顧客満足度向上への意欲が高まり、企業のブランド価値向上にも繋がっています。
株式会社丸井グループ
丸井グループは一時的に業績が悪化した際に、従業員エンゲージメントの低さが原因の一つであると認識し、抜本的な改革に着手しました。
特徴的な取り組みは、従業員の「やりたい」という自発的な意欲を尊重し、それを会社の成長に結びつける仕組みを構築した点です。
例えば、会議への参加を挙手制にしたり、グループ会社間での職種変更異動を促進したりすることで、従業員が自身のキャリアを主体的に形成し、新たな事業領域に挑戦できる機会を提供しています。
このような施策の結果、従業員一人ひとりが生き生きと働ける環境が生まれ、それが業績改善や新たな事業展開へと繋がっています。
ロート製薬株式会社
ロート製薬は、従業員の成長と自律を促すことで、高いエンゲージメントを実現している企業です。
実践しているユニークな取り組みの一つに、社内でのダブルジョブの推進や社外での副業・兼業の許可があります。
これは従業員にあえて社外で多様な経験を積んでもらうことで、個人のスキルアップだけでなく、将来的にはそれが企業の新たな価値創造に繋がるという考えに基づいています。
また、全従業員が年2回キャリアビジョンシートを作成し、役員がそれを基に異動案を考案するなど、従業員のキャリア形成に深くコミットしています。
このような多角的な成長支援は、従業員が会社に貢献したいという強い意欲を持つことに繋がっています。
まとめ
VUCA時代において、従業員エンゲージメントは企業の持続的成長に不可欠な要素です。
エンゲージメントを高めるには、現状把握、研修・教育、人事評価制度の整備、成長支援とキャリアパスの提示、そして働きやすい環境づくりが重要です。
これらの施策は、経営層の関与、継続的な改善、従業員への丁寧な説明と巻き込み、そして人事担当者の橋渡し役によって成功へと導かれます。
従業員エンゲージメントは、単なる人事施策ではなく、企業の成長戦略そのものです。
本記事の内容を参考に、ぜひ貴社でもエンゲージメント向上への取り組みを加速させ、組織の潜在能力を最大限に引き出してください。