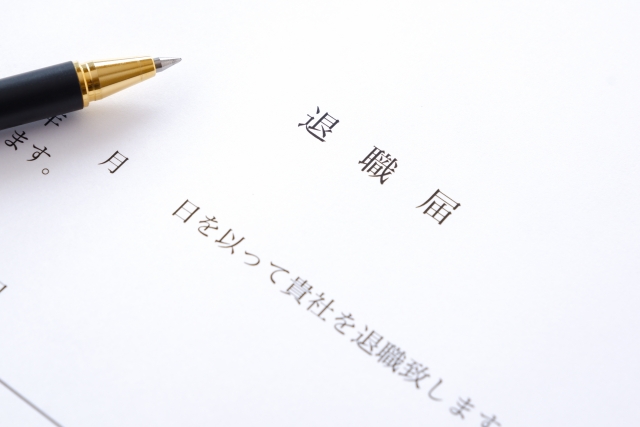会社を支えていた優秀な人材が突然辞めることは、現場に大きな衝撃を与えます。引き留められなかった後悔、残された社員への負担、そして経営へのダメージは計り知れません。
本記事では、優秀な人材が会社を見限る「本当の理由」と、彼らが辞める前に見せるサイン、そして離職を防ぐための具体的な対策を解説します。組織の未来を守るために、今すぐできる改善策を見つけましょう。
優秀な人材が辞める理由——経営を揺るがす「組織の病」
厚生労働省の「令和6年雇用動向調査結果の概況」によると、一般労働者(非パートタイム労働者)の離職率は12.1%となっています。
この数字だけを見れば「10人に1人が辞める程度」と感じるかもしれません。しかし、問題なのは「誰が辞めたか」です。パレートの法則によれば、成果の8割は組織の2割の社員に依存しているという傾向があります。つまり組織における重要人物が抜けた場合、その損失はただ1人社員が減った、というだけでは済みません。優秀な人材の流出は、組織にとって大きな問題であり、放置すれば経営基盤そのものを揺るがす事態となります。
参考:厚生労働省-令和6年雇用動向調査結果の概況-(PDF)
優秀な人材が会社を見限る「5つの本音」
優秀な人材は冷静に現状を分析し、将来を見据えた上で「辞める」という決断を下します。ここでは、彼らが抱える5つの本音を深掘りします。
1. 正当に評価・還元されていないという不満
待遇面での不満は、優秀な人材が辞める最も大きな要因の一つです。優秀な人材ほど自身の市場価値を正しく理解しており、出した成果に見合う対価を求めます。
単に給料が低いことだけが問題なのではありません。「成果を出しても出さなくても給料が変わらない」「年功序列で、自分より働かない上司の方が高給取りである」というように、納得できない状況が離職の引き金となります。人事評価制度や給与テーブルが実力主義に見合っていない場合、社員はより正当に自分を評価してくれる場所へと移動してしまうでしょう。
2. この会社では成長できないという停滞感
優秀な人ほど、仕事に対して成長を求めています。そのためルーチンワークばかりで新しいスキルが身につかない環境や、ロールモデルとなる先輩がいない職場など、成長できる環境が用意されていないと感じる場合には、離職を考える恐れが高くなります。毎日変わり映えのしない同じ業務を与えていたり、社員の実力に伴わない仕事を回していたりすると、やりがいを感じられなくなってしまいます。
「ここではもう学ぶことがない」「自分のキャリアが停滞している」と感じさせてしまえば、定着させることは困難です。優秀な人材を惹きつけ続けるには、常に挑戦的な課題や、スキルアップできる環境を用意する必要があります。
3. 会社の将来性やビジョンに共感できないという失望
視野の広い優秀な人材は、自社の課題や業界内での立ち位置を客観的に見ています。経営陣が現場の実情を無視した方針を打ち出したり、解決すべき問題が長年放置されていたりすると、彼らは会社に対して不安を感じるようになります。
自分のいる会社における問題点が改善されないと気づいたり、成長しづらい環境であると感じたりすれば、会社を離れる選択をするのも無理はないでしょう。
4. 挑戦が許されず、裁量権がないことへの窮屈さ
優秀な人材は、自分の頭で考え、行動し、結果を出すことにやりがいを感じます。それゆえ裁量権が全くない職場では窮屈さを感じてしまい、その能力を発揮できません。
例えば、年功序列の色が強い企業や、過度なトップダウン方式の業務体制の中では、優秀な人材は息苦しく感じてしまうでしょう。会社の今後の成長を考える上でも、若い優秀な人材にはある程度裁量権を与えることが重要です。
5. 特定の人に業務が集中する「やりがい搾取」への疲弊
タスクが集中してしまうことによる疲弊から、優秀な人材が会社を辞めてしまうことも多くあります。優秀な人材は処理能力が高いため、周囲が頼りにしてしまいがちですが、それが常態化すると「なぜ自分だけが」という不公平感が生まれます。さらに業務の集中が過度に進めば、メンタルヘルス不調や体調不良を抱えてしまい、職場を離れざるを得なくなる恐れもあります。
明らかにキャパシティを超えた業務量や、あまりにも短い締め切りでの仕事の押し付けなどは、社員の疲弊を招く要因となります。タスクが集中すると仕事の質自体も下がってしまうので、仕事量を分散させることが大切です。
【要注意】優秀な人材から「見切られる」会社、3つの共通点
特徴1:人事評価制度が曖昧で、上司の主観に左右される
評価基準の不透明さは、モチベーション低下の直結要因です。「数値目標を達成したのに評価されない」「上司に気に入られている社員だけが昇進する」といった状況では、社員は正しく評価されていると感じられず、モチベーションを維持できません。
明確で客観的な評価指標(KPI)や、360度評価などの公正な仕組みが整っていない場合、優秀な人材から見切られてしまう傾向にあります。
特徴2:部下を育てられない管理職が放置されている
実務能力が高くて管理職に就いたからといって、すべての人に十分なマネジメント能力が備わっているとは限りません。
部下の意見を潰す、フィードバックを行わない、手柄を横取りするといった管理職をそのままにしている場合、その下にいる優秀な部下は次々と辞めてしまいます。経営層が管理職のマネジメント能力不足を黙認している企業文化そのものが、離職の原因となり得るのです。
特徴3:「昔からこうだから」が通用する保守的な企業文化
「前例がない」「昔からこうだから」という言葉が飛び交う保守的な会社も、優秀な人材にとっては居心地の悪い場所です。
非効率な業務フロー、無意味なハンコ文化、形骸化した会議などが改善されないまま残っていると、合理性を好む優秀な人材は強いストレスを感じるでしょう。
変化に対して消極的な組織は、優秀な人材にとって、自身の成長スピードを鈍化させる環境のように感じられるため、より革新的でスピード感のある企業へと人材が流出してしまいます。
見逃すな!優秀な人材が辞める前に見せる5つのサイン
優秀な人材は、退職を決意するかなり前から、行動に変化(サイン)を見せています。
サイン1:会議での発言や新たな提案がなくなる
これまで積極的に発言していた社員が、急に聞き役に徹するようになったら要注意です。「意見を言っても無駄だ」と諦めているか、既に心が離れており会社を良くしようという意欲を失っている可能性があります。
サイン2:残業を減らし、定時退社や有給消化が増える
会社への貢献意欲が低下すると、会社のために費やしていた時間を「自分のための時間」へとシフトします。特に、急に定時退社が増えたり、半日休暇や有給休暇を頻繁に取得し始めたりする場合は、面接などの転職活動を行っている可能性が高いでしょう。
サイン3:同僚との雑談や飲み会を避けるようになる
退職を決意した社員は、周囲との心理的な距離を置き始めます。後ろめたさからか、あるいは「もう関係なくなるから」というドライな感情から、ランチや飲み会、雑談の輪に積極的に参加しなくなる傾向が高いです。
サイン4:会社の愚痴や批判的な言動が増える
以前は建設的な改善提案をしていた人が、単なる愚痴や皮肉を言うようになった場合、組織へのエンゲージメントが著しく低下していると言えます。周囲への悪影響も懸念されますが、これは彼らが抱える不満が限界に達しているSOSのサインでもあります。
サイン5:将来のキャリアに関する相談をしなくなる
1on1などの面談で、来期の目標や数年後のキャリアパスについて話したがらなくなった場合、その社員の未来予想図の中に、自社は存在していないかもしれません。今現在の仕事の話しかしなくなった時は、既に退職の意思を固めている可能性があります。
1人の離職では終わらない——優秀な人材の退職がもたらす深刻な経営リスク
チーム全体の生産性と士気の低下
優秀な人材は、チームの要であることがほとんどです。彼らが抜けることで、ノウハウや技術が失われるだけでなく、「あの人が辞めるなら、この会社はもう駄目かもしれない」という不安が他の社員に伝播します。結果としてチーム全体の士気が下がり、生産性が大きくダウンします。
他の社員の連鎖退職の誘発
最も恐ろしいのが「連鎖退職」です。優秀な社員が抜けた穴を埋めるために、残された社員の業務負担が激増します。その負荷に耐えきれなくなった社員が次々と辞めていく負のスパイラルが発生します。また、優秀な人材を慕っていた若手社員が後を追って退職するケースも珍しくありません。
数百万単位に及ぶ採用・育成コストの損失
社員1名を採用して戦力化するまでには、多くのコストがかかります。優秀な人材が辞めることで、これまで投資してきた育成コストがすべて水の泡となってしまいます。さらに抜けた穴を埋めるために、同レベルの人材を新たに採用するためのエージェント費用や教育コストが改めて発生するため、財務的なダメージも甚大です。
顧客からの信頼低下と企業ブランドの毀損
優秀な人材は、顧客からの信頼も厚いものです。「〇〇さんが担当だから契約している」という顧客も少なくありません。引継ぎがうまくいかなかったり、サービスの質が低下したりすれば、顧客離れを引き起こします。また、業界内での評判が悪化し、今後の採用活動に悪影響を及ぼすリスクもあります。
明日からできる!優秀な人材を惹きつけ、離さないための具体的対策7選

【仕組み・制度編】
1. 透明性と納得感のある人事評価制度を構築する
評価基準を明確にし、全社員に公開しましょう。「何をすれば評価されるのか」がクリアになることで、迷いなく業務に取り組めます。また、評価結果のフィードバックを丁寧に行い、本人が納得感を持てるプロセスを設計することが不可欠です。
2. 社員のキャリアパスを共に描き、成長機会を提供する
「この会社にいれば成長できる」と感じてもらうために、定期的なキャリア面談を実施しましょう。社内研修の充実、資格取得支援、あるいは副業の解禁など、社員が望むキャリアを実現できる選択肢を用意することが定着につながります。
3. 業務量を可視化し、適切な権限委譲を行う
特定の人材への負荷集中を防ぐため、タスク管理ツールなどで業務量を可視化します。その上で、優秀な人材には作業ではなく権限を渡し、裁量を持って働ける環境を整えます。同時に、勤怠管理システムで長時間労働をモニタリングし、アラートが出た場合は即座に調整を行うなどのケアも重要です。
【コミュニケーション・文化編】
4. 1on1ミーティングを形骸化させない仕組みを作る
1on1は単なる業務報告の場ではありません。部下の悩みやキャリアの希望を聞き出し、信頼関係を築く時間です。上司側の傾聴スキルを高め、本音で話せる心理的安全性の高い場として機能させる必要があります。
5. 管理職向けのマネジメント・コーチング研修を実施する
プレイングマネージャーが多い現代において、管理職へのマネジメント研修は必須です。部下の強みを活かすコーチングや、ハラスメント防止の知識を習得させ、組織全体のマネジメントレベルを底上げしましょう。
6. 退職者インタビュー(エグジットサーベイ)から本音を学ぶ
辞めていく人材の意見には、組織の弱点が詰まっています。形式的な手続きで終わらせず、第三者がインタビューを行うなどして本音を引き出し、その内容を経営課題として真摯に受け止め、次の改善に活かすサイクルを作ります。
7. 経営層が会社のビジョンと将来性を熱意をもって語る
優秀な人材をつなぎとめる最後の砦は「共感」です。経営層は、会社がどこを目指しているのか、社会にどのような価値を提供したいのかを、定期的に、そして熱意を持って社員に伝える必要があります。ビジョンへの共感が、困難な状況でも踏みとどまる求心力となります。
優秀な人材が定着・活躍する企業の取り組み事例
Googleでは、業務時間の20%を担当業務以外の新規事業立案などに充てられる「20%ルール」と呼ばれる制度を導入しています。
これによって、Googleの社員は日常の業務から離れて、クリエイティブな仕事に従事することができます。実際、この取り組みによって、Gmailなどの新しいプロダクトが生まれました。
このように、優秀な人材に能力を十分に発揮する機会を与えることも重要でしょう。
リクルートホールディングス
リクルートホールディングスは、優秀な人材が能力を発揮できるように柔軟な働き方を取り入れています。具体的な取り組みは、以下のとおりです。
- リモートワークの実施
- フレックスタイム制
- 男性育児休暇制度
- アニバーサリー⼿当
- 副業の自由化 など
こういった各個人のライフスタイルに合わせた働き方を導入することで、優秀な人材が働きやすい環境を作っています。
価値観の多様化した現在では、個人を尊重した働き方の導入は必須でしょう。
サイバーエージェント
サイバーエージェントでは、毎月社員の現状についてのアンケートを回収する「GEPPO」というシステムを導入しています。
具体的には、一人一人のコンディションやキャリア志向、抱えている問題などを調査します。この調査を基にして適材適所を図り、組織と個人のミスマッチを解消することに成功しています。
実は優秀な人材が、働かせる場所を間違えていることで能力を発揮できないことは多いです。個人個人の適材適所を図ることも重要な施策でしょう。
ココナラ
ココナラでは、OKR(Objectives and Key Results)を取り入れて、従業員のエンゲージメントを高めています。
OKRでは、会社の目標を基にチーム、そして個人の目標が設定されます。これによって、社員の働きが会社の目標に直結するようになるため、エンゲージメントが高まるというわけです。
優秀な人材は、仕事にやりがいを求めています。個人の働きが会社の役に立っていると見える化することが重要です。
まとめ:優秀な人材の定着は、企業の持続的成長の生命線
優秀な人材が辞める理由は、「給与」だけではなく、「成長実感」「裁量権」「将来性」など多岐にわたります。彼らの離職は、現場の負担増だけでなく、企業競争力の低下や連鎖退職のリスクも招きます。
重要なのは、離職のサインを見逃さず、手遅れになる前に手を打つことです。
透明性のある評価制度、心理的安全性の確保、そしてビジョンの共有。これらは一朝一夕には完成しませんが、継続的に組織改善を行い、優秀な人材が「ここで働き続けたい」と思える組織を作ることは、企業の持続的な成長にとって最大の投資となります。
まずは自社の現状と向き合い、できる対策から一つずつ始めていきましょう。
優秀な人材の採用と定着を科学するツール「テキカク」
長く働いてくれる優秀な人材を獲得することは、企業の存続と成長にとって非常に重要な課題です。採用活動を成功させるには、採用時に候補者の適性をしっかりと把握することがポイントとなってきます。そこで役立つツールが適性検査「テキカク」です。
「テキカク」は採用ミスマッチを防ぎ、候補者が自社の目指す組織の未来像において貢献できる人材かどうかを示してくれます。そして企業と採用候補者の的確なマッチ度を算出できるのには理由があります。それは、組織改善ツール「ラフールサーベイ」で蓄積されたデータの活用と、心理学×データ×AIで導かれた分析による裏付けがあるためです。
「テキカク」は「ラフールサーベイ」を導入していなくても利用できますし、スカウトサービスや採用管理システムなど、すでに自社が利用しているサービスにプラスオンする形で利用できるため、余計な手間がかからないのも魅力のひとつです。
採用ミスマッチを防ぎ、自社にマッチした優秀な人材を獲得するために、適性検査「テキカク」の導入を検討してみませんか?