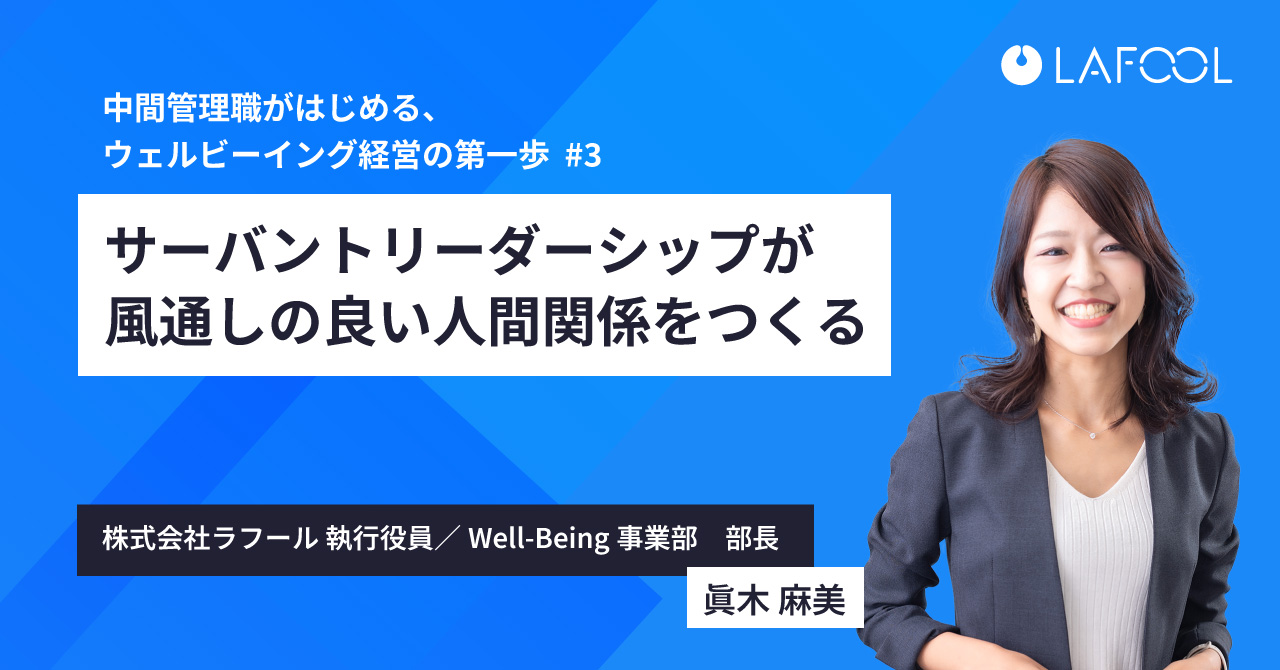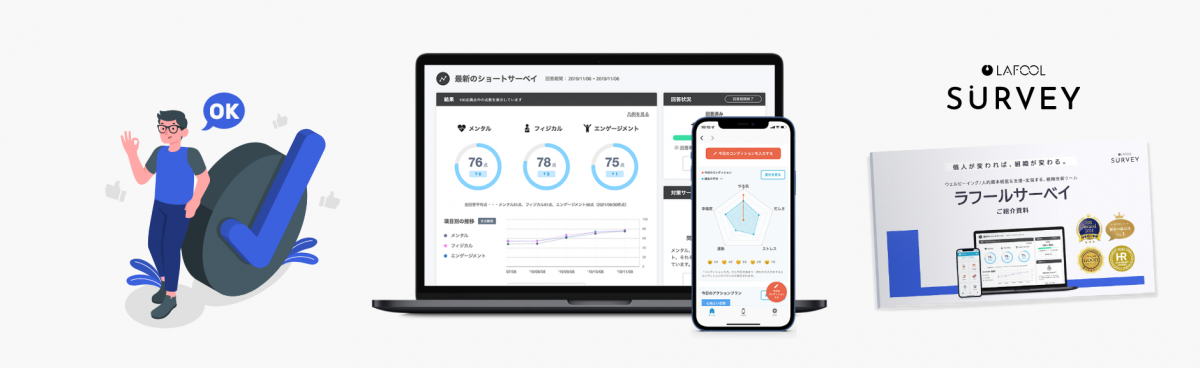このコラムでは、ラフールというベンチャー企業であり、お客様のウェルビーイングをご支援する会社の執行役員をやっている私の目線で、ウェルビーイングな環境をつくる『サーバントリーダーシップ』についてお話したいと思います。
このコミュニケーション手法で私自身、メンバー(部下)からの意見が増え、育成にもつながり、私自身のチャレンジの時間の創出にもなりました。日々、業務に追われ『部下が成長しない』『意見があがってこない』という方はご参考にしていただけると嬉しいです。
みなさま、こんにちは。株式会社ラフールの執行役員、眞木麻美です。
※私に関しての自己紹介はコチラ をご覧ください
サーバントリーダーシップとは
少し前から聞くようになった『サーバントリーダーシップ』という言葉。
まずはその言葉の定義から確認しましょう。
サーバントリーダーシップとは・・・
サーバントリーダーシップは、ロバート・グリーンリーフ(1904~1990)が1970年に提唱した「リーダーである人は、まず相手に奉仕し、その後相手を導くものである」というリーダーシップ哲学です。サーバントリーダーは、奉仕や支援を通じて、周囲から信頼を得て、主体的に協力してもらえる状況を作り出します。
出典:NPO法人日本サーバント・リーダーシップ協会HPより

自分自身が圧倒的上位に立ち、指示を出し実行してもらうとは全く別の世界観で、リーダー自身が下支えとなり、ひとりひとりのメンバーを導き自立させていく、ということを指します。
この考え方がウェルビーイング経営にどうつながっているのか?
分かる方には分かるかもしれませんが、要するに
やらせれ仕事ではなく、自分自身の意思を持ってやった仕事の方が、心も身体も健康で働きがいが継続される可能性が高い。
ということです。
当然のことですが、目的や意義が分からない業務をただこなすだけなのと、目的や意義を理解して、だれの何に役立つのかを意識してやる業務の方が楽しさを感じられますし、期待を超える仕事ができる可能性も高いので、結果相手にも喜ばれ、さらにやる気が出るという良いループを作り出すきっかけになります。
上司という役割を持つ方には、今後サーバントリーダーシップは必要とされる能力のひとつになります。
サーバントリーダーシップには10の属性があります。
正直長いのであまり理論から実践をしない方は、次の目次にスキップしていただいても問題ありません。
1)傾聴(Listening)
大事な人達の望むことを意図的に聞き出すことに強く関わる。同時に自分の内なる声にも耳を傾け、自分の存在意義をその両面から考えることができる。2)共感(Empathy)
傾聴するためには、相手の立場に立って、何をしてほしいかが共感的にわからなくてはならない。他の人々の気持ちを理解し、共感することができる。3)癒し(Healing)
集団や組織を大変革し統合させる大きな力となるのは、人を癒すことを学習する事だ。欠けているもの、傷ついているところを見つけ、全体性(wholeness)を探し求める。4)気づき(Awareness)
一般的に意識を高めることが大事だが、とくに自分への気づき(self-awareness)がサーバント・リーダーを強化する。自分と自部門を知ること。このことは、倫理観や価値観とも関わる。5)説得(Persuasion)
職位に付随する権限に依拠することなく、また、服従を強要することなく、他人の人々を説得できる。6)概念化(Conceptualization)
大きな夢を見る(dream great dreams)能力を育てたいと願う。日常の業務上の目標を超えて、自分の志向をストレッチして広げる。制度に対するビジョナリーな概念をもたらす。7)先見力、予見力(Foresight)
概念化の力と関わるが、今の状況がもたらす帰結をあらかじめ見ることができなくても、それを見定めようとする。それが見えたときに、はっきりと気づく。過去の教訓、現在の現実、将来のための決定のありそうな帰結を理解できる。8)執事役(Stewardship)
エンパワーメントの著作でも有名なコンサルタントのピーター・ブロック(Peter Block)の著書の書名で知られているが、執事役とは、大切な物を任せても信頼できると思われるような人を指す。より大きな社会のために、制度を、その人になら信託できること。9)人々の成長に関わる(Commitment to the Growth of people)
人々には、働き手としての目に見える貢献を超えて、その存在をそのものに内在的価値があると信じる。自分の制度の中のひとりひとりの、そしてみんなの成長に深くコミットできる。10)コミュニティづくり(Building community)
(出典:サーバントリーダーシップ ロバート・K・グリーンリーフ (著), 金井 壽宏 (監修), ラリー・C・スピアーズ (編集), 金井壽宏 (監修), 金井 真弓 (翻訳))
歴史のなかで、地域のコミュニティから大規模な制度に活動母体が移ったのは最近のことだが、同じ制度の中で仕事をする(奉仕する)人たちの間に、コミュニティを創り出す。
非常に細かく書いてありますが、このような行動がサーバントリーダーシップには必要ということです。正直完璧超人かな?というのが私の感想です。
そんなことを思った私でも、近しいマネジメントスタイルを実現できているので、お読みのみなさまにもきっと実現していただけると思います。
なぜメンバーから意見があがってこないのか
サーバントリーダーシップを実現するには、ボトムアップでメンバーからの意見や主体的行動が必要になってきます。そもそも主体的に仕事をするってなんでしょうか。ボトムアップってなんでしょうか。
上司サイドのイメージだとメンバーから積極的な意見があがってきて、建設的議論が行われ、上司の強いかかわりや指示がなくてもある程度業務が進んでいく状態でしょうか。
実は私の部署も以前は、意見を挙げる人が非常に少ない部署でした。原因はいくつかあったのですが
- そもそも、人前でアウトプットする機会を与えてこなかった
- 先に私が答え(と自身が思っていること)を言ってしまっていた
- 施策に関する丁寧な説明や目的・意図の落とし込みを怠っていた
- 私自身も「会社が必要なこと」より「(自分の)上司のやりたいこと」を優先してしまっていた
書いていて、ちょっと恥ずかしいですね。笑
サーベイを導入しているお客様からは、よく『部下は何の意見もいわない』と聞くことがあります。多くの場合、上記のような状態になっていることが多いです。
人前で手を挙げて発言することを得意とする人は、あまり多くない印象です。得意でない人が多いのに、いきなり『やりなさい』は無理があります。
私の場合は、まず小さな単位(3〜4人のチームとか)の場で、あえて発表という形で人に説明する機会をつくるということから始めました。時にはフリートークで最近あったことをスピーチするということもしました。
最初のころは、話し方が分からなかったり、噛んでしまったり、言葉に詰まったりと、聞いていて聞きやすい発表が少なかったのですが、繰り返すうちにどんどん発表の精度があがってきました。しゃべり方、資料の作り方、ポイントのまとめ方。全てが変わってきました。
また聞く側のスタンスにも変化がありました。
自分も発表することが増えたため、発表する側の気持ちがわかるようになったのです。すると聞く姿勢や表情、リアクションが変わりました。
誰にもリアクションされない辛さは発表者が一番わかってますよね。
これが良い循環になり、発言しやすい環境になります。ここから、少しずつ発表の場をグループ→部→事業部と広げていき、とうとう経営の前でも説明やプレゼンができるようになっていくのです。
アウトプットをする場があると、自分の意見を日々考えることにもつながってきます。
上司にあたる人は、このようなアウトプットが増える環境の構築と場をつくる立ち回りをする必要があります。
メンバーを信じていますか?
さて、アウトプットの場を準備する話をしましたが、みなさまはメンバーをどのくらい信頼できてますか?そして、信頼を言葉にして伝えていますか?
サーバントリーダーシップがうまくいっている組織では、マネジメントに対する信頼度が高いと言われていますが、実は、これは自分自身が相手を信頼できているので信頼されるのです。まったく信頼していない相手から自分が信頼されることは、ほぼないと言ってもいいでしょう。
とはいえ、『過去信じられなくなるような仕事をしてきたじゃないか』と思う局面もあるかもしれません。
信頼とは過去の経験を鑑みず、未来の相手に対して行うものなので、過去どのような経験があっても信頼はできるものだ、と言われています。私はこの考え方がちょっと腹落ちしなかったので、相手の信頼できる部分を切り出して明確に期待と一緒に伝えることにしました。
信じられなくなるエピソードがあったとしても、信頼できるエピソードや部分は少なからず存在しているはずです。その部分を切り出して相手に信頼値としてお伝えします。
そうすることで相手はもらった信頼にはこたえたいと思うのです。少しずつ切り出す信頼を増やしていくことで、できる仕事やお願いできることも増えていくことができ、成長や自立にもつながっていくことになるのです。
風通しの良い会社ってどんな会社?
サーバントリーダーシップを持っている管理職のいる会社はいわゆる「風通しの良い会社」と表現されることが多いのではないでしょうか。
弊社に面接に来られる方からも「風通しのいい会社かどうかが転職軸です」という言葉を聞くくらい、働く人にとってその言葉は重要だと思われます。
では、その「風通しが良い」ってそもそもどのようなことを表現しているのでしょうか。
- 社長に直接ものがいいやすい環境である
- 上司に意見しやすい環境である
- 会社の最新情報が常に入ってくる
- 横のつながりが強固
このあたりが出てくるのではないでしょうか。
私自身も「確かにな」と思う部分は多々あるのですが、現実問題はどうでしょうか。
- 社長に直接ものがいいやすい環境である
→ 物理的に社長と会わないところにいることもある - 上司に意見しやすい環境である
→ その意見は建設的なのか?不満なのか? - 会社の最新情報が常に入ってくる
→ 全ての情報を得て理解しきれるのか - 横のつながりが強固
→どことつながっていると満足できるのか
と実践しようとするとハードルがそこそこあるような気がしますし、経営者の観点からすると、必ずしもそれがいいとは言い切れない部分もあるのではないでしょうか。
ではどうするのか。
“自身が欲しい情報を能動的にとりに行けるようなメンバー育成を実践する”
ということだと私は思っています。
全員が、相手が言ってきてくれるのを待っているスタンスだと、与えられる情報は相手にゆだねられることになりますので、満足いく情報をメンバーが手に入れられる可能性は低くなります。
ひとりひとりの「風通しの良い」の定義が異なる以上、メンバー毎に上司がカスタマイズするか、自身でほしい情報を取りにいくかのいずれかしか答えはありません。
すると、現実的なのは、情報を取りに行けるメンバーを管理職が育成していくかないのです。
決して、簡単なことではないのですが、その意識を管理職として持っていくことが風通しの良い会社にするひとつのポイントだと考えます。
自身のコミュニケーションの変え方
ここまで、サーバントリーダーシップについて書いてきましたが、
『頭ではわかっているけど、なかなかコミュニケーション変えられないんだよ!』というみなさまの声が聞こえてきそうです。私自身もそう簡単ではありません。
ただ、私がお伝えしたいことは
『人は認知(意識)することで、感情やコミュニケーションをコントロールできる』ということです。
ストレスマネジメントでもそうですが、人は認知することで自身の感情をコントロールしやすくなります。管理職がマネジメントするうえでも同じです。
傾聴し、受容し、共感し、導けという難題を与えられた我々中間管理職は、そういった自分であればメンバーに自主性が培われ、部署の成長が見込まれると信じましょう。
そして、日々のコミュニケーションを強く意識していきましょう。
少しずつではあると思いますが、メンバーから見える自分自身の姿に変化があるはずです。人材会社でバリバリ上下関係のみで働いてきた私も、意識ひとつで大きくコミュニケーションを変えることができました。自分のマネジメントを変えてみたい方はぜひ試してみてください。
もし、ご相談がある方がいらっしゃいましたらぜひご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。