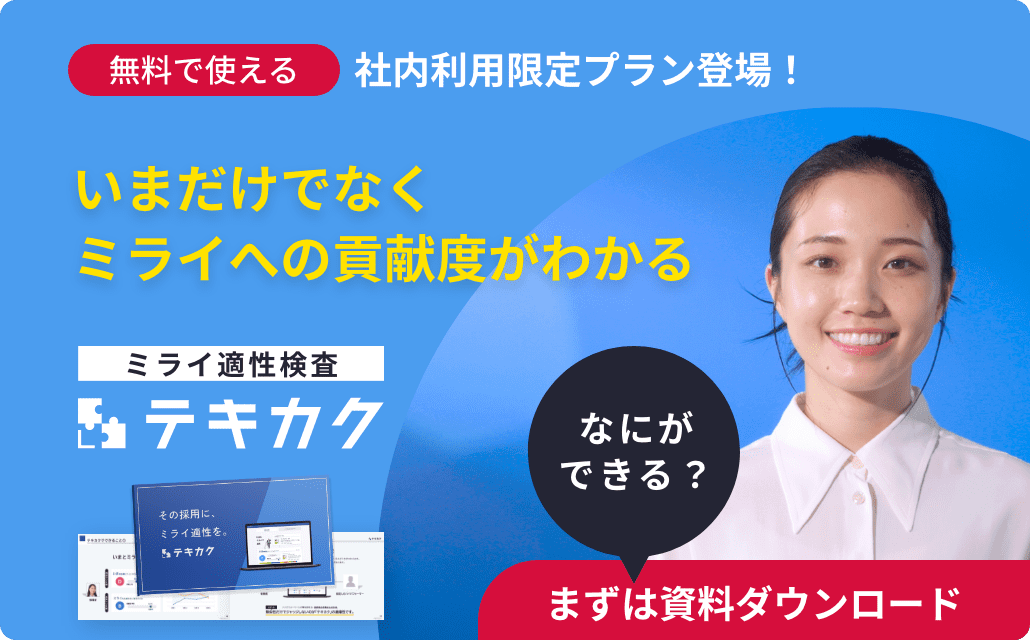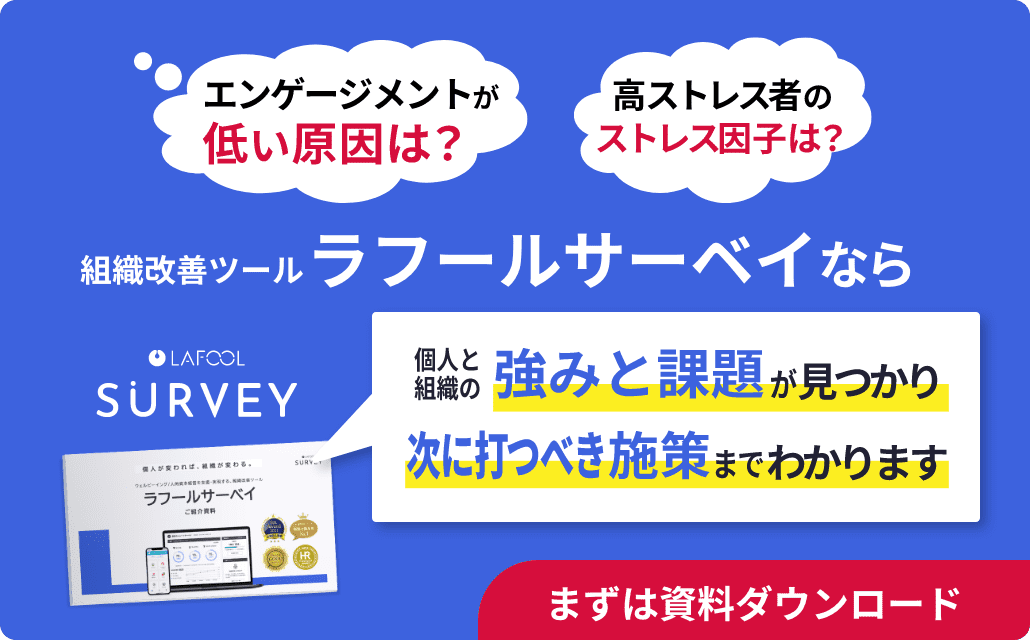近年、ハラスメントは単なる個人の問題ではなく、企業の存続をも脅かす深刻なリスクとして認識されています。 職場におけるハラスメントは、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、生産性の低下、優秀な人材の流出、そして企業のブランドイメージ失墜に直結します。 しかし、「ハラスメント対策」と一言で言っても、何から手をつければ良いのか、効果的な対策とは具体的に何を指すのか、頭を悩ませている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。 本記事では企業の人事担当者の皆様が、複雑化するハラスメント問題に確実に対応できるよう、その定義や基礎知識、具体的な予防策、さらには効果的なツールの活用方法までを網羅的に解説します。
ハラスメントとは?
ハラスメント(Harassment)とは、「嫌がらせ」や「いじめ」といった迷惑行為全般を指す言葉で、職場においては個人の尊厳を傷つけ、精神的・身体的苦痛を与える行為を指します。
これは単なる人間関係のトラブルにとどまらず、従業員のモチベーションや生産性の低下、離職、さらには企業の法的責任や社会的信用の失墜にもつながりかねません。
職場では、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)をはじめ、SOGIハラスメントやアウティングなど、さまざまな形態が問題視されています。
企業はこうしたリスクを正しく理解し、未然に防止するための対策が求められます。
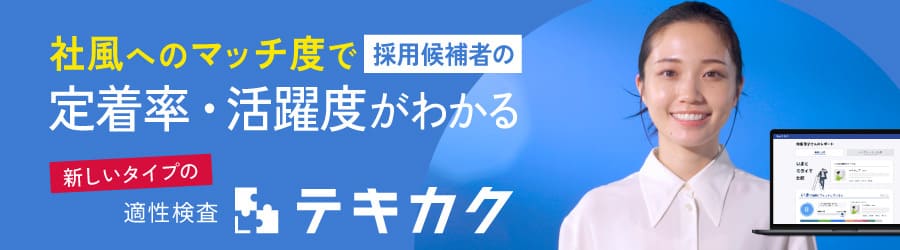
職場で起こりうるハラスメントの種類
ハラスメント行為には内容によってさまざまな種類があります。いずれのハラスメント行為も相手を傷つけ、結果として職場の環境を悪くするため、早急の対策・防止策が必要です。
パワーハラスメント(パワハラ)
職場での自身の地位を利用し、業務上必要な程度を超えた行為で相手に精神的、または身体的な苦痛を与えることです。パワハラは上司から部下へ行われるイメージがありますが、同僚間、または部下から上司・先輩から後輩へ行われることもあります。パワハラには適切な範囲の指示や指導は含まれませんが、人によって同じ行為でも感じ方が違うため、線引きが難しいです。
<例>
- 長時間にわたり、必要以上の指導や叱責を行う
- 大勢の目の前で、あえて人目を引くように怒鳴る・注意する
- 意図的に仕事を与えない、または能力に応じた仕事を与えない
- 相手の昇進を妨害する
セクシャルハラスメント(セクハラ)
セクハラは相手が性的に不快と思う発言や行動で、相手の尊厳を傷つけることです。男性から女性だけでなく、女性から男性へ、または同性間でも起こりえます。
<例>
- 必要以上に体に触れる
- 相手が拒否しているにも関わらず、食事などに誘う
- 相手のプライベートな交際関係について質問する
- 自身の立場を利用して性的関係を強要する(昇給・昇進をもちかけるなど)
- 性別のフィルターがかかった発言をする
「男が育休なんてとる必要はない」
「女に責任のある仕事は任せられない」
モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメント(モラハラ)は、言葉や態度によって人の心を傷つけ、精神的な苦痛を与える行為です。
多くの場合直接的な暴力は伴わず、陰湿で巧妙な形で繰り返されるため、被害者がその行為をハラスメントだと認識しにくく、周囲からも見過ごされやすい傾向にあります。
加害者自身に「ハラスメントをしている」という自覚がないケースも少なくなく、行為が表面化しにくいことから、早期発見や対策が極めて難しいハラスメントです。
そのため、被害者の精神的な苦痛が想像以上に深刻化し、心身の不調や休職・退職につながるケースも少なくありません。
<例>
- 無視や仲間外れにするなど、人間関係から意図的に排除する
- 人格を否定する、侮辱する、または傷つけるような発言を繰り返す
- 達成が困難な業務を不当に押し付けたり、過度な責任を負わせたりして自信を喪失させる
- 精神的に追い詰めるような言動や状況を意図的に作り出す
マタニティハラスメント/パタニティハラスメント(マタハラ/パタハラ)
妊娠、出産、育児に関する不適切な言動や、社内の制度を利用した嫌がらせによって、被害者に精神的苦痛、肉体的苦痛を与えることをマタハラやパタハラと言います。近年聞かれるようになった「パタハラ」は、男性に対するハラスメントです。
マタハラ・パタハラとしてよく知られている問題は減給、降格、不適切な配置転換、解雇などです。しかしこれらは男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の違反に値します。
<例>
- 妊娠している女性社員に対して、正社員からパートになるように強要する
- 出産や育児を控えている人を、評価や昇進の対象から外す
- 休日に病院へ行くことを強要する(平日の休暇を認めない)
- 育休や産休を取ることを否定する、または快く思わないような発言をする
- 妊娠や育児のために時短業務をしている人に対し、「楽してる」などの不適切な発言をする
- 「子どもは女に任せて男は仕事しろ」などの不適切な言葉をかける(パタハラ)
ケアハラスメント(ケアハラ)
介護を行っている人に対する、業務上の不適切な行為がケアハラです。マタハラやパタハラと同様に、減給、降格、不適切な配置転換、解雇などは、育児・介護休業法違反にあたります。
<例>
- 介護を理由に降格、または評価・昇進の対象から除外する
- 介護のために時短勤務をしている人に「早く帰れてよい」などの発言をする
- 介護をしている人に「他の人に任せればいい」など、相手の状況を考慮しない言葉をかける
- 介護のための休暇取得を拒否する、または快く思わない態度をとる
エイジハラスメント(エイハラ)
エイハラとは年齢で差別することです。相手の状態や能力を考えずに年齢だけで物事を判断したり、年齢に関した失礼な言動をとったりすることを指します。
<例>
- 能力ではなく、単純に年齢で仕事の振り方を決める
- 年齢でスキルの有無を判断する
- 年齢に関して相手を傷つける言葉を言う
「もう若くないのだから」
「若い人はこれだから…」 - 年齢・世代で相手のことをとらえる言動をする
「ゆとり世代には任せられない」 - 年齢に絡めて、結婚など私生活に関する発言をする
「まだ結婚していないのか」
リストラハラスメント(リスハラ)
リスハラはリストラ対象者に嫌がらせを行い、被害者を自主退職させる行為です。企業が出す解雇通知には、裁判などのリスクがあります。リスハラは、そのリスク回避として行われることがあります。
リスハラの具体例には以下のようなものがあります。
- 窓際部署を作り、対象者を配置転換する
- 相手に「無能だ」などの自信を無くさせるような発言をし、精神的に追い詰める
- 相手の能力に見合わないような仕事ばかりを押し付ける
アルコールハラスメント(アルハラ)
アルコールに関係する不適切な行為全般は、アルハラに該当します。
<例>
- 飲み会などで、相手に飲酒を強要する
- 早飲みや一気飲みなどの強要
- 飲み会などで、お酌を強要する(女性社員が相手の場合はセクハラにとられることもあります)
- お酒に酔ったうえでの暴言、暴力
スメルハラスメント(スメハラ)
においによって相手に不快な思いをさせたり、身体的不調に追い込んだりすることをスメハラと言います。スメハラは加害者が自分のにおいに気づいていない場合が多く、注意喚起に気を遣う問題です。
スメハラは以下のようなにおいが原因になることがあります。
- 体臭
- 口臭
- たばこ
- 香水
- 柔軟剤
SOGIハラスメント・アウティング
SOGIハラスメント(ソジハラ)とは、性的指向(Sexual Orientation)や性自認(Gender Identity)に関する差別や嫌がらせを指します。
性別に基づく固定観念の押し付けや嘲笑、不当な人事異動や嫌がらせ、無視なども含まれます。これは個人の尊厳を深く傷つけ、LGBTQ+の方々が安心して働ける環境を奪う深刻なハラスメントです。
中でも、SOGIハラスメントの一種として問題視されているのが「アウティング」です。
これは本人の同意なく、性的指向や性自認などのセンシティブな情報を他人に漏らす行為を指します。
たとえ悪意がなかったとしても、プライバシーの侵害にあたり、精神的ダメージや人間関係の破綻、場合によっては命に関わる深刻な問題にもつながります。
過去にはアウティングが原因で自死に至った事例もあり、企業が責任を問われたケースもあります。
<例>
- 「男のくせに化粧なんかするな」「もっと女らしく振る舞うべき」
- 同性を好きだと打ち明けた社員に対して嘲笑や差別をする
- 性的指向や性自認を理由に、昇進の機会を与えない・不当な部署異動を命じる
- 本人の了承なく「◯◯さんってゲイなんだって」と他の社員に言いふらす
リモートハラスメント(リモハラ)
リモートハラスメント(リモハラ)とは、テレワークや在宅勤務中に発生するハラスメントの総称です。
対面でのやり取りが少ないリモート環境では、相手への配慮を欠いた言動や、デジタルツールの悪用によって精神的・身体的な負担を与えるケースが見られます。
リモハラは、加害者・被害者ともに自覚しにくい点が特徴です。プライベートと仕事の境界が曖昧になりやすいため、被害者が孤立しやすく、声を上げにくい状況にも陥りがちです。
<例>
- 常にオンライン状況を監視したり、勤務時間外に連絡を繰り返す
- 背景の映り込みや家族構成についてしつこく聞く
- 業務に関係ない私的メッセージやセクハラ的スタンプを送信する
- 会議情報や必要資料を意図的に共有しない
- 特定メンバーだけ会議に呼ばない、チャットグループから外す
2022年4月からパワハラ対策が義務化
2022年4月より、すべての企業にパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
これは改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)によるもので、従来は大企業のみが対象でしたが、改正により中小企業も含めた全事業主に対策が義務づけられた形です。
企業は「相談窓口の設置」「被害者・加害者への適切な対応」「再発防止措置」「就業規則等への明記」など具体的な防止措置を講じることが求められます。
対策を怠れば、行政指導や企業の社会的信頼の低下、ひいては法的責任を問われるリスクもあります。
パワハラを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場づくりのために、企業は法令を正しく理解し、主体的な対策を講じることが不可欠です。
参考
労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
社内のハラスメント問題を防ぐための対策

すでに起こったハラスメントへの対処も重要ですが、今後ハラスメントを起こさないことも大切です。以下ではハラスメント防止の具体策をご紹介します。
トップダウンでハラスメントを許さない姿勢を周知
ハラスメント対策を効果的に行うには、まず経営層などのトップが企業方針として周知することが大切です。企業としてハラスメントを許さない方針が明確になると、相手を尊重し、気遣いながら働く環境が生まれます。また問題が発生した際に相談しやすくなるため、課題の早期発見・対処が可能です。
企業への周知には、以下のような方法があります。
- 朝会など社員が集まる場所で通知
- 新年など、節目のあいさつの場で通知
- 研修時に通知
ハラスメント研修などの啓発活動
ハラスメントの防止は、一部の人だけでは達成できません。そのため研修によって、個々に問題を意識してもらうことも大切です。ハラスメントとは何か、どのような行為がハラスメントにあたるのかといった価値観の共有や、実際にハラスメントが起きた場合の具体的な解決方法を共有することで、ハラスメントに対する組織全体の意識が高まります。
ハラスメントのシグナルを見逃さない組織文化の醸成
従業員がお互いの変化に気づき、ハラスメントを見逃さない環境を作るには、管理職クラスの人が率先して行動することが重要です。管理職が関わると、企業が一体となって取り組む問題と認識されるため、互いの変化に気づける環境が育まれます。
ハラスメントを見逃さない環境を作るには、以下のような方法があります。
- 企業幹部による、ハラスメントの説明会の実施
- 従業員の顔色、服装、体調のチェックの実施
コミュニケーションが活発に行われる風通しの良い組織作り
ハラスメントを相談しやすい環境づくりには、コミュニケーションの活性化が重要です。コミュニケーションをとらないと、相手のことを思い込みで判断しやすくなり、それによって生じた誤解がハラスメントにつながります。また問題を相談しにくい環境ではハラスメントが表面化しないため、知らないうちに職場環境が悪化していまいます。
コミュニケーションをとりやすい環境作りには、以下が効果的です。
- 相談窓口の設置
- 各部署やチームに相談役やフォロー役を設置
ハラスメント対策を効果的・効率的に行う「ラフールサーベイ」
現在の組織の状態をチェックし、具体的な課題を見つけて対策するのは非常に難しく、時間もかかります。そのような場合は組織のストレス診断ツールを使うのがおすすめです。
ラフールサーベイは、仕事に対する「心理的安全性」と「エンゲージメント(ポジティブで充実した心理状態)」を可視化する組織診断ツールです。
ラフールネス指数による可視化
ラフールネス指数とは、チェック結果を表すラフールサーベイ独自の数値です。「個人」と「職場」、「総合」の3つの観点から、組織の健康度合いを示します。
直感的に課題がわかる分析結果
調査結果の「見える化」により、問題や具体策が把握しやすいのがラフールサーベイの特徴です。調査結果は点数や、点数を基にしたABC判定、グラフなど、直感的にわかる形で報告されます。また部署別、男女別、時間軸などで多角的にデータ分析も行えます。
課題解決の一助となる自動対策リコメンド
ラフールサーベイでは、対策が必要な危険要素も具体的に報告されます。危険要素に関しては、推奨される対処法である「対策リコメンド」も表示されるため、すばやく問題の解決にあたることが可能です。
154項目の質問項目で多角的に調査
年に2回のスタンダードサーベイでは、厚生労働省が推奨する57項目に加え、ラフールサーベイ独自の84項目のチェックが行われます。
ラフールサーベイではストレス指数はもちろん、受験者の性格や給与、福利厚生といった職場での衛生要因、受験者の仕事に対するポジティブさを表すエンゲージメントなど、従来のストレスチェックでは把握できなかった要因もチェックできます。
19の質問項目に絞り、組織の状態を定点チェック
毎月行うショートサーベイは、チェック項目を19に厳選しています。日頃の精神・体の状態、エンゲージメントを短時間でチェックできるため、従業員の負担を最低限に抑えつつ、日常的に職場の環境を確認できます。
適切な対策案を分析レポート化
ラフールサーベイでは、ラフールのメンタルヘルスチェックのノウハウと、専門家の研究内容から検査結果がフィードバックされます。そのため専門的な視点によって、素早く・的確に課題の特定が行えます。また問題を解決するための具体的な対処もアドバイスされるため、効率的にハラスメント対策を行うことが可能です。

ハラスメントが起きてしまった場合の事後措置は?
万が一、職場でハラスメントが発生してしまった場合、企業には迅速かつ適切な事後措置を講じる義務があります。そのステップは以下の通りです。
1. 事実関係の迅速かつ正確な確認
相談を受けた内容について、関係者からのヒアリング、証拠の収集などを通じて、客観的な事実認定に努めます。
この際、相談者や関係者のプライバシー保護には最大限配慮し、秘密が漏洩しないよう徹底することが不可欠です。
2. 被害者への適切な配慮
被害者の意向を確認した上で、加害者との接触を避けるための配置転換や勤務場所の変更、精神的なケアの提供などが考えられます。
3. 加害者に対する厳正な措置
事実関係に基づいて、就業規則に則った懲戒処分はもちろんのこと、加害者への指導や研修なども検討し、適正に行います。
4. 再発防止に向けた取り組み
当該事案の原因を分析し、組織全体への注意喚起、ハラスメント研修の強化、社内ルールの見直しなど、再発を許さない職場環境の整備に継続的に取り組みます。
これらの措置を通じて、企業は従業員の安全を守り、組織の信頼を回復する責任があります。
参考
まとめ
ハラスメント対策は、企業にとって単なるコンプライアンス遵守にとどまらず、極めて重要な経営課題です。
2022年4月からは中小企業にもパワハラ対策が義務化され、すべての企業が法的責任を負うこととなりました。これは法的義務という側面だけでなく、従業員が安心して能力を発揮できる健全な職場を整え、企業の持続的な成長を支えるための「戦略的投資」と捉えるべきです。
ハラスメント対策は、未然に防ぐ予防と、発生時に迅速かつ適切に対応する事後措置の両面から、継続的に取り組むことが不可欠です。
ハラスメントのない職場は、従業員のエンゲージメントと生産性を高め、結果として企業のブランド価値と競争力の向上にもつながります。
「何から取り組めばいいのかよく分からない…」といった場合は、ラフールサーベイなどの診断ツールを活用することもおすすめです。