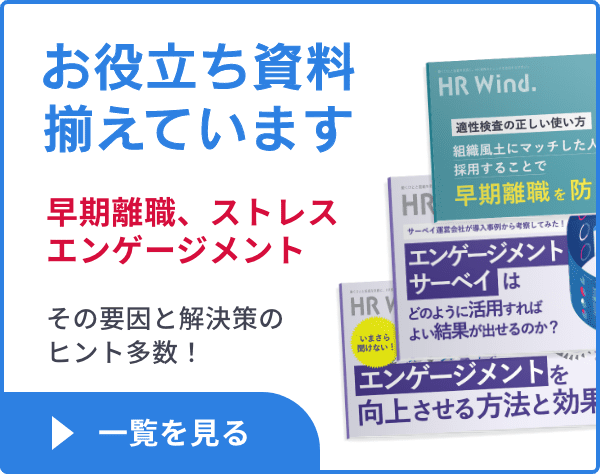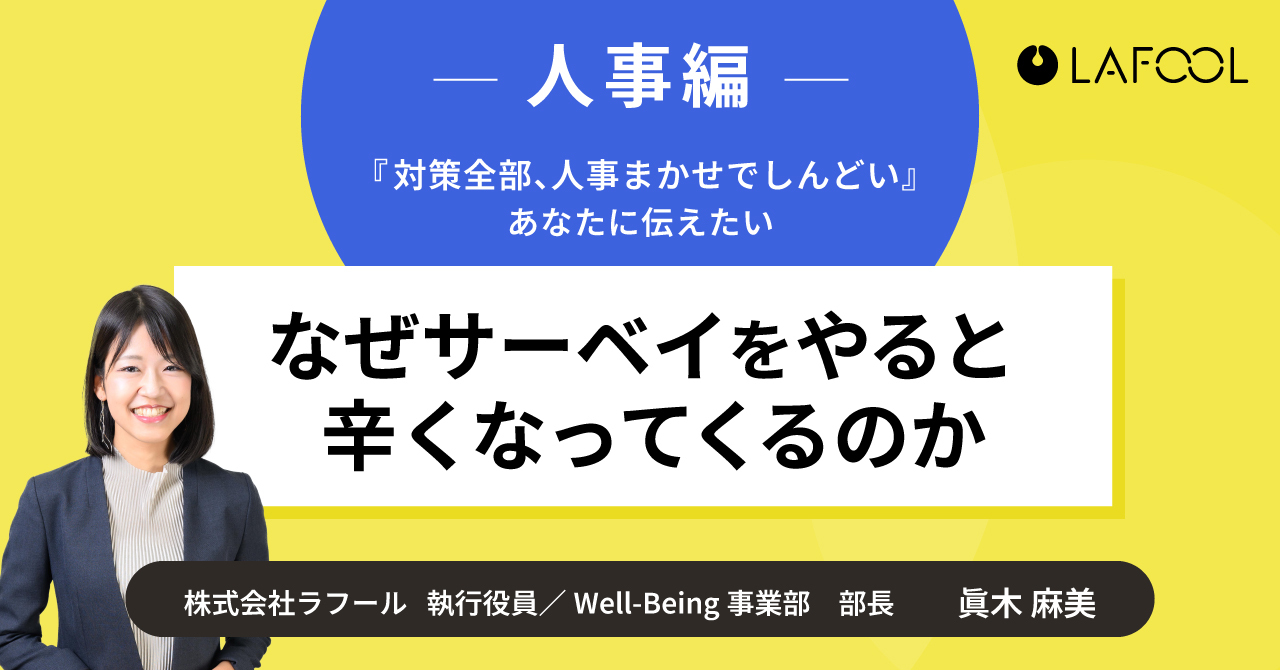個々のメンバーのスキルは高いはずなのに、なぜかチームとしての成果が出ない。新しいプロジェクトに対して、現場から「どうせ無理だ」という諦めの空気が漂っている——。 このような組織の課題は、個人の能力不足ではなく「集合的効力感(Collective Efficacy)」の欠如にあるかもしれません。
集合的効力感とは、簡単に言えば「私たちならできる」というチーム全体の自信のことです。近年、組織パフォーマンスを最大化する鍵として心理的安全性と並び注目されています。
本記事では、集合的効力感の正しい意味や自己効力感との違い、そして人事・管理職が現場で実践できる「集合的効力感を高める4つの方法」を解説します。根拠のない自信が招くリスクについても触れていますので、強い組織づくりの参考にしてください。
集合的効力感とは?
集合的効力感(Collective Efficacy)とは、「自分たちのチームなら、与えられた目標を達成できる」というチーム全体の共有された自信や信念を指します。
この概念は、心理学者のアルバート・バンデューラ(Albert Bandura)博士によって提唱されました。
彼は、個人が自分の能力を信じる「自己効力感(セルフ・エフィカシー)」を提唱した人物でもありますが、現代の組織運営においては、個人の力だけでなく「集団としての自信」が成果を左右するとして、この集合的効力感という概念が重要視されています。
アルバート・バンデューラによる定義
バンデューラ博士の定義の核心は、単なる自信ではなく集団が特定の成果を出すために必要な一連の行動をいかに組織し、実行できるかという信念にあります。
この定義には、組織運営において重要な「3つの学術的要素」が含まれており、この効力感が強い集団ほどより高い目標に挑戦し、たとえ失敗に直面しても「自分たちのやり方を変えれば克服できる」と粘り強く努力を継続する傾向が証明されています。
「共有された」信念(Shared Belief)
一部のリーダーだけが「できる」と思っている状態ではなく、メンバー全員が「自分たちにはその能力がある」と共通認識を持っている状態を指します。
この「共有」こそがチームの一体感を生む源泉となります。
「組織化」と「実行」への自信
単に「結果が出ることを願う」楽観主義とは異なります。目標達成に向けた具体的なプロセス(計画の策定、適切な役割分担、困難時の軌道修正)を、自分たちが主体的にコントロールできるという確信に基づいています。
個人の能力の総和を超える「相乗効果」
集合的効力感は、単に「能力の高い個人を集める」だけでは生まれません。メンバー同士の連携や補完関係に対する信頼が含まれるため、個人のスキルの単純な合計以上の成果(シナジー)を生み出すための「組織のOS」として機能します。
自己効力感との違い
集合的効力感を理解する近道は、個人レベルの「自己効力感」と比較することです。
- 自己効力感(I can) 「私はこれをやり遂げられる」という自分への自信です。個人の学習意欲やモチベーションを左右し、困難に直面した際の粘り強さに直結します。
- 集合的効力感(We can) 「私たちなら達成できる」というチーム全体への信頼です。これは個人のやる気にとどまらず、メンバー間の協力体制や、組織としての土壇場の踏ん張り、そして最終的な組織成果に大きな影響を及ぼします。
たとえ優秀な「個」が集まっていても、チームとして「どうせ無理だ」という空気が蔓延していれば、組織のポテンシャルは半分も発揮されません。
構成する3つの要素
集合的効力感は、単なる精神論ではなく、以下の3つの要素が組み合わさって形作られます。
- 集合的能力感 チームが持つスキル、知識、リソースに対する信頼。「このメンバーと設備なら解決できる」という実感です。
- 使命感 共通の目的意識と方向性。何のためにこの壁を乗り越えるのかという「意義」が、チームの結束を強めます。
- レジリエンス 困難や環境変化に対応する柔軟な強さ。予期せぬトラブルが起きても「今の私たちなら軌道修正できる」と前向きに捉える力です。
企業が集合的効力感を高める3つのメリット
集合的効力感が高い組織は、単に雰囲気が良いだけでなく、ビジネスにおいて極めて実利的な強みを発揮します。
なぜ多くの企業がこの概念の醸成に力を入れるのか、具体的な3つのメリットを見ていきましょう。
組織パフォーマンスと生産性の向上
多くの学術的なメタ分析(複数の研究結果を統合した分析)において、集合的効力感とチームパフォーマンスには強い正の相関があることが証明されています。
「できる」と確信しているチームは、自然と高い目標を設定し、それを達成するための努力を惜しみません。結果として、生産性の向上に大きく寄与します。
従業員エンゲージメントの向上と離職防止
厚生労働省の人手不足の下での「働き方」をめぐる課題についてでも、働きがい(ワーク・エンゲージメント)を高める重要性が指摘されています。
「このチームなら成果を出せる」「自分はこのチームに貢献できている」という感覚は、組織への深い帰属意識(コミットメント)を育みます。
これが心理的な報酬となり、優秀な人材の離職防止につながるのです。
困難な状況への耐性(レジリエンス)
ビジネスにトラブルは付き物ですが、集合的効力感が高いチームは失敗を「能力不足」のせいにしません。
「手法が合わなかっただけだ、次はどう挽回しようか」と建設的に捉え直す力が強いため、試行錯誤の中からイノベーションが生まれやすくなります。
【実践】集合的効力感を高める4つの方法

集合的効力感は、単なる精神論で高まるものではありません。
提唱者のバンデューラ博士は、効力感を高めるための「4つの情報源」を提唱しています。これらを現代のチーム運営に落とし込んだ、具体的な実践アクションを紹介します。
1. 成功体験の共有
最も強力なのは「自分たちはできた」という実体験です。 大きな目標をいきなり追うのではなく、「スモールウィン(小さな勝利)」を積み重ねましょう。
プロジェクトを細分化し、小さな達成を朝会やチャットツールで「今日のGood News」として全員で祝う習慣が、チームの自信を底上げします。
2. 代理体験とモデリング
「あそこにできたなら、自分たちにもできるはずだ」という感覚を醸成します。
社内の他部署の成功事例を共有する勉強会を開いたり、競合他社の成功プロセスを分析して「自社ならこう再現できる」とシミュレーションしたりすることが有効です。
3. 社会的説得とポジティブなフィードバック
リーダーや周囲からの「君たちならできる」という根拠のある励ましが、チームの自信を補強します。
単に精神論で励ますのではなく、過去の実績や現在の強みを具体的に言語化して伝えてください。メンバー同士で称賛し合う「ピアボーナス」などの仕組みも、社会的説得を加速させます。
4. 情動的喚起と心理的安全性
過度なプレッシャーや不安は「できないかもしれない」というネガティブな感情を呼び起こします。
失敗を責めずに学習の機会とする「心理的安全性」を確保し、リラックスして実力を発揮できる環境を整えましょう。
ストレスチェックの集団分析を活用し、高ストレスな職場環境を改善することも、間接的に効力感を高めます。
集合的効力感を高める第一歩は「組織の可視化」から
集合的効力感を醸成するには、リーダーの主観や勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて組織の状態を把握することが重要です。
もしチームの底流に「言っても無駄だ」という諦めや、過度なストレスによる疲弊が隠れている場合、表面的な鼓舞だけでは逆効果になりかねません。
まずは組織の「健康状態」を正しく測定し、効力感を阻害している要因を取り除くことから始めましょう。
組織改善ツール「ラフールサーベイ」の活用
こうした組織の状態を可視化する有効な手段の一つが、ラフールサーベイです。
従来のストレスチェックだけでは見えなかった「エンゲージメント」や「心理的安全性」を多角的に分析できます。
データによってチームの弱点や伸びしろが明確になれば、集合的効力感を高めるための「的確な打ち手」を打つことが可能になります。
注意点:過信が招く「集団浅慮」のリスク
集合的効力感は組織の強力な武器になりますが、一方で「盲目的な自信」が牙をむくこともあります。
健全な組織運営を継続するために、人事や管理職が知っておくべき2つの落とし穴とその対策についてお伝えします。
根拠のない自信とリスクテイク
集合的効力感は重要ですが、実力を伴わない「過信」には注意が必要です。
市場の変化を無視して「自分たちならなんとかなる」と楽観視しすぎると、無謀なリスクテイクを招く恐れがあります。
常に客観的なデータに基づき、冷静な意思決定プロセスを維持するバランス感覚が求められます。
リンゲルマン効果(社会的手抜き)の防止
「チーム全体が優秀だから、自分一人がサボっても大丈夫だろう」という心理(社会的手抜き)が働くリスクもあります。
これを防ぐには、チーム全体の目標を掲げつつも、個々のメンバーの役割と責任を明確にすることが不可欠です。
まとめ:主語を「私」から「私たち」へ
集合的効力感は、一朝一夕に築けるものではありません。
しかし、リーダーが率先して「私(I)」ではなく「私たち(We)」を主語にして語り、小さな成功を積み重ねていくことで、組織の底力は確実に高まります。
「私たちならできる」という確信が、困難を突破する最強の武器になるはずです。