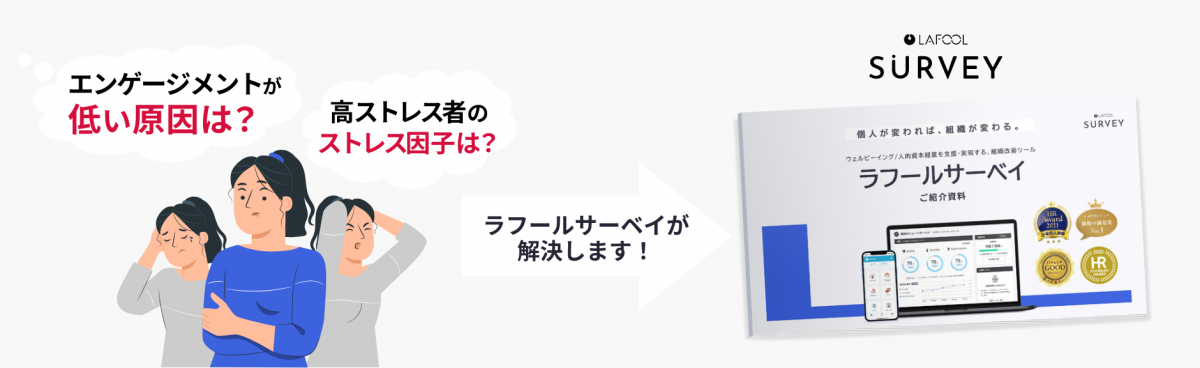近年、話題に上がる「キャリアブレイク」。長期間働き続ける中で、一時的に仕事を離れ、スキルアップやリフレッシュの時間を確保することは、今後のキャリアに大きな影響を与える可能性があります。
しかし、キャリアブレイクを選択するには、経済的不安や転職時の懸念などの懸念点もあるでしょう。また、企業側もキャリアブレイク経験者を採用する際にどのような点を評価すべきかを考える必要があります。本記事では、キャリアブレイクのメリット・デメリットから、成功させるためのポイント、企業と個人の双方にとっての影響について詳しく解説します。
キャリアブレイクとは
キャリアブレイクとは、一時的に仕事を離れ、リフレッシュやスキルアップのために時間を費やすことを指します。具体的には、語学留学や資格取得、ボランティア活動、育児や介護、休養など、目的に応じてさまざまな形態が存在します。
キャリアブランク・サバティカル休暇との違い
キャリアブレイクと似た概念として「キャリアブランク」「サバティカル休暇」がありますが、それぞれ異なる特徴を持っています。
キャリアブランクとは、企業に在籍していない空白期間を指します。「キャリアブレイク」が離職を積極的に選択する際に用いられるのに対して、「キャリアブランク」は「転職時の懸念点」などと結びつけられ、時にネガティブな意味としても用いられています。
一方でサバティカル休暇とは、長期間働いた勤務者に対して与えられる1カ月~1年程度の休暇を意味します。男女共同参画白書 令和5年版によれば、サバティカル休暇は欧米で活用されており、日本では「長期休暇」「研修休暇」と呼ばれることもあります。ハーバード大学で始まった、研究のための有給休暇を起源とするもので、日本の企業における例はまだ少ないですが、各大学では教職員の研究休暇として導入・利用されています。
参考:内閣府 男女共同参画局「男女共同参画白書 令和5年版」
2つの言葉と比較して考えてみると、個人が自分の意志で数か月以上仕事を離れる場合、現状日本で取られることの多い選択肢がキャリアブレイクであると言えます。
キャリアブレイクが注目される背景
キャリアブレイクが注目される背景には、今わたしたちがキャリアの見直しが必要な時代に生きていることや、ワークライフバランスが重視されていることが挙げられます。
日本の平均寿命が伸びるにつれ、自身の生活費や医療費をまかなうため、個人が以前より長く働く必要が生じてきました。労働期間が長ければ、学びなおしが必要な局面が増えてきます。
また現代は、「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる時代です。VUCAとはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った造語で、目まぐるしく変化するために予測が難しい状況を意味します。将来の予測が難しい時代において、長期的なキャリア計画はより困難です。そのため、個人は度々自らのスキルを見直し、学び直しの期間を設けることが必要となるのです。
加えて近年は、働き方改革や価値観の多様化により、従業員の健康や幸福度を重視する傾向が強まっています。キャリアブレイクは、仕事とプライベートのバランスを見直す機会としても注目されています。
キャリアブレイクのメリット
取得者側
キャリアの見直しができる
仕事に追われる日々では、自分のキャリアについてじっくり考える時間を確保するのは難しいものです。キャリアブレイクを取ることで、 「自分は本当にこの仕事を続けたいのか?」「どんな働き方を望んでいるのか?」 を再考する機会を得られます。
特に、 スキルチェンジを考えている人や新たな分野に挑戦したい人にとっては、キャリアブレイク期間を活用して学びなおしをしたり、新たな経験に触れたりすることが、有意義な転機となるでしょう。
心身のリフレッシュ
キャリアブレイクは、 心身のリフレッシュのためにも効果的 です。仕事のストレスが蓄積すると、 燃え尽き症候群(バーンアウト) に陥るリスクが高まります。一時的に仕事から離れることで、 精神的なリセットができる だけでなく、健康面でもプラスの影響を与えることができます。
また、適切な休息を取ることで仕事へのモチベーションが回復し、復帰後のパフォーマンス向上にもつながることが期待されます。
企業側
多様な人材の確保
キャリアブレイクを経験した人材は、通常のキャリアパスを歩んできた人とは 異なる視点や価値観を持っています。特に変化のめまぐるしい現代では、さまざまな背景をもつ人材が社内に存在することによって、企業が柔軟に変化に対応できることもあるでしょう。企業にとって、キャリアブレイク経験者を採用すること は、組織の競争力を高めることにもつながります。
既存社員への刺激
キャリアブレイクを経験した人が職場に戻ってくると、既存社員にとって 新たな視点を得る機会になります。固定観念を打破するきっかけになったり、新しいスキルや知見を持った社員が戻ることで、新しい価値観、組織全体のスキル向上にも寄与したりといった影響が期待できるでしょう。
柔軟な働き方を推進できる
企業がキャリアブレイク制度を導入し、社員の長期休暇を認めることで、 「柔軟な働き方を推進する企業」 というイメージを構築できます。これは、企業のブランド価値を向上させるだけでなく、 優秀な人材の採用にもプラスに働きます。
特に、ミレニアル世代やZ世代は、 働き方の自由度やワークライフバランスを重視する傾向 にあります。キャリアブレイク制度を持つ企業は、 こうした若い世代にとって魅力的な職場と映るため、採用活動にも良い影響を与えるでしょう。
キャリアブレイクのデメリット
取得者側
経済的不安が大きい
キャリアブレイク中は、基本的に給与が支給されないため、生活費をどう賄うかが大きな課題になります。また、キャリアブレイク後に転職活動が長引いた場合、貯金を切り崩すことになってしまうでしょう。
特に、住宅ローンや家族の生活費などを負担している場合、キャリアブレイクの期間中も安心して暮らせるように計画的な資金準備を行っておくことが大切です。
転職活動で不利になる可能性がある
キャリアブレイクの認知度は年々向上しているものの、企業によっては 「キャリアの空白期間」としてネガティブに評価されることがあります。
採用担当者に「仕事への意欲が低いのでは?」と誤解されるリスクを防ぐには、「なぜキャリアブレイクを取ったのか」「その期間に何をして過ごしていたのか」「今後のキャリアにどう活かすのか」を明確に説明できる準備をしておくことが大切です。また、キャリアブレイクを選択する際には、復帰後のキャリアも見据えた計画を行うことも意識すると良いでしょう。
企業側
導入にはコストがかかる
企業が自社社員にキャリアブレイクを認める場合、一定期間の休職者が出るため、 業務の負担が一部の社員に集中するリスク があります。また休職者の穴を埋めるために追加採用が必要になれば、人件費が増加するでしょう。
さらに、キャリアブレイク中の 給与や福利厚生の取り扱い によっては、企業側の負担が増えることも考えられます。多くの企業では、キャリアブレイクを 無給の長期休暇として扱いますが、福利厚生の継続や、復職後の賃金体系の調整が必要になるケースもあります。
また、求職によってキャリアブレイクを取得した社員が 復帰を望まずに転職するケースも考えられます。人材流出によって育成コストが無駄になってしまうことに加え、新たに採用を行う必要が生じれば、 採用コストや教育コストが追加で発生することになります。
人材の流出リスクがある
キャリアブレイクを取得した従業員が、休暇中に新しいスキルを習得したり、価値観を見直したりすることで、転職を決意する可能性があります。
特に、 学び直し型のキャリアブレイクを取った社員は、新たな業界へのキャリアチェンジを考えることもあるため、復職せずに別の企業へ転職してしまうケースもあるでしょう。
企業側としては、 優秀な人材を失うリスクを最小限にするために、キャリアブレイク取得者とキャリアプランを共有しておくなどの工夫が必要です。
キャリアブレイクを成功させるためのポイント
キャリアブレイクを 成功させるためには、取得前から復帰後までを見据えた準備と戦略が重要 です。ここでは、キャリアブレイクを最大限に活かすためのポイントについて詳しく解説します。
目的を明確にする
キャリアブレイクは 長期間にわたる人生の一大イベント です。そのため、 「なぜキャリアブレイクを取るのか?」 という目的を明確にすることが非常に重要です。
目的が曖昧なままキャリアブレイクを取得すると、 休暇の終わりが近づいたときに焦りを感じたり、復帰後のキャリアに対して明確な方向性が見えなくなったりする 可能性があります。
まずは 「何を実現したいのか?」 を明確にし、それに応じた行動計画を立てることが重要です。
キャリアブレイクの代表的な目的と具体例
スキルアップ・学び直し(リスキリング)
- 例:語学習得、プログラミングの学習、MBAの取得
- 目的:専門スキルを強化し、より高いレベルのキャリアに進む
- 成功のコツ:計画的に学習時間を確保し、資格取得やプロジェクト参加など具体的な成果を出す
新しいキャリアパスの模索
- 例:起業準備、異業種への転職準備、クリエイティブ活動(執筆・芸術活動など)
- 目的:キャリアチェンジに向けた知識・経験の蓄積
- 成功のコツ:実際に業界のプロジェクトに参加したり、インターンやボランティア活動を経験する
リフレッシュ・バーンアウト回避
- 例:旅行、趣味の追求、ワークライフバランスの調整
- 目的:心身の健康を回復し、働くモチベーションを取り戻す
- 成功のコツ:だらだら過ごさず、計画的にリフレッシュの時間を確保する
家庭やライフイベントへの対応
- 例:育児・介護、パートナーの転勤への同行
- 目的:家庭の事情に合わせた柔軟なキャリア形成
- 成功のコツ:キャリアブレイク後の復職プランを具体的に考えておく
資金計画を立てる
キャリアブレイクを取得すると 収入が一時的に途絶えるため、事前にしっかりとした資金計画を立てることが不可欠 です。特に、転職活動が長引いた場合や、学び直しのための費用が想定より高くなった場合など、 計画不足によって経済的に困窮するリスク があります。
キャリアブレイクの資金計画の立て方例
1. 必要な生活費を把握する
- 家賃、光熱費、食費、通信費、交通費、保険料などの費用を計算
- 可能な限り 節約できる部分を見直す(サブスクリプションの見直しなど)
2.キャリアブレイクの期間を決める
- 「○ヶ月後には復帰する」 という期限を明確にする
- その期間に必要な資金を逆算し、どれくらいの貯蓄が必要か計算
3.ブレイク期間中の収入源を検討する
- フリーランス・副業での収入確保(ライティング、プログラミング、オンライン講師など)
- 退職金・失業保険の活用(ブレイク後に転職活動を行う場合)
4.突発的な支出に備える
- 病気や事故などの予期せぬ出費に対応できるよう 「緊急資金」 を確保する
企業がキャリアブレイク取得者を採用する際のポイント
キャリアブレイクを取得した人材を採用する際、企業側はどのように評価すべきかを十分検討する必要があります。近年、キャリアブレイクの認知度が高まり、企業も柔軟な働き方を受け入れる傾向にありますが、依然として 「ブランク=ネガティブな要素」と考える企業も少なくありません。
しかし、キャリアブレイクは候補者が積極的に選択した結果の休暇であり、適切な評価を行うことで 企業にとって有益な人材を確保するチャンスになります。ここでは、 キャリアブレイク取得者を採用する際に重視すべきポイントを詳しく解説します。
キャリアブレイクをポジティブに捉えているか
採用時の面接では、候補者がブレイク期間をどのように説明できるかを理解することが重要です。この問いに対して、応募者が明確な目的意識を持ち、前向きに捉えているかどうかを確認することで、その人のキャリア観を知ることができます。
【見るべきポイント】
- キャリアブレイクに際してどのような計画を立てていたのか
- 応募者が自分のキャリアを主体的に考えているか
- キャリアブレイクをポジティブに捉え、 今後のキャリアに活かす意識があるか
キャリアブレイク期間中に何をしていたか
キャリアブレイク中に どのような活動をしていたかを確認することは、採用するうえで必要不可欠なポイントです。新しいスキルの習得、ボランティア活動、リフレッシュなど、候補者によって過ごし方はそれぞれです。
ブレイク期間中の過ごし方自体のみならず、その時の経験をどう捉えているかを尋ねることによって、候補者のキャリアとの向き合い方がより深く理解できるでしょう。
【企業が見るべきポイント】
- どのようなことに時間を使っていたか
- 経験を通じてどういった学びを得たのか
- 期間中の過ごし方は今後のキャリアにどうつながるのか
これからのキャリアを具体的に考えているか
キャリアブレイク取得者が 今後のキャリアについてどれだけ具体的に考えているかという点も、採用時の重要なポイントです。キャリアブレイクを経て「なぜ今この企業に応募しているのか?」を明確に説明できるかどうかが、採用可否の判断基準となります。
【企業が見るべきポイント】
- キャリアブレイクの経験を踏まえ、どのような仕事をしたいのか
- なぜ自社を選んだのか
まとめ
キャリアブレイクは、個人にとって スキルアップやキャリアの見直し、リフレッシュの機会であり、企業にとっても多様な人材を確保し、職場を活性化させるチャンスとなります。一方で、採用時にはブランク期間をどのように説明・評価するかが課題となることもあります。個人と企業の双方がキャリアブレイクの本質を理解し、適切な準備と評価を行うことが成功の鍵となるでしょう。
特に、企業がキャリアブレイク経験者の適性をより正確に判断するためには、適性検査の活用も有効です。適性検査を導入することで、 職務適性やストレス耐性、価値観などを客観的に評価でき、履歴書や面接だけでは見えにくい応募者の強みや企業文化との相性を把握することができます。適性検査「テキカク」では、10~15分の検査で「いまの社員と採用候補者の相性/組織を成長させる革新人材になるか/社内ハイパフォーマーとの類似度合い」をチェックすることができます。
キャリアブレイクは、適切に評価すれば 企業の成長を支える有能な人材の発掘につながります。採用の際は、適性検査を活用しながら、ブレイク経験者のポテンシャルを見極め、長期的に活躍できる環境を整えることが重要です。