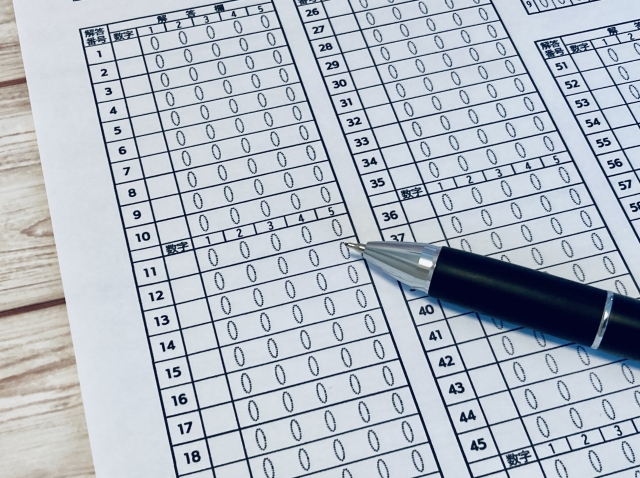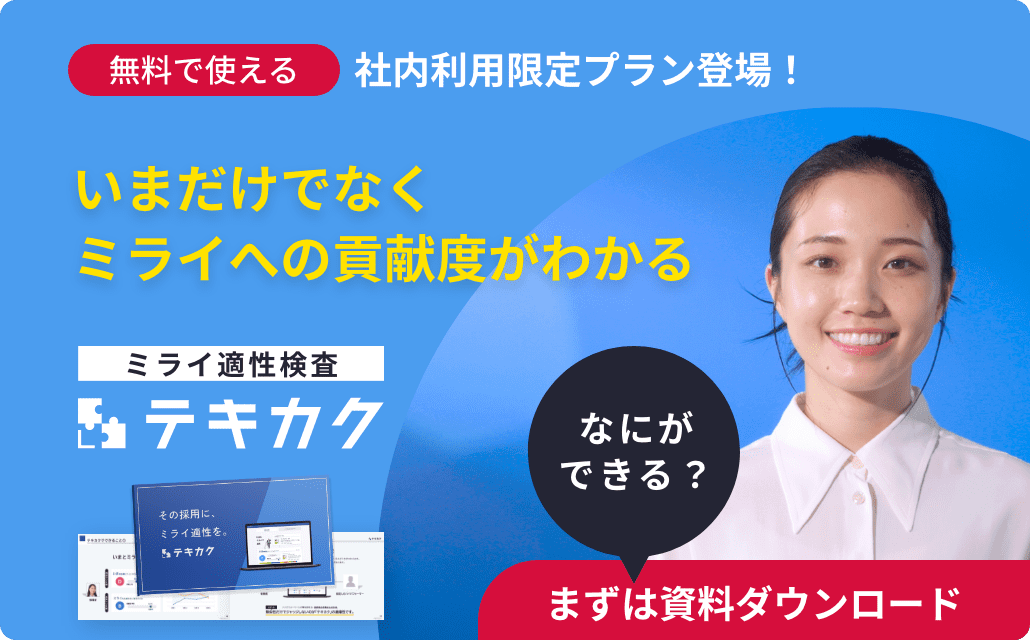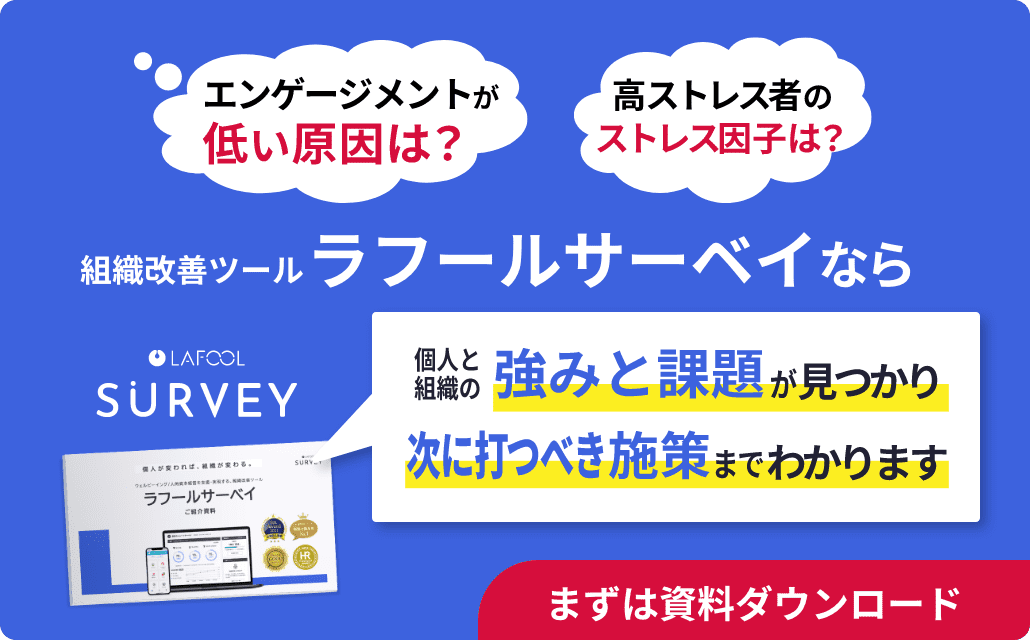近年、採用候補者や自社の社員の資質を客観的にはかる指標として、多くの企業で適性検査が取り入れられています。サービスの種類も増えている中、効果的に適性検査を取り入れるためには、サービスを比較検討したうえで自社に合ったものを選ぶ必要があるでしょう。 そこで今回の記事では、「適性検査とは何か」という基本を踏まえたうえで、その選び方や具体的なサービスの比較紹介を解説しています。企業の採用担当や人事担当の方は是非参考にしてみてください。
適性検査とは?
適性検査とは、採用活動において企業が求めている人材かどうか見極めるためのツールです。
スキルや知識だけではなく、人間性や考え方などを客観的に見極めることができ、採用だけではなく配属先の適性を判断する材料にもなります。
適性検査を取り入れることで採用リスク、内定辞退、早期離職を低減する効果があり、昨今、多くの企業が取り入れています。
適性検査を実施する目的とメリット
自社にマッチした人材かどうか、採用担当者のみの判断で決めるには負担が重く、面接では面接官の主観が入ってしまう恐れもあります。
また、面接だけでは見えてこない応募者の性格や特性などを知ることができるため、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
採用活動以外でも、自社の社員に対して検査を実施することで、実際に活躍している社員の性格や傾向を知ることができるため、それをもとに採用基準を構築することも可能です。
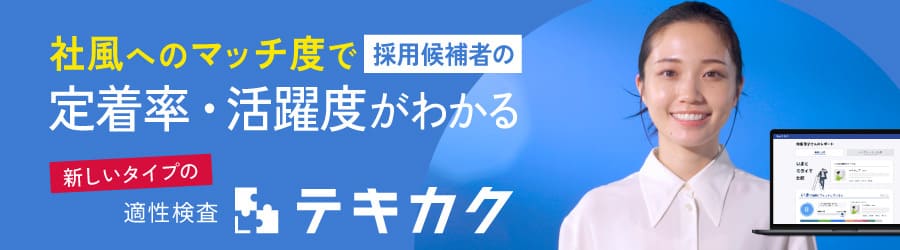
適性検査の種類
適性検査は大きく分けて「能力適性検査」と「性格適性検査」があります。
それぞれの検査でどういったことが分かるのでしょうか?
能力適性検査
- 基礎的な学力
- 一般常識、マナー
- 語彙力、文章読解、論理的思考力
- 計算、推論、数的理解力
- 英語の理解力
- 業務に対する知識、対応力
性格適性検査
- 人間性や考え方、価値観
- 対人スキル、協調性
- コミュニケーション能力
- ストレス耐性
おすすめの適性検査サービス一覧を比較
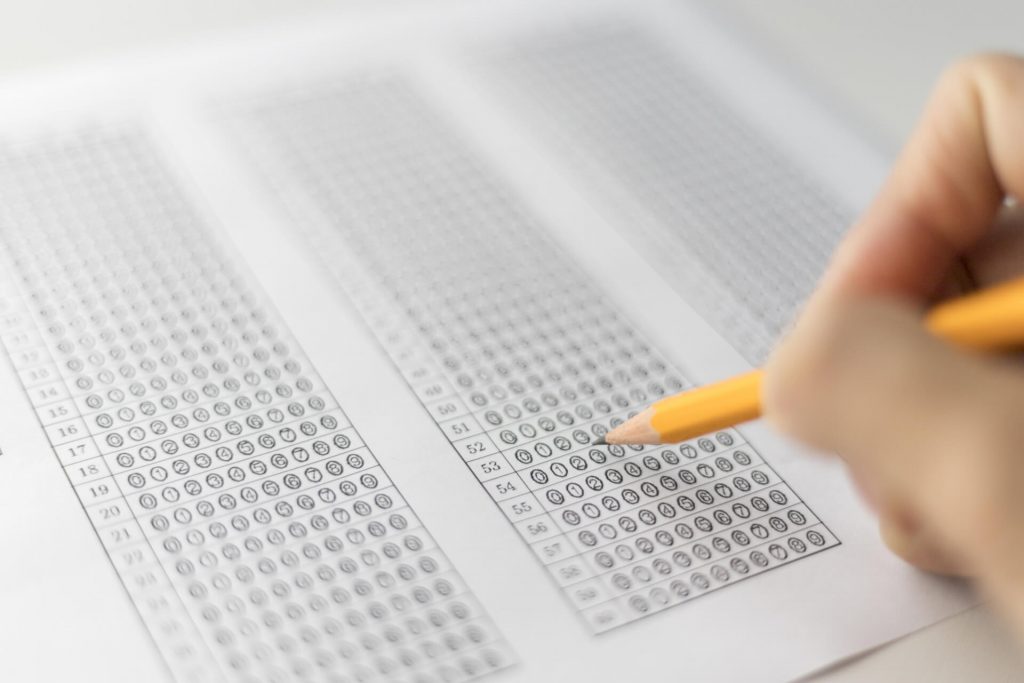
ここでは人気の適性検査サービスをご紹介します。
テキカク
組織形成のために必要な人材タイプを組織改善ツール「ラフールサーベイ」で蓄積したビッグデータからAI解析し、”いま”と”ミライ”の貢献度やマッチ度、既存のハイパフォーマー社員との類似度を比較することが可能。
組織と人材のミスマッチを防ぎ、採用候補者が組織の”いま”と”ミライ”への貢献度がわかる適性検査サービス。
SPI3
適性検査のスタンダードともいえる検査で、応募者の人柄を簡単に確認できるため一人ひとりに合わせたフォローを行える。
面接で確認した方がいいことを「面接支援報告書」にまとめてくれるため、面接官の負担も低減される。
初期選考や面接から内定後のフォローや配属まで、多岐にわたって活用できるのが特長。
https://www.spi.recruit.co.jp/
Talent Analytics
知的能力テストと性格・価値観テストの2種類で構成された精度の高い検査。
学歴や職歴では分からない、能力や価値観を可視化することができる。
所要時間は35分で、初期費用は無料。企業・受験者の双方に負担が少ないのが特長。
https://jinji-test.en-japan.com/
Compass
1,000社を超える企業の人事担当者の“本音”を評価項目に反映したWeb形式の適性診断サービス。
「ストレス耐性」や「対人コミュニケーション」「抑うつ傾向」など入社後のリスク要因を5つの因子、10段階でチェックすることができる。
検査時間は約20分で、英語・中国語での受検にも対応。
tanΘ(タンジェント)
ストラテジスト・ハンター・アナリスト・ファーマー・バランスという5つの思考タイプに分類し、直感的に個人の特性を把握することができる。
一つの設問に複数の因子を結びつけることで、適性検査は約15分で受検することができる。能力検査3科目を加えても60分で受検することができ、スマホ受験にも対応している。
https://www.shinka.com/business/tangent.html
ミキワメ
社員を複数名選定するとシステムが自動で社員分析し、従業員の性格傾向が分かる。
社員分析をもとに作成された採用基準と照らし合わせて、候補者が活躍する可能性を「S~E」の14段階で表示。配属部署との相性や、活躍できる人材かどうかが一目でわかるのが特長。
検査時間は10分で、面接で聞くべき質問も自動生成してくれる。
CUBIC
採用選考から人事異動・育成まで幅広く網羅しており、適性結果を元に現在の組織力をスコア化できるのが特長。
検査時間が短く、検査結果もすぐに分かるため、スピーディに進めたい企業におすすめ。
CUBIC TRIUMPH ver.
心理的特性を表す因子を数値化し、5タイプのストレス耐性値を測定することができる。
応募者が希望する働き方の傾向を知ることができるため、早期離職防止にも効果的。
さまざまな料金体系から採用活動に適したプランを選ぶことが可能で、手厚いフォロー体制と実用性の高さが魅力。
TG-WEB
「新卒採用向け」「キャリア採用向け」「従業員向け」の3つの適性検査があり、活用シーンに合わせて選ぶことができる。
「コンピテンシー」「ストレス対処力」「チーム・コミュニケーション」など、多面的に評価できる豊富な検査が特長。
オンラインAI監視型WEBテスト方式 TG-WEB eyeを開発しており、替え玉受検やカンニングを防止することができる。
https://tg-web.humanage.co.jp/
ミイダス
活躍要因診断を社員に受験してもらうことで、分析結果をもとに採用基準を明確にし、ミイダスのデータベースから採用基準に合致する求職者へダイレクトにアプローチすることができるのが魅力。
無料アプリで応募者とやりとりすることが可能で、社員だけでなく業務委託など必要なとき、必要な人材に業務を依頼することもできる。
「HaKaSe診断」for Recruiting
低コストで応募者の個性やチームとの相性を把握できるWeb適性検査。
「ビッグファイブ理論」や「交流分析」に基づいた独自の質問設計を採用し、パーソナリティを60タイプに分類して、応募者を分かりやすく可視化することができる。
10分以内で受検が完了するため、採用候補者の負担が少なく、候補者自身も結果を閲覧することができるので自己理解に役立てることが可能。
https://www.aspicjapan.org/asu/service/44872
HCi-AS
検査時間はおよそ10分で、8ヶ国語に対応しており、Web受検では24時間365日どこからでも受検可能で、完了後すぐに報告書を確認できる。
設問に対する正解はないため受検者の本質をとらえることができ、具体的に人物像を把握できる記述中心の報告書になっている。
メンタルヘルスチェックにも対応しており、ストレス耐性を詳細に診断できる。
https://hci-inc.co.jp/product_as/
内田クレペリン検査
簡単な一桁の足し算を1分毎に行を変えながら、休憩をはさみ前半と後半で各15分間ずつ合計30分間行う。
「作業負荷」をかけることを前提としているため、Webテストは実施していないが、自宅や遠隔地でも受検可能な「UKリモートパック」は利用可能。
足し算を連続して行う検査なので、外国人の方を採用する際にも利用できる。
60年以上の歴史がある信頼性の高い検査。
https://www.nsgk.co.jp/uk/whatis
アッテル
対策ができない設問設計になっており、より正確に応募者の価値観を可視化できるようになっている。
データとAIで「活躍可能性」を判断し、明確な採用基準を作成することが可能。
取得できるデータは、組織全体の生産性向上、活躍人材の増加にも活用することができる。
課題や企業規模に合わせて3つのプランから選ぶことができる。
SCOA
基礎能力や事務能力といった知的側面から、持って生まれた気質や後天的に形成される性格や意欲といった情意的側面まで多面的に測定・評価できる適性検査。
1985年に開発された長い実績と「人事測定・評価開発研究委員会」による厳しい分析で、信頼性の高いデータが取得できる。
テストセンター方式、Web方式、マークシート方式があり、受検者と採用担当者、双方にとって最適な方式を選択可能。
https://www.noma.co.jp/lp/scoa/
TAP
総合タイプ・性格タイプ・短縮タイプなどさまざまなメニューから選択可能で、英語・事務適性・情報処理・自由に問題を作成できるオリジナルプランもあり、専門知識や業界知識など幅広い測定ができるのが特長。
受検形態はWeb(PC、タブレット、スマートフォン)かマークシートを選択可能。
GPS-Business
ベネッセグループのテスト作成ノウハウをもとに開発されたWeb適性検査。
いま採用で重視されている評価基準「思考力」 を測定する採用ツールで、「課題を発見する力」「解決する力」「価値観の前提やすれ違いを見抜く力」などを詳細に可視化。
音声・動画による出題で候補者の本来の力を測定することができるのが特長。
問題解決力の高い人材を見極めたいと考えている企業におすすめ。
https://www.benesse-i-career.co.jp/gps_business/
ミツカリ
約10分で計測可能な採用・配置・マネジメントに活用できる適性検査で、一人ひとりの人物像や会社・部署の特徴を明らかにし、採用や配属、マネジメントにおける人間関係や業務内容のミスマッチを防止する。
32項目の性格の特徴を7段階で表示し、コミュニケーションにおける言動をソーシャルタイプと呼ばれる4つのタイプで分類する。
性格・価値観に合う業務分類やコミュニケーション提案、個人の詳細把握など人事に
必要な機能が満載。
https://mitsucari.com/services/personality
玉手箱Ⅲ
応募者を「知的能力」と「パーソナリティ」の両面から測定する総合適性診断システム。
診断結果は入社時に見ておくべき「ヴァイタリティ」「チームワーク」などの9特性のフォーマットで判定される。
パーソナリティ診断において、実施時間が短くかつ受験人数制限がないのが特長。
http://www2.shl.ne.jp/product/index.asp?view=recruit
適性検査を選ぶ時の3つのポイント
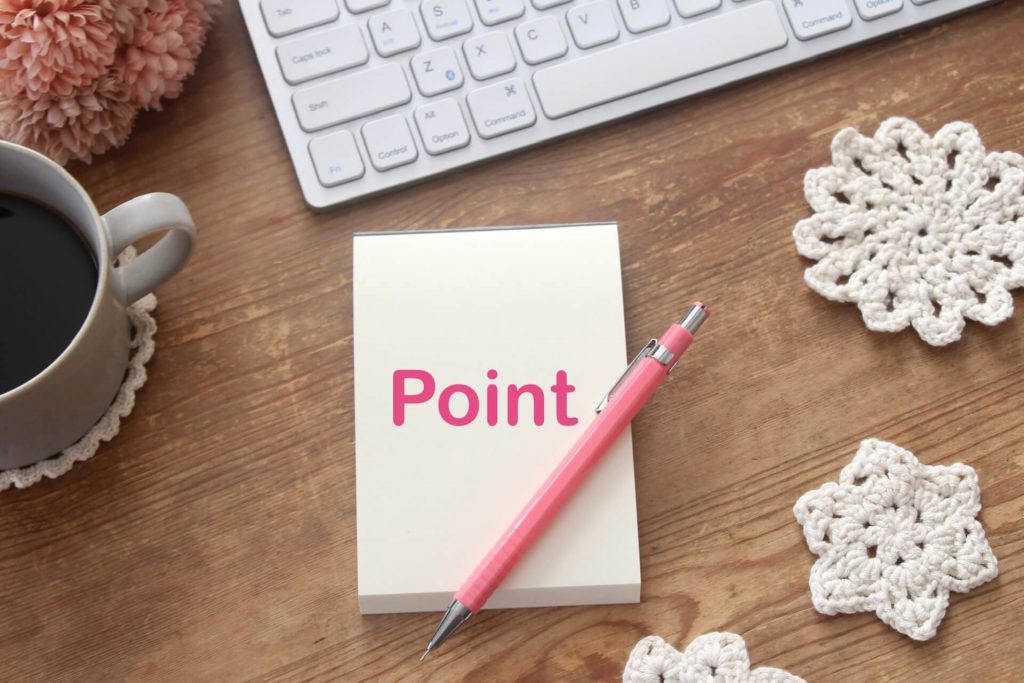
適性検査サービスを選ぶ際は、それぞれの特徴をチェックし、自社に合った適性検査を選びましょう。
ここでは選び方のポイントを3つご紹介します。
自社に適した適性検査か
まず適性検査の結果をどのように活用するのか明確にしましょう。
「応募者のストレス耐性を知りたい」「面接の際に検査結果を活用したい」「相性の良い部署を知りたい」など、見極めたいものや必要なサポートを明確にしてから導入することをおすすめします。
費用は予算内か
適性検査サービスによって費用はまちまちで、初期費用や年間利用料などがかかるものもあります。
導入する前に料金形態を確認し、予算内に収まるのか、受検者数を考えて選びましょう。
テスト形式と所要時間
企業で行うペーパー受検、テストセンターでの集合受検、スマホやPCで行うWeb受検などさまざまな受検方式があります。
自社で実施する場合は場所や日程などの調整が必要ですが、自宅で行ってもらう場合はスマホやPCが必要になります。
所要時間も数分程度で終わるものから数時間かかるものまであり、詳しい結果を知りたい場合は所要時間も長くなります。
企業側、応募者側双方に都合の良いものを選択しましょう。
まとめ
適性検査を導入することで、面接だけでは分かりにくい応募者の人物像が可視化され、採用担当者も客観的に判断することができます。
また採用の可否だけではなく、内定後のサポートをしてくれるタイプもあり、さまざまな活用方法があります。
従業員に受検してもらい、企業が求める人物像を明確化できれば、採用後のミスマッチ防止にも期待できます。
無料トライアルを行っている適性検査サービスも多いので、検討を考えている方はお試ししてみるのはいかがでしょうか。