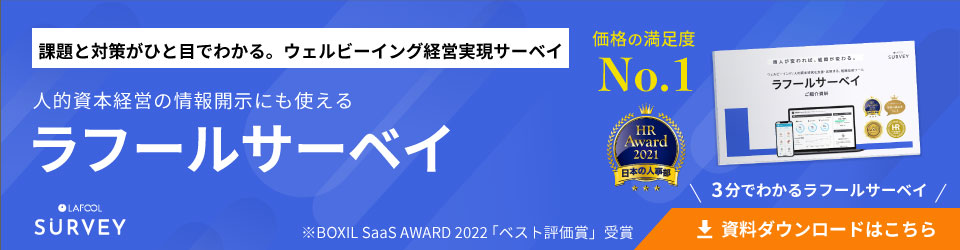採用活動をしている企業にとって、「応募が集まらない」「内定辞退が相次ぐ」といった悩みは深刻です。その背景には、労働市場のバランスが「売り手市場」に傾いている現状があります。では、売り手市場とは具体的にどのような状態を指し、企業はどのように採用を成功させれば良いのでしょうか。ここでは基礎的な整理から最新データをもとにした解説まで、わかりやすくまとめていきます。
そもそも売り手市場ってどんな状態?

「売り手市場」という言葉は、労働市場における需給バランスを表すものです。
ここでいう「売り手」は働き手=求職者のことであり、「買い手」は人材を募集する企業を指します。
つまり売り手市場とは、「働き手の方が有利に就職先を選べる状態」を意味します。求人を出している企業の数に対して、働き手が不足しているため、求職者は複数の企業から内定を得やすく、選択肢を持ちやすい状況になるのです。
一方で企業側からすると、採用競争が激しくなり、「採用したい人材に出会えない」「内定辞退が増える」といった課題が発生します。
有効求人倍率1.0超え=求人が人を奪い合うサイン
売り手市場を測る指標のひとつが「有効求人倍率」です。これは「求職者1人あたりに、何件の求人があるか」を示す数字です。
計算式は以下の通りです。
有効求人倍率 = 有効求人数 ÷ 有効求職者数
この倍率が1.0を超えると、求職者よりも求人数の方が多い=求人が人を奪い合う「売り手市場」になります。
厚生労働省の最新データによると、2025年6月時点での有効求人倍率は 1.22倍 となっています。
つまり、働き手1人に対して1件以上の求人が存在している状況であり、多くの企業が限られた人材を取り合っているのです。
この数字からも、企業が従来通りの採用活動をしていては「選ばれにくい立場」に置かれてしまうことがわかります。
【参考】厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年6月分)について」
なぜ今また売り手市場なのか?4つの背景
「売り手市場」は一時的な景気要因だけでなく、構造的な変化や新しいトレンドが重なって生まれています。ここでは、特に大きな影響を与えている4つの背景を整理してみましょう。
① 若い労働人口が減り続けている(少子高齢化)
まず大前提として、日本の労働供給は長期的に減少傾向にあります。総務省の統計によれば、15〜64歳の労働力人口比率は2024年平均で81.5%となり、前年からわずかに上昇したものの、すでに高水準で推移しており今後の大きな伸びは見込みにくい状況です。
【参考】総務省統計局「労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の概要」
少子高齢化が進むなかで、この比率は将来的に縮小することが予測されており、結果的に「働きたい人の絶対数」が減り続けています。景気が好転しても求人に応じられる人材の母数そのものが限られる、という構造的な制約があるのです。
② DX・生成AIでIT人材の求人が増加
次に注目すべきはIT人材の需要です。DX推進や生成AI活用が急速に広がり、企業の「エンジニア採用ニーズ」は拡大を続けています。
厚生労働省の統計によれば、情報処理・通信技術者(パート除く常用)の有効求人倍率は2025年6月時点で1.67倍 に達しており、全職種平均(1.22倍)を大きく上回っています(厚生労働省「一般職業紹介状況」)。
つまり「特定分野で人材の奪い合いが激化」している構造が、結果的に労働市場全体の“売り手有利”を強めているのです。
【参考】厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年6月分)について」
③ 医療・建設など業界ごとの深刻な人手不足
売り手市場を語るうえで、業界別の動向も無視できません。厚生労働省の「労働経済動向調査」によれば、医療・福祉分野や建設業では「人手不足」と回答する企業の割合が突出しています。
- 医療・福祉分野:高齢化で需要が拡大し続ける一方、担い手の不足が深刻化。
- 建設分野:インフラ更新や災害復旧のニーズが重なり、慢性的な人材不足に直面。
こうした業界では需給バランスの崩れが特に顕著であり、人材市場全体をさらにタイトにしているのです。
【参考】厚生労働省「労働経済動向調査(令和7年5月)の概況」
④ 転職・副業が一般化し、人が流動化
さらに近年は「働き方の多様化」も影響しています。大手企業の副業解禁やリモートワークの普及によって、人材が1社に定着しにくい環境が広がっています。結果として、企業がせっかく採用しても短期間で転職したり、副業によって時間や労力が分散したりするケースが増加。採用の難易度は一層高まっています。
言い換えれば「人材はいるのに定着しない」という、新しいタイプの人材不足が進行している状況です。

売り手市場が企業にもたらす課題
売り手市場は一見「働き手にとってチャンスが広がる明るい状況」に見えますが、企業にとっては必ずしも歓迎できるものではありません。採用が計画通りに進まなかったり、せっかく採用した人材がすぐに辞めてしまったりと、現場の負担や人材コストに直結する課題が次々に表面化します。ここでは、企業が直面しやすい3つの代表的な課題を整理してみましょう。
採用が思うように進まない
売り手市場では、求職者にとって選択肢が広がる一方で、企業は「採用したい人材に出会えない」「応募が集まらない」といった壁に直面します。欠員補充が進まず現場の負担が増えたり、少ない母集団の中で奪い合いになるため採用単価が高騰するのも大きな課題です。結果として「採用コストは増えるのに人はなかなか入らない」という矛盾した状態に陥りがちです。
離職が増えて悪循環に陥る
ようやく採用にこぎつけても、入社後すぐに辞めてしまうケースが増えているのも売り手市場の特徴です。働き手が転職しやすい状況にあるため、条件や職場環境に不満があればすぐに動きやすいのです。離職が増えると残された社員にしわ寄せがいき、疲弊やモチベーション低下を招きます。その結果エンゲージメントが下がり、さらに離職が連鎖するという悪循環が起きてしまいます。
なかなか人が定着しない
「人が辞めやすい」背景には、人間関係の不満、成長機会の不足、待遇のミスマッチ、企業文化との相性など、さまざまな要因があります。特に最近は、表向きは働き続けていても心の中では転職を考えている“隠れ離職予備軍”が増えているのも見逃せません。こうした層の存在は、突然の離職リスクを高めるだけでなく、周囲の雰囲気や生産性にも影響を与えます。企業にとっては「採用する」だけでなく「定着させる」ことがますます重要になっているのです。
企業が今すぐ始める採用・定着対策チェックリスト
売り手市場の中で採用を成功させるためには、「採用する」ことと同じくらい「定着させる」ことが重要になります。そのためには、特別な仕組みをいきなり導入するよりも、基本的な打ち手を着実に実行することが効果的です。以下に、すぐに始められる5つのチェックポイントをまとめました。
自社の魅力をひと言で説明できるようにする
候補者が応募を決めるのは、待遇だけではなく「この会社で働く意味」に共感できるかどうかです。ミッションや強みをひと言で伝えられる準備をしておくと、面接でも印象がぐっと強まります。
候補者を迷わせない、スムーズな選考フローを設計する
売り手市場では「早い企業に取られてしまう」ことも多いもの。選考に時間をかけすぎたり、連絡が遅れたりすると候補者の熱が冷めてしまいます。応募から内定までのプロセスをシンプルに整えることが大切です。
入社前からこまめに連絡を取り、辞退リスクを減らす
内定を出しても、入社前に辞退されてしまうケースは珍しくありません。入社までの期間に、定期的にフォローの連絡を入れることで不安を解消し、「この会社に行こう」という気持ちをつなぎとめられます。
現場任せにせず、育成・伴走の仕組みを仕組み化する
定着には「入社後の体験」が何より大きく影響します。OJTを現場任せにするのではなく、育成計画やメンター制度などを仕組み化し、誰が入っても安心してスタートできる環境をつくることが重要です。
コンディションの変化をサーベイで可視化し、早めに対応する
人は辞める前に必ずサインを出していますが、それを個々の管理職が察知するのは難しいものです。サーベイを活用してコンディションの変化を可視化することで、離職予備軍の早期発見につながります。データで把握し、先手を打って対応する仕組みを持つことが、売り手市場での定着力強化に直結します。
組織の状態を可視化し、改善アクションにつなげる「ラフールサーベイ」
ラフールサーベイは「組織」と「個人」の両面を対象とした従業員サーベイです。定期的な実施により、職場環境やエンゲージメントなどの状態を継続的に可視化することができます。
また、スコアの良し悪しだけでなく、「なぜその状態になっているのか」という背景にある要因まで把握しやすい設計になっており、チームごとの傾向や構造的な課題の把握にも役立ちます。
それぞれの手法には得意な領域があるため、自社の課題や目的に照らして、最適な手法を選択することが重要です。
ラフールサーベイで組織改善がすすむ理由
ラフールサーベイは、サーベイ結果から「なぜそうなったのか」までを可視化し、具体的な改善アクションにつなげることができる組織改善ツールです。ここでは、ラフールサーベイが本質的な組織改善につながる3つの理由をご紹介します。
多面的な設問で組織と個人の状態をまるっと調査
ラフールサーベイは、ストレスチェックや満足度調査だけでは把握しきれない組織と個人の状態を、網羅的に調査できる設計となっています。
組織に関する設問では、エンゲージメントスコアに加えて、仕事へのやりがいや職場の人間関係、eNPS、離職・ハラスメントリスクなど、多面的な項目で組織の状態を分析します。
個人に関する設問では、メンタル・フィジカルスコアやストレス状態に加えて、睡眠に関するデータも把握でき、従業員のコンディションチェックや健康管理に役立ちます。
こうした多角的な設問設計によって、組織課題の全体像を精度高く把握し、適切な改善アクションの出発点を明確にすることが可能になります。
「なぜこの結果になったのか」を構造的に読み解ける
ラフールサーベイは、こうした「なぜこの結果になったのか」という問いをあきらかにするために、スコアの背景にある要因を構造的に読み解くための仕組みを備えています。
たとえば、エンゲージメントの低下が見られた際に、「上司との関係性」「仕事のやりがい」「個人のストレス状態」など、関連する観点を横断的に確認することで、表面的な結果にとどまらず、その背後にある原因に近づくことが可能です。
こうした分析を通じて、サーベイをやりっぱなしにせず、具体的な改善アクションにつなげるための土台として活用できます。
部署・属性別に分解し、構造的な課題を特定できる
設問ごとの結果を関連づけて横断的に確認できるだけでなく、回答結果を部署や職種などの単位で集計・分析することも可能です。
たとえば「上司との関係性に課題がある」というスコアが出たときも、特定の層や部署に集中しているかを確認することで、改善の優先順位やアプローチを検討しやすくなります。
このように、数値の背景にある構造的な要因を分析する視点を取り入れることで、サーベイの結果をそのまま終わらせず、改善施策の優先順位づけや現場との対話のきっかけとして活用できます。

まとめ
売り手市場は「採用が難しい」だけでなく「定着が難しい」ことも大きな課題です。だからこそ、採用広報や選考フローの工夫とあわせて、入社後のフォローや組織改善の仕組みを整えることが欠かせません。
ラフールサーベイは、売り手市場で課題になりやすい「定着」や「職場環境の改善」に役立つ従業員サーベイです。個人と組織の両面を継続的に見える化できるので、「なぜその状態になっているのか」という背景を把握しやすくなります。
採用した人が長く安心して働ける環境づくりを進めたい企業にとって、日常的に活用できる心強い仕組みになるはずです。
▼「ラフールサーベイでできること」「お客様の声」などをまとめた資料はこちらからダウンロードしてご覧いただけます。