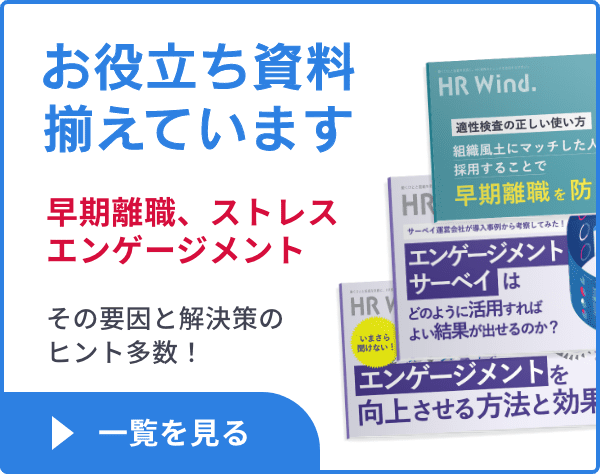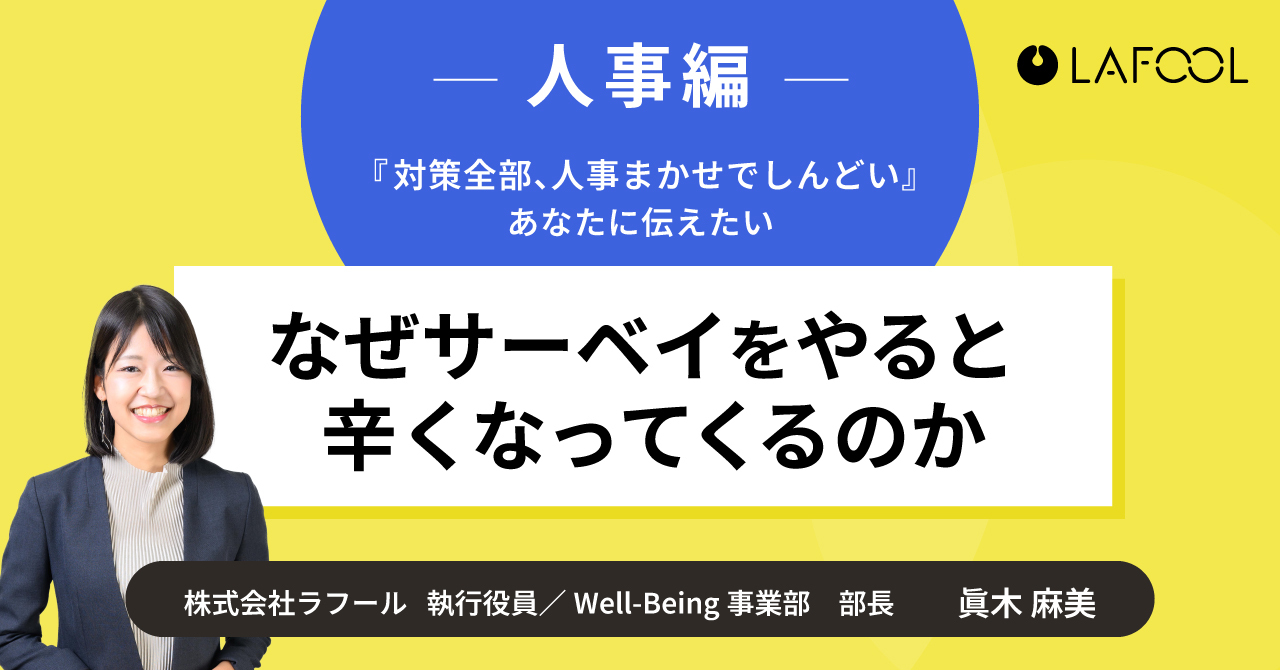試用期間とは?
本採用をする前に、試用期間を設定する企業が多くあります。実際の業務の中で、人柄やスキル、適性等を見極められるため、試用期間を設定することで採用のミスマッチを防げると言えるでしょう。
ただし、試用期間の設定はメリットも多くありますが、デメリットや注意しておくべきポイントもあります。正しく知らないままに設定していると、トラブルを招いてしまうことも。「こんなはずではなかった」と後悔することがないよう、正しく理解する必要があります。試用期間を上手く活用して、企業側と労働者側でWin-Winな関係を築きましょう。
この記事では、試用期間の目的や設定方法、注意点やよくあるトラブルとその対処法について解説します。
試用期間中の雇用契約は?
まず、試用期間中の雇用契約はどのようになっているのでしょうか?結論を言うと、試用期間中でも雇用契約は成立しています。
ただ、試用期間中の雇用契約は「解雇権保留付労働契約」であり、「労働契約締結と同時に雇用効力が確定している」「企業側は労働契約解除権を留保している」という特徴があります。このため、試用期間中に企業側が「業務の遂行が難しい」と判断した場合、双方の合意のもと、労働契約の解除ができます。
なお、雇用契約は口頭で結ぶことも可能です。しかし、試用期間中に労働条件などでトラブルが発生することを避けるため、契約書に条件等を明記して労働契約を結ぶのが一般的です。
試用期間と研修期間の違いは?
試用期間の類似語に、「研修期間」があります。では、試用期間と研修期間の違いはどこにあるのでしょうか?
試用期間はすでに雇用契約を締結している状態で、試用期間後に継続して雇用契約を結ぶかどうかを見極めている期間です。企業が対象者を本採用するかどうかを判断する期間とも言えます。
一方、研修期間は「現場で必要な業務を行うために必要な知識や技術を身に着ける教育期間」のことです。
本来は試用期間と研修期間はそれぞれ意味が違う用語ですが、企業によっては研修期間を試用期間と同じような意味で捉えている場合もあります。
試用期間の目的
採用のミスマッチを防ぐ
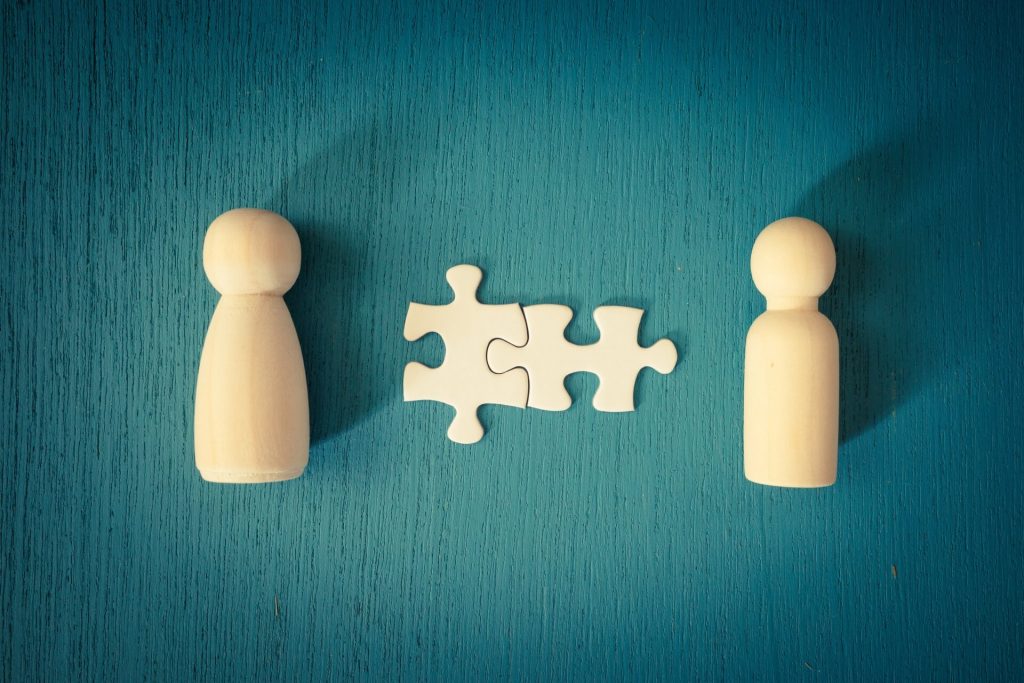
試用期間の目的のひとつは、「採用のミスマッチを防ぐ」ことでしょう。
応募書類や面接を経て採用したものの、実際に働いてもらうと「自社の業務とミスマッチだった」ということがあります。企業側も、応募書類と面接だけで採用者の能力やパーソナリティを把握することは困難です。また、自社の社風や既存社員と合うかなど、実際に働いてみないと分からないことが多いのも事実です。
試用期間を設けることで、企業側・採用者側双方のミスマッチを回避でき、その結果として、採用後の定着にもつながると言えるでしょう。
試用期間を設定するメリットとデメリット
試用期間を設定するメリットとは
企業が試用期間を設定するメリットは、「採用者の勤務態度や実務能力を確認できる」ことです。また、採用者を注意深く観察できるため、配属や担当業務を決めるための判断材料となります。
また、作業スピード、コミュニケーションの取り方、メモを取るなどの仕事への取り組み方、提案の内容など、採用面接中には分からなかった本人の特徴を把握できます。このため、万が一「本採用を行わない」との決定を行ったとしても、事実を元にその理由を伝えられます。
試用期間を設定するデメリットとは
一方、試用期間を設定するデメリットもあります。それは、「試用期間を設けることで他社と天秤にかけられる可能性がある」ということです。
採用者からすると、試用期間中は「試用期間後に本採用されるかどうか」の不安があります。このため、他社の条件と比較して他社への入社を決めてしまうことがあります。特に、中途採用の場合は、試用期間なしで本採用されることを条件として考えている人もいるため、試用期間を設けることで敬遠される可能性もあります。
また試用期間は、採用者側にとっても、会社の雰囲気や環境などが自分と合っているか考える期間となるため、企業側が本採用を希望しても当人に拒否されるケースもあります。
試用期間の設定方法
試用期間は何日間に設定すべき?
試用期間を設定するにあたり、考慮すべき事項の1つ目は「試用期間の期間設定」です。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構の『従業員の採用と退職に関する実態調査』によると、正社員の試用期間の長さで1番多いのが「3か月程度」で、2番目が「6か月程度」です。なお、試用期間の設定の長さについて、法律上の制限はありません。
とはいえ、企業側に解雇権があるため、無尽蔵に長期間の試用期間を設けるのは問題があるとされています。
試用期間中の当人だけでなく、従業員エンゲージメントにも影響するため、試用期間は長くとも1年以内に設定するのが望ましいでしょう。
試用期間は延長できる?
採用者の業務状況により、企業側がもう少し時間をかけて見極めたいと希望する場合、試用期間の延長が行われる場合もあります。
ただし、試用期間の延長の可能性、理由、期間に関して書面による説明と、本人との合意が必要です。
なお、試用期間の延長については客観的合理性が必要です。また、試用期間の繰り返しの延長は認められていないため注意が必要です。
試用期間中の労務管理上の5つの注意点
注意点1:労働契約書の書き方
1つ目の注意点は「労働契約書の書き方」です。
雇用する場合、雇用者に対して雇用条件を記載した「労働条件通知書」を作成し、交付する必要があります。このとき、試用期間を設定するのであれば、期間や処遇などの条件を記載し、本人への説明が必要です。例えば、試用期間が3カ月の場合であれば「試用期間は3カ月」、あるいは「入社後3カ月間」と書きます。試用期間の延長もしくは解雇の場合も同様で、「労働条件通知書」に明記する必要があります。
また、就業規則にも試用期間があることや、試用期間中の身分や労働条件にも明記する必要があります。
注意点2:給料
2つ目の注意点は「給料」です。
試用期間中であっても、給料の支払義務が発生します。ただし、企業によっては、試用期間中は本採用時よりも賃金が低く設定されるケースがあります。
本採用時より低い賃金を提示する場合、法律で定められた最低賃金を下回らなければ問題ありません。
注意点3:各種社会保険への加入
3つ目は「各種社会保険への加入」です。
たとえ試用期間中であっても、一定の要件を満たしているのであれば、労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(健康保険、厚生年金)に加入させる必要があります。
「試用期間だから」といってこれらの保険に加入させない場合、法律違反となるため注意が必要です。
注意点4:時間外労働
4つ目は「時間外労働」についてです。
試用期間中であっても、残業が発生した場合は残業代を支払う必要があります。
労働基準法で「時間外労働の場合は2割5分以上(60時間以上は5割以上)」「休日出勤の場合は3割5分以上」の割増率が定められています。試用期間の従業員であっても、残業が発生した場合は、本採用者と同様に割増賃金を含めて支払う必要があります。
注意点5:有給休暇
5つ目は「有給休暇」です。
労働基準法では付与条件として以下のように定められています。
- 6カ月以上の勤務
- 全労働日の8割以上の出勤
企業によっては「、試用期間中は有給休暇を付与しない」というケースがあります。これは上記要件を満たさなければ付与する必要がないためです。
なお、付与要件で記載した「6カ月以上の勤務」には試用期間も含める必要があります。このため、期間を算出するには労働契約を締結した日から起算する必要があります。
試用期間に関するよくあるトラブルと対処法
試用期間中の賞与は支払う?
試用期間がボーナス査定の期間に含まれるかどうかを定めた法律はありません。このため、試用期間をボーナス査定の期間に含めるかどうかは、企業の判断となります。また、試用期間とボーナスの支給時期を重ねるかどうかについても、企業の判断となります。
ただし、場当たり的な対応を取っていては、試用期間中の採用者とのトラブルになるだけです。このため、試用期間中のボーナスの支給有無については就業規則等に明確に記載する必要があります。
試用期間中の解雇はできる?
試用期間中の解雇については、労働基準法で厳しい制限が設けられています。このため、「試用期間中であれば簡単に解雇できる」と認識している企業もあるようですが、これは誤りです。
しかし、試用期間中の場合は「解約権留保付労働契約」に該当するため、以下のように正当な理由があれば解雇は可能です。
- 業務遂行能力がなく、指導しても改善が見られない
- 遅刻や欠勤を繰り返すなど勤務態度が悪く、指導しても改善が見られない
- 重大な経歴詐称があった
また、社会通念上「解雇されても仕方がない」と認められる場合も解雇が可能です。
試用期間中の解雇予告とは?
労働基準法第20条1項には「少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない」ことが書かれています。このとき30日の日数のカウントは歴日でカウントする必要があります。また、解雇する日を「〇〇年〇〇月〇〇日」という形で日付を特定して、予告しなければなりません。
試用期間中の解雇に関する手続きは?
試用期間中に解雇する場合、「14日以内の解雇」か「14日を超えての解雇」かによって手続きが変わります。
「14日以内の解雇」の場合、企業側は解雇予告や解雇予告手当などの義務を果たす必要はなく、労働基準法第20条1項に基づいて即日解雇が可能です。とはいえ、先にも述べたように企業側の都合に応じて、簡単に解雇できるわけではありません。解雇するには正当な理由が必要です。
「14日を超えての解雇」の場合、他の従業員と同様に解雇予告制度が適用されます。そのため、先にも述べたように、30日以内に解雇予告が必要です。なお、30日前に解雇予告なしに解雇する場合、解雇までの日数分の賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
本採用拒否とは?
試用期間の契約は、「解約権留保付労働契約」です。このため、本採用を留保した状態での雇用契約となり、企業側は試用期間終了後の本採用拒否の判断を行う権利があります。
とはいえ、試用期間後に本採用拒否(本採用を行わない)の場合は、解雇に相当します。試用期間中の解雇と同様に、「社会通念上解雇に相当する」などの正当な理由がないままに企業の都合で解雇することはできません。
トラブルを回避するためにも、就業規則を整備し、本採用拒否に関する規則をあらかじめ設けておくとよいでしょう。
まとめ
この記事では、試用期間の目的や設定方法、注意点やよくあるトラブルとその対処法について解説しました。
試用期間とは、採用者の勤務態度や適正などを判断し、本採用するかどうかを企業側が判断するための期間です。「採用のミスマッチを防ぐ」などのメリットがある一方で、「他社への入社を決められてしまう」などのデメリットもあります。
また、試用期間を設定するにあたっては「期間」「労働契約書の書き方」「給料」「有給付与」「解雇」などの考慮事項が必要です。
採用者とのトラブルを招かないためにも、この記事に記載した注意事項を考慮しながら試用期間に関する規則を整備し、就業規則に明記しましょう。