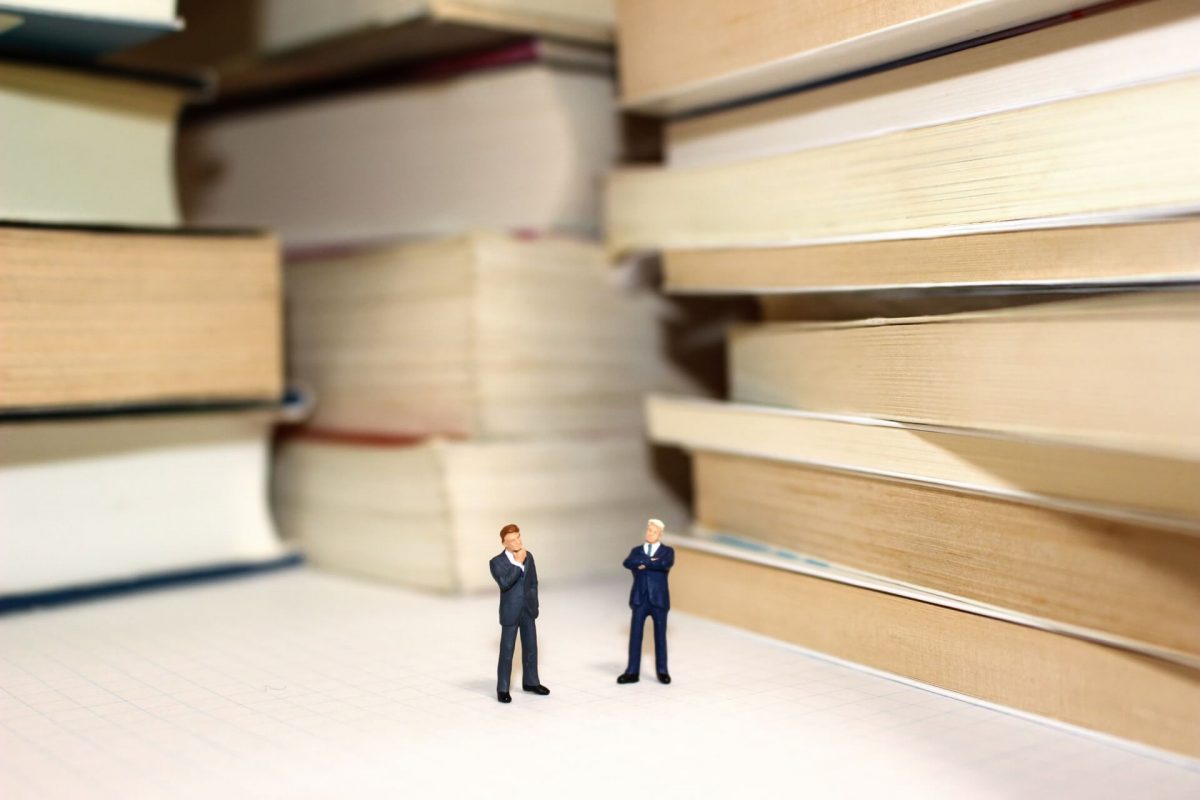急速な技術革新や多様な働き方の広がりにより、現代の企業はこれまで以上に柔軟かつ戦略的な運営が求められています。その中で重要な役割を果たすのが「組織マネジメント」です。単なる業務管理にとどまらず、人材の強みを引き出し、チームの力を最大化するための実践知として注目されています。本記事では、組織マネジメントの基本から実践ポイントまでを詳しく解説します。
組織マネジメントとは
組織マネジメントとは、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を効果的に活用し、企業の目標やビジョンを実現するための戦略的な管理手法を指します。単なる業務管理にとどまらず、組織全体のパフォーマンスを最大化し、継続的に新しい価値を生み出すことを目的としています。
具体的には、人材の採用や育成・評価、資源の調達と活用、予算策定や執行、情報の共有や分析など、幅広い分野を包括的に統括することを意味します。組織マネジメントは企業活動の土台であり、経営戦略の一環として欠かせない役割を担っています。
組織とマネジメントの関係
企業は、一人の力では成し遂げられない目標に挑むために「組織」という形をつくります。組織は構造化されることで効率的に機能し、変化の激しい環境にも柔軟かつ迅速に対応できるのが特徴です。
その組織を円滑に機能させる要となるのが管理職であり、彼らは組織マネジメントの実践者です。管理職は「上位方針をもとに計画を立てる」「標準化された手順を徹底する」「PDCAサイクルを回す」といった役割を担い、組織全体をつなぐ“連結ピン”として機能します。
一方で、管理が過度になると弊害も生まれます。経営学者ゲイリー・ハメルは「人間本来の創造力や自主性が、過剰なルールや標準化によって失われてきた」と指摘しています。つまり、マネジメントは効率性だけでなく、創造性をいかに活かすかという視点も求められているのです。
なぜ現代において組織マネジメントが重要なのか
現代社会は、技術革新やグローバル化、消費者ニーズの多様化により、変化のスピードがかつてないほど加速しています。市場環境が不透明で先行きが読みづらい今、企業が生き残り、持続的に成長していくためには、組織全体の潜在能力を引き出す組織マネジメントが不可欠です。
効果的な組織マネジメントは、変化に柔軟に対応できる組織体制をつくり、社員の力を最大限に活用することで競争優位性を確立します。まさに組織マネジメントは、企業が未来に向けて成長し続けるための羅針盤であり、経営戦略の成功を左右するカギと言えるでしょう。
組織マネジメントの役割と課題解決への効果
組織マネジメントは、単に業務を管理するだけでなく、人材の定着、生産性の向上、多様な働き方への対応といった現代企業が抱える課題を解決するための強力な手段です。ここでは、組織マネジメントが果たす役割と、企業が直面する課題をどのように克服できるのかを具体的に見ていきます。
人材の流出とエンゲージメント向上
近年、多くの企業が人材の流出や離職率の高さに頭を悩ませています。従業員が会社に満足感ややりがいを感じられない場合、優秀な人材ほど他社に流れてしまうリスクがあります。
組織マネジメントを適切に実践することで、社員一人ひとりの役割や目標が明確になり、成長実感を得られる環境を整備できます。また、成果を正しく評価し、フィードバックを行う仕組みを導入することで、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高まり、結果的に人材の定着率向上につながります。
組織全体の生産性・効率性向上
組織が大きくなるほど、「情報共有がうまくいかない」「業務が属人化する」といった非効率が生まれやすくなります。こうした問題を放置すると、生産性の低下や意思決定の遅れを招き、競争力を失う原因になります。
組織マネジメントを通じて、業務フローの可視化、情報の透明化、PDCAサイクルの徹底を行えば、無駄の削減と効率化を実現できます。さらに、従業員が自律的に動ける環境を整えることで、単なる業務効率化にとどまらず、組織全体のパフォーマンスを底上げすることが可能です。
多様性やリモートワーク環境での課題解決
現代の職場は、性別・国籍・世代の異なる多様な人材が共に働く環境へと変化しています。また、コロナ禍をきっかけにリモートワークやハイブリッドワークが定着しつつあり、従来の対面前提のマネジメントでは対応が難しくなっています。
このような環境で組織マネジメントは、心理的安全性の確保、柔軟な評価制度、オンラインでの円滑な情報共有といった仕組みを提供します。多様な価値観や働き方を尊重しつつ、全員が共通の目標に向かって協働できる組織文化を築くことができるのです。
現代の組織マネジメントにおける管理職の役割
かつての組織マネジメントにおいては、管理職の役割は「上層部の意思決定を部下に伝達し、実行させる」「自身の経験や成功体験をもとに指示を出す」といった、比較的単線的で指示命令型のものでした。こうした狭義のマネジメントは、安定した市場環境下では一定の効果を発揮してきました。
しかし、現代は技術革新や市場の急変、多様な価値観の共存など、予測困難な時代です。こうした環境下では、管理職が単に命令を下すだけでなく、方向性を示し、メンバーの多様な強みを引き出しながら共通のビジョンに向かって進む「広義のマネジメント」が求められています。リーダーシップを発揮しつつ、部下と双方向のコミュニケーションを取りながら組織を導くことが不可欠となっているのです。
さらに、日本における働き方改革の推進は、管理職のあり方にも大きな変革をもたらしました。これまでは成果や効率を重視するあまり、労働時間や職場環境への配慮が不足しがちでしたが、現在は部下のワークライフバランスを考慮し、長期的なパフォーマンスを維持できる環境を整えることが重要視されています。また、ダイバーシティ経営が進む中で、ジェンダーや年齢、国籍、働き方の違いを尊重し、全員が能力を発揮できる職場づくりも管理職の重要な役割となっています。
組織マネジメントに必要な能力・スキル
組織マネジメントには、組織を良い方向に進めるための能力が必要です。
ここでは、組織マネジメントに必要な具体的な能力を紹介します。また、能力を得るために日ごろからできる試みについても紹介しているので参考にしてみてください。
チームの目標設定/計画力
目標設定/計画力とは、チームがどこへどう向かって行くのかを具体的に示す力のことです。例えば、売上を2倍に増やすという目標を設定したら、そのために営業の成功率を2倍にする、そのためには営業の仕方をこう変えるといった具合です。
チームの目標設定/計画力がないと、チームがどこへどう進んで良いのかが分からなくなってしまいます。進むべき方向も、進み方も分からなければ、メンバーのモチベーションが上がらず、生産性も向上しないでしょう。
目標設定のコツは、大目標とその過程に達成する小目標を決めることです。また、期間や数値を具体的に定めることも、組織に目標を浸透させるという点で重要です。
コミュニケーション力
組織マネジメントにおけるコミュニケーション力とは、説明能力といっても良いでしょう。管理職には、なぜそういった目標を掲げているのか、なぜそういった判断をくだしたのかを、チームに説明し理解してもらうことが必要とされます。
メンバーが管理職に不満を感じるほとんどの場合が、決定に対しての説明不足です。理由も分からず業務をこなしていては不満が出るのも当然といえます。管理職は、チームのメンバーに対して納得できるように理由を説明する必要があるのです。
まずは、日ごろからチームメンバーとコミュニケーションを取るようにしましょう。「1on1面談」などを取り入れて、メンバーと話をする時間を設けるのも1つの選択肢です。
統率力
統率力とは、目的達成のために組織をまとめ上げる力のことです。
組織のメンバーの考え方、信条はバラバラですが、組織においてはこれをまとめ上げて同じ方向を向かせなければいけません。メンバーがそれぞれバラバラな方向を向いていると、目標達成に向けて真っすぐに進んでいけません。
組織の統率力を高めるためには、組織メンバーからの人望が必要です。管理職の人こそ自分から積極的に動き、メンバーから信頼される存在になりましょう。
実行力
ここでいう実行力とは、組織に与えた目標や業務を完遂させるための実行力のことです。目標を達成するためには、組織のメンバーに実際に動いてもらわなければいけません。
この実行力を高めるには、指示の伝え方や叱り方に気を付ける必要があります。感情的になるのではなく、「どうしたらメンバーは動いてくれるのか?」という観点から、メンバーと接するようにしましょう。
組織マネジメントを成功させる実践ポイント
組織マネジメントを効果的に行うには、単にルールや仕組みを整えるだけでは不十分です。管理職やリーダーが自らの在り方を明確にし、メンバーと信頼関係を築き、チーム全体で共通の目標を掲げることが必要不可欠です。ここでは、組織マネジメントを成功に導くための4つの実践ポイントを紹介します。
自分のミッションを明確にする
組織マネジメントの出発点は、管理職自身が「何を大切にし、どんな組織を作りたいのか」を明確にすることです。 「自分はどんな存在でありたいか」「妥協できない価値観は何か」「管理職として何を期待されているのか」――こうした問いに向き合うことで、自分自身の“マイビジョン”が形作られます。
ミッションやビジョンが不明確なままでは、部下に方向性を示したり、信頼を得たりすることは難しいでしょう。逆に、リーダーが自らの思いを言語化し、チームに伝えることで、組織全体が一体感を持ち、目標達成に向けて動き出せるのです。
職場の心理的安全性を高める
職場において本音を語ることは、多くの人にとってリスクを伴います。そのため、議論が表面的になり、真の課題が見えにくくなることがあります。ここで重要となるのが「心理的安全性」です。
多様な価値観やバックグラウンドを持つ人材を活かすには、命令や管理によるマネジメントでは不十分です。必要なのは、メンバー同士が互いの強みを認め合い、共に新しい価値を生み出す「協働・創発のマネジメント」です。その土台となるのが心理的安全性であり、管理職が積極的にその環境を整備することが求められます。
メンバー1人ひとりと対話し、仕事への考え方・特性を理解する
組織マネジメントを成功させるうえで欠かせないのが、メンバーとの継続的な対話です。チーム全体の目標設定や方針策定も重要ですが、それ以上に大切なのは、メンバー1人ひとりが「どのような価値観を持ち、どんな働き方を理想としているのか」を理解することです。
人によって得意分野やモチベーションの源泉は異なります。ある人は数字や結果を重視し、別の人は人間関係やチームの雰囲気を大切にするかもしれません。こうした個性を把握することで、管理職は適切な役割分担を行い、強みを最大限に活かすことができます。
また、日常的な1on1ミーティングやフィードバックの場を設けることで、メンバーが抱える不安や課題を早期に把握でき、離職リスクの低減やエンゲージメントの向上にもつながります。
さらに、こうした対話を通じて「この職場では自分が尊重されている」という感覚が生まれれば、心理的安全性も高まり、主体性や創造性の発揮が促進されます。結果として、チーム全体の生産性向上にも直結するのです。
チーム全体で目標・価値観を共有する
管理職のビジョンが明確になり、信頼関係が構築されたら、次はチーム全体で「共通のビジョン」を作り上げる段階です。
まずは管理職が自分の「マイビジョン」を示し、それをチームビジョンの仮案として提示します。そのうえで、メンバーそれぞれの思いや目標を引き出し、重なる部分を集約して「チームビジョン」として再定義します。こうしたプロセスを経ることで、メンバーは「自分たちの声が反映された目標」として捉え、主体的に取り組むようになります。これが、メンバーそれぞれがチーム全体での目標・価値観を自分事として捉え、共有するための鍵です。
管理職が組織マネジメントを習得するための代表的なフレームワーク

組織マネジメントを行う上で、組織マネジメントのフレームワークを知っておくことは重要です。フレームワークを知っておくことで、そのフレームワークに当てはめて組織の現状を分析することができます。
ここではアメリカのコンサルティング会社マッキンゼーの提唱するフレームワークを紹介します。
マッキンゼーが提唱する「7S」
7Sというフレームワークは、アメリカのコンサルティング会社マッキンゼーが、「エクセレント・カンパニー(超優良企業)」を分析したときに生まれました。30年以上も前に生まれたフレームワークですが、今でも多くのコンサルティング会社などが利用しています。
7Sは企業の戦略や仕組みを7つの要素に分け、それらが相互にどう関係し合い、組織の成果に影響を与えるかを整理したものです。優れた企業ほど、7つの要素をバランスよく連動させながら戦略を実行しているといわれています。
この7Sは「ハードの3S」と「ソフトの4S」に分けられます。
ハードの3S
- Strategy(戦略):企業がどの方向に進むのかを示す道筋
- Structure(組織構造):役割分担や指揮命令系統などの仕組み
- System(システム):社内情報システムや予算管理制度、目標管理制度などを含む運用
ソフトの4S
- Shared Value(共通の価値観):組織に浸透する理念や文化
- Style(経営スタイル):リーダーシップの在り方や意思決定の傾向
- Staff(人材):組織を構成する人々やその特性
- Skill(能力):組織や人材が持つ強みや専門的スキル
ハードの3Sは比較的短期間で変更可能ですが、ソフトの4Sは価値観や文化に根差しているため、一朝一夕に変えることは困難です。組織変革では「戦略や構造(ハード)」に手を加えることが多い一方で、それだけでは十分ではありません。
たとえば、新しい戦略を立てても、社員全員をすぐに入れ替えることはできませんし、必要なスキルが短期間で身につくわけでもありません。だからこそ、ハードとソフトの両面を統合的に整合させることが、組織マネジメントの成功のカギ となります。
フレームワークを実務に活かすためのポイント
7Sのフレームワークを活用して組織改革を進める際には、その変化が企業全体や社員に少なからぬ負担をもたらすことを理解しておく必要があります。
たとえば、組織構造を変更すれば、一時的に業務の効率が下がったり、再編コストが発生したりするケースがあります。改革が軌道に乗れば回復や成長が見込めますが、逆に失敗すれば企業業績の悪化につながるリスクも否めません。
また、従業員にとっても環境の変化は大きな影響を及ぼします。企業文化や経営方針、人材育成の方向性が変わることで、現場の負担が増え、場合によってはモチベーション低下や離職率の上昇につながる可能性もあります。
したがって、7Sを導入する際には「組織と社員にどのような負荷がかかるか」を事前に想定し、全社的な理解と協力体制を築いたうえで取り組むことが成功の条件といえるでしょう。
関連動画:組織が拡大するときに直面する課題を解決 組織問題のスコア化と管理職意識の育成のポイント
組織マネジメントに役立つツール
組織マネジメントにおいて重要なのは、例えば、「業務の効率化」「組織の生産性向上」などです。
通常、把握することの難しい企業内部のそれらの課題を解決し、組織マネジメントに役立つのがラフールサーベイです。
ラフールサーベイは「社員の状況の把握・分析」や「職場の状況に応じた改善策提案」をしてくれる、職場環境改善に最適なサーベイツールです。その具体的な機能や特徴について次の段落から解説していきます。
ラフールネス指数による可視化
組織・個人の「健康度合い」から算出したラフールネス指数により、企業が抱えているメンタルヘルスの課題を可視化します。
個人ラフールネス、職場ラフールネス、総合ラフールネスの3つの指数を、他社・時系列比較で把握できます。また、全国平均や各業界と比較することも可能です。
これによって自社が、どれくらい健康に経営が行えているのかを、客観的な視点から把握できます。
直感的に課題がわかる分析結果
上記の分析結果は、グラフや数値で確認することができます。部署や男女別にデータをソートし、細分化された項目とのクロス分析も可能です。
一目で分かる見やすいデザインのインターフェースで、直感的に課題が見つかります。
課題解決の一助となる自動対策リコメンド
数値による分析結果から、自動でフィードバックをコメントを表示してくれる機能を搭載しています。良い点・悪い点が簡単に分かるので課題解決に大いに役立つでしょう。
重視したい項目もピックアップすることが可能です。
154項目の質問項目で多角的に調査
ラフールサーベイのストレスチェックには、154の項目が設けられています。154項目の構成は以下のとおりです。
- 厚生労働省推奨の57項目
- 独自の84項目
従来のストレスチェックでは把握できなかった「受験者の性格」「衛生要因(給与・福利厚生)」「エンゲージメント(エンプロイー・ワーク)」などを追加しています。多角的な調査により、より詳細な状況を把握することが可能です。
19の質問項目に絞り、組織の状態を定点チェック
19の質問項目に絞ったショートサーベイで、組織の状態を定点チェックすることも可能です。月次での変化を負いながら、課題への対策効果がどれぐらい上がったか可視化します。
こちらは月一回の実施を推奨しています。
適切な対策案を分析レポート化
細かい分析結果により、課題を把握し、リスクを見える化できます。
部署/男女/職種/テレワーク別に良い点や課題点を一望化
ラフールサーベイでは、部署や男女、職種別にデータ分析をすることが可能です。他部署・男女・職種での比較ができるだけでなく、危険ゾーンとなる箇所が直感的に一目で確認することができます。
また、「テレワーク属性」を追加したことで、テレワークを行っている社員を含めたデータ分析をできるようになりました。テレワークを行う社員の状況までも可視化できます。
まとめ
社員全員のことを考えた上で、社内の課題にマッチした業務を効率化するための対策を行うことができれば、管理職や社員の生産性向上、ストレス低下、離職率低下など様々なメリットを享受することが可能です。社内の課題にあった的確な対策を見つけるための方法もいくつかありますが、ラフールサーベイを使うことで効率的にその作業を行えます。