「ヒヤリハット」で済ませていませんか?職場で起こる事故の多くは、従業員の行動が原因となる「不安全行動」に関係しています。
労災は企業に多大な損失をもたらすだけでなく、従業員の命と健康を脅かす深刻な問題です。
本記事では、企業の人事担当者様向けに不安全行動がなぜ起こるのか、その根本原因から具体的な防止策、そして対策を進める上で陥りやすい落とし穴までを徹底的に解説します。
安全で生産性の高い職場を実現するためのヒントを見つけ、労災ゼロを目指しましょう。
不安全行動とは?
不安全行動とは、人の行動や判断ミスをきっかけに危険な状態を作り出す行為全般を指します。
具体的には保護具の不着用、定められた手順の無視、指差呼称の怠りや危険な場所への無断侵入などがこれに該当します。
従業員自身の不注意、誤った認識、慣れによる気の緩みなどが原因で発生することが多いのが特徴です。
参考:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
不安全状態との違いは?
不安全行動と混同されやすいのが「不安全状態」です。
不安全状態とは設備、機械、施設、作業環境といった「モノや場所」に起因する危険な状態のことです。
例えば、安全カバーが外れた機械、整理整頓されていない作業場、照明の不足などがこれにあたります。
多くの労働災害は、この不安全行動と不安全状態のどちらか一方だけでなく、両者が組み合わさることによって発生します。
例えば「床に工具が散乱している(不安全状態)場所で、足元を確認せずに急いで歩いた(不安全行動)結果、転倒した」といったケースです。
原因を正しく見極め、人・モノ・環境の両面からアプローチすることが、災害防止には不可欠です。
不安全行動が重要視される理由
企業にとって従業員の安全と健康を守ることは、企業の持続的な成長、競争力強化、そして社会的責任を果たす上で極めて重要な経営課題です。
労災は治療費や休業補償だけでなく、生産性低下、企業への信用の失墜、従業員の士気低下などさまざまな損失を招きます。
事故が起きれば企業のブランドイメージは大きく傷つき、優秀な人材の離職にも繋がりかねません。
そのため、不安全行動対策は「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えるべきです。
安全な職場環境であれば従業員が安心して業務に集中できるため、結果的に生産性向上に繋がります。
企業が従業員の安全を真剣に考える姿勢は、従業員エンゲージメントを高め、企業の競争力強化にも直結します。
近年重視されるESG経営においても、従業員の安全・健康は重要な要素であり、企業の社会的評価を高める上でも不可欠な取り組みなのです。
不安全行動はなぜ起こる?「人の心理」と「組織の課題」
不安全行動は、個人の心理的要因(ヒューマンエラー)と、組織や環境的要因が複雑に絡み合って発生します。
個人の心理的要因(ヒューマンエラー)
個人の心理的要因としては、慣れた作業での気の緩みや疲労、集中力低下などによる無意識な行動・うっかりミスが挙げられます。
「これくらいなら大丈夫だろう」「自分は事故を起こさない」といった思い込み、いわゆる危険軽視・過信は不安全行動を誘発します。
ルールや手順の理解不足・誤解、あるいは体力不足や体調不良といった身体的能力の限界も、安全な行動を妨げる要因となります。
組織・環境的要因
組織や環境が抱える課題としては、安全意識を育むための安全教育の形骸化、OJTの不徹底、危険感受性の低下が挙げられます。
また、不適切な設備や整備不良、作業スペースの不足といった作業環境の不備は、不安全行動を誘発する物理的な原因となります。
マニュアルの不備や、ルールが守られない職場風土も深刻な問題です。
管理者の指導不足や監視不足といった管理監督体制の不十分さ、さらにはヒヤリハット情報の共有不足や、意見を言いにくい雰囲気といったコミュニケーション不足も原因のひとつです。
安全行動へのインセンティブ不足や、危険行為を誘発するような評価制度、そして長時間労働や休憩不足といった労働環境の問題も従業員のストレスを高め、不安全行動のリスクを増加させます。
不安全行動の具体例と労災事例(業種別)
実際に不安全行動がどのように労災に繋がるのか、具体的な事例を通じて見ていきましょう。
労災は単なる「不注意」で片付けられるものではなく、その背後には個人の心理、そして組織の安全管理体制や文化に根ざした要因が潜んでいます。
製造業
稼働中のプレス機内で安全カバーを外したまま清掃作業を行い、指を挟んでしまった事故があります。
これは稼働中の機械への接近や安全カバーの取り外しといった不安全行動が原因です。
その背景には、作業手順の無視、危険軽視、時間短縮への意識、そして管理者による監視不足や安全カバー機能に関する認識不足がありました。
人事担当者としては、安全教育で安全カバーの重要性を徹底し、安易な取り外しが重篤な事故に繋がることを具体的に示す必要があります。
また、時間短縮を目的としたルール逸脱がないか実態をヒアリングし、安全装置が安易に外せない「ポカヨケ」の導入や、定期的な職場巡視でルール遵守状況を確認し、指導と再教育を行うことが求められます。
建設業
高所作業において安全帯の着用をせずに作業を行い、足を踏み外して転落、重傷を負う事故が発生しています。
これは安全帯の不着用という不安全行動が引き起こした典型的な事例です。
「少しの間だから」「慣れているから大丈夫」といった過信や安全意識の低さ、管理者の指導不足が背景にありました。
人事担当者としては、高所作業の危険性を疑似体験できる教育(VR/AR活用など)を導入して危機意識を高め、安全帯の装着方法や正しい使用に関する再教育を徹底すべきです。
さらに安全パトロールを強化し、安全帯の着用状況を厳しくチェックする体制を構築し、協力会社を含めた全員が安全ルールを理解し遵守するための定期的な合同安全ミーティングを実施することが不可欠です。
サービス業
飲食店では厨房で床にこぼれた油を放置したまま、滑りやすいサンダルで急いで移動し、転倒して火傷を負う事故があります。
これは油の放置、滑りやすい履物の着用、急いだ移動という複数の不安全行動が重なった結果です。
清掃ルールの不徹底、危険軽視、5S活動の形骸化、従業員の安全意識の低さ、管理者による職場環境チェックの甘さが背景要因として挙げられます。
人事担当者としては、5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底と定期的な監査を行う必要があります。
また、厨房での専用シューズ(滑りにくい靴底)着用を義務化し、交換目安を明確にすることも重要です。
油や水がこぼれた際の即時清掃ルールを徹底し、声かけ運動を推進すること、そして火傷対策として適切な保護具(アームカバーなど)の着用を義務付けることも有効な対策となります。
企業が取り組むべき不安全行動防止策とは?
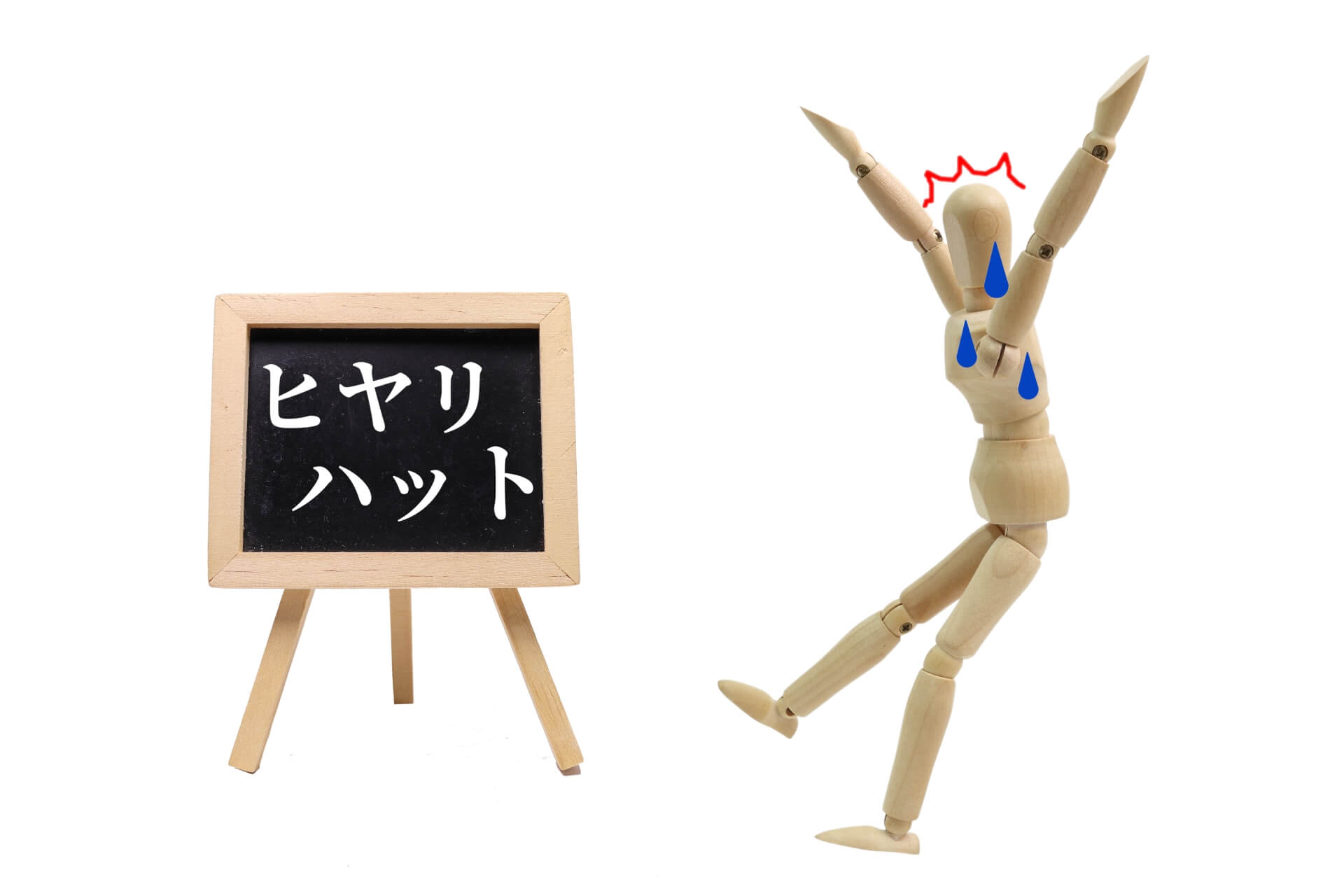
不安全行動を未然に防ぎ、労災ゼロを実現するためには、企業が組織的に、かつ継続的に取り組む必要があります。
人事担当者が中心となって推進すべき防止策を5つご紹介します。
安全教育の徹底と継続
従業員の安全意識を高め、危険を予知する能力を養うための教育は、不安全行動防止の土台です。
具体的には、新入社員、中堅、管理者といった階層別の教育を体系的に実施し、各階層に合わせた内容で安全の重要性、具体的な危険予知方法、緊急時の対応などを学ばせます。
また、KYT(危険予知訓練)の導入や活性化、ヒヤリハット研修、VR/AR活用による疑似体験研修などを通じて危険感受性を高めることも重要です。
教育内容は時代の変化や最新の技術、過去の事故データに基づき、常に見直しとアップデートを行うことで、その実効性を高めます。
マニュアルとルールの整備
安全を確保するための物理的な環境とそれに伴う運用ルールを明確にし、徹底することが重要です。
根本的な安全対策として、機械設備の安全装置設置や作業スペースの改善といった工学的対策を優先します。
作業手順については「なぜこの手順が必要なのか」という理由も明確に記載し、現場の実態に即した作業手順書を作成し全従業員に徹底します。
デジタル化や図解、写真などを活用し、視覚的に理解しやすい工夫も有効です。
作業内容に応じた適切な保護具を従業員に支給し、着用ルールを徹底することで、万が一の事故の際の被害を最小限に抑えられます。
ヒヤリハット・労災情報の活用と再発防止
過去の経験から学び、未来の事故を防ぐための情報共有と改善の仕組みを構築しましょう。
従業員が気軽にヒヤリハットを報告できる仕組みと雰囲気を作り、報告者へのフィードバックを欠かさないようにすることが重要です。
報告された内容は単なる記録で終わらせずにその背後にある要因を分析し、具体的な改善策に繋げます。
労災が発生した際はその原因を深く掘り下げて究明し、同様の事故が他部署や他拠点で発生しないよう得られた教訓を組織全体で共有しましょう。
そして安全対策は一度行えば終わりではありません。常に改善を繰り返すことで、より安全性の高い職場環境を目指します。
管理監督者と他部署との連携強化
安全衛生活動を実効性のあるものにするためには、現場を統括する管理監督者と人事以外の各部門との連携が不可欠です。
管理監督者が自身の安全衛生に関する役割と責任を明確に認識し、部下への指導や職場巡視のスキルを向上させるための教育を強化します。
また専門家である産業医や衛生管理者と密に連携し、職場の健康管理やリスク評価に関する助言を積極的に受け入れましょう。
部門間の壁を越えた連携を通じて、総合的な安全対策を推進していくことが求められます。
従業員の健康とメンタルヘルスケアの推進
従業員の心身の健康状態は不安全行動に大きく影響します。健康な状態を維持できるよう、サポート体制を構築することも人事の重要な役割です。
長時間労働は疲労や集中力低下を招き、不安全行動のリスクを高めてしまうので、勤怠管理の徹底や業務効率化の推進により過重労働の解消に努めましょう。
ストレスや精神的な不調もヒューマンエラーの原因となり得ます。
定期的なストレスチェック、相談窓口の設置、ラインケアの推進など、従業員の心の健康をサポートするメンタルヘルスケア体制を整えることも不可欠です。
さらに定期健康診断の受診を促し、結果に応じた適切な事後措置や保健指導を実施することで、従業員の健康維持・増進を図りましょう。
失敗から学ぶ!不安全行動対策で陥りやすい落とし穴
どんなに良い対策も、運用方法を誤ると効果は半減します。
対策を進める上で陥りやすいポイントと、その回避策について解説します。
「罰則」に偏りすぎたアプローチ
不安全行動に対し罰則のみで対応しようとすると、かえって従業員がヒヤリハットや軽微な事故を報告しなくなる可能性があります。
恐怖心から隠蔽につながり、真の原因究明や改善の機会を失ってしまうためです。
罰則だけでなく教育や環境改善、行動変容を促すポジティブな働きかけとのバランスが重要です。
現場の実態と乖離したルール作り
本社や一部の管理者だけでルールを策定し、現場の意見を取り入れない場合実態に合わないルールは形骸化しやすくなります。
現場の従業員こそが作業の具体的な危険や効率的な手順を最も理解しています。
そのため現場の従業員を巻き込み、彼らの意見を吸い上げる仕組み(例:安全委員会への参加、アンケート、ヒアリング)を導入することが不可欠です。
「安全は現場任せ」という意識
安全対策は現場の管理監督者や作業員任せにせず、経営層と人事部門が積極的にコミットし、リソースを投入する姿勢を示す必要があります。
人事部門は全社的な視点から安全衛生管理体制を構築し、各部門への支援や連携を促進する「司令塔」としての役割を担うべきです。
一度きりの対策で終わってしまう
安全対策は「終わり」がなく、常に改善を続ける必要があります。
一度施策を打ったらそれで安心するのではなく、効果測定と継続的なPDCAサイクルを回すことで、常に最適な状態を目指しましょう。
環境の変化や新しい技術の導入、従業員の入れ替わりなど、常に状況は変化するため対策も柔軟に見直していく必要があります。
コミュニケーション不足
安全に関する情報は、定期的にかつ分かりやすく従業員に伝え続ける必要があります。
一方的な情報提供だけでなく、従業員が安全に関する疑問や懸念を気軽に相談できる心理的安全性のある環境を築くことが大切です。
オープンなコミュニケーションは、潜在的な危険の早期発見や、従業員自身の安全意識向上に繋がります。
不安全行動を防ぐには組織改善ツール「ラフールサーベイ」
ラフールサーベイは、「社員の状況の把握・分析」や「職場/チームの状況に応じた改善策提案」をしてくれる、組織開発に最適なサーベイツールです。
漠然となりがちな組織課題を定量的に可視化できるため、PDCAを回しやすい設計となっています。
また、従来の社内アンケートなどでは見えにくい心の状態などを可視化することで、社員が安心して働ける環境づくりのお手伝いをします。
社員が安心して働ける環境づくりは、企業の成長・拡大のための土台となります。
まずは、社員一人一人にとって居心地の良い職場を整え、人材の定着と組織改善に繋げましょう。
まとめ
不安全行動対策は単なる労災防止に留まらず、企業の持続的な成長と従業員の幸福に直結する重要な経営課題です。
不安全行動は個人の心理的要因と組織の環境的要因が複雑に絡み合って発生するため、その対策には多角的な視点と継続的な取り組みが不可欠です。
人事担当者は、安全教育の推進、作業環境・ルールの整備、ヒヤリハット情報の活用、管理監督者との連携強化、そして従業員の心身の健康サポートまで幅広い視点から安全衛生管理に戦略的に取り組む必要があります。
現場の声を聴きPDCAサイクルを回し続けることで、安全で活気ある職場環境を実現し、企業の価値向上にも繋げていきましょう。













