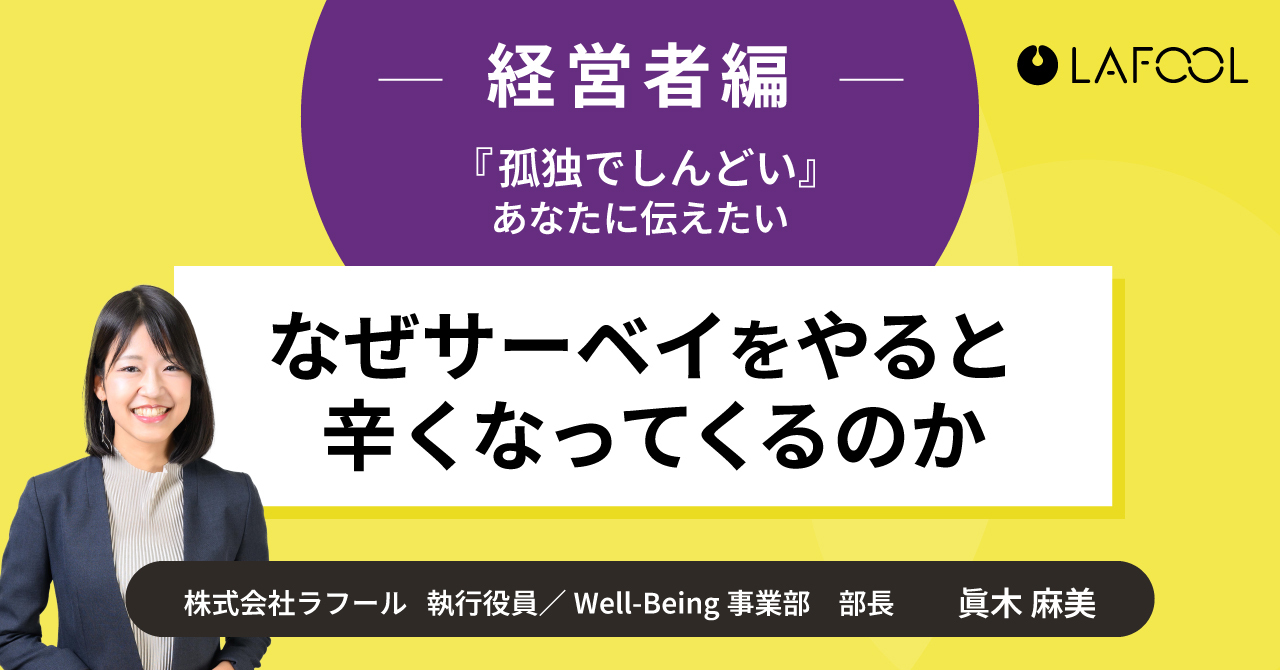こんにちは。
株式会社ラフールで執行役員をしている眞木です。
私は日頃から、ラフールサーベイという組織改善ツールを通じて、人事・管理職、そして経営者の方々と「どうすれば組織をより良くできるのか」を一緒に考え続けてきました。
その中で、経営者の方からよく聞くのが「サーベイをやると、自分が否定されたように感じてしまう」「結果を見るのが辛い」という声です。
経営者にとって、サーベイの結果は単なるデータではなく、経営そのものの評価のように突き刺さり、孤独を深めてしまうことがあります。
しかし同時に、それは「組織を変えるための出発点」にもなり得ます。
辛さをどう受け止め、どう発信するかによって、組織の未来は大きく変わっていくのです。
この記事では、サーベイを続ける中で「孤独でしんどい」と感じている経営者の方に、前に進むヒントを少しでもお伝えできればと思います。
サーベイ結果で「自分が否定された」感覚に
サーベイを導入すると、毎回の結果は数字やスコアとして経営者の目に届きます。
その数字は 「従業員の意見」にとどまらず、ときには経営のあり方そのものを突きつけてくるように感じられることがあります。
「信頼されていないのではないか」「自分の方針が間違っていたのではないか」。
そんなふうに、まるで自分自身が否定されたかのように受け止めてしまうのです。
誰のせいでもないのに、つい人事や管理職に責任を問いたくなったり、苛立ちを覚えたりすることもあります。
けれども同時に、そんな感情を誰にも相談できず、一人で抱え込み、落ち込んでしまう。これが経営者特有の「孤独」といえるでしょう。
さらにサーベイを続ける中では、「やっても人が動かない」「施策をしても数字が上がらない」「コメントに心が折れる」といった行き詰まりを感じ、サーベイの意義そのものを見失ってしまう時期もあります。
その背後にあるのは、「社員の声を聴くこと自体が辛い」という本音です。私たちラフールはその感覚を否定することはありません。むしろ、そこを出発点として前に進むことが大切だと考えています。そして忘れてはいけないのは、サーベイには常に組織が次に進むための手がかりが含まれているということです。サーベイは「批判の声」ではなく、「翻訳機」。経営の意図と現場の体感のズレを可視化し、対話を前進させるための共通言語なのです。
サーベイが「儀式」になってしまうとき
ただし、その価値を十分に活かせないまま、形骸化してしまうケースも少なくありません。
現場では、次のような場面が繰り返し見られます。
- 会議が「点数の責任追及」だけで終わってしまう
- 改善施策を盛り込みすぎて、現場が疲弊する
- 数字の上下ばかりを議論して、具体的なアクションが決まらない
- 結果を共有しただけで満足し、次につながる対話が生まれない
- 最初に経営トップの心が折れて、メッセージの発信が止まってしまう
こうした状況を繰り返すと、サーベイは「形だけの儀式」と化してしまいます。
サーベイが育てるのは「声を聴く姿勢」
では、それでもサーベイを続ける意味はどこにあるのでしょうか。
サーベイの価値は、何よりも「社員の声を聴く姿勢」を組織に根づかせることにあります。改善に取り組んでも、すぐに成果が出るとは限りません。ときには結果が悪化することさえあります。しかし、そこでやめてしまえば「経営が社員の声を聴く」という姿勢そのものが失われてしまうのです。
サーベイは即効薬ではなく、長期的に組織を強くするための体質改善のような存在です。だからこそ大切なのは、姿勢を形だけで終わらせず、仕組みと行動に落とし込むこと。その導線をつくるのが、経営・人事・管理職の協働なのです。ここからは、経営者がどのように関われば“姿勢”が現場の具体的な一歩へと変わるのかをお伝えします。
経営者がまず示すべき姿勢
厳しい結果を目の前にすると、人事や管理職を責めたくなる気持ちが生まれることもあるでしょう。
しかし、経営者がまず示すべきは「責める」のではなく「一緒に考えよう」という姿勢です。サーベイ結果は単なる数字ではなく、経営と現場をつなぐ共通言語です。
経営者が「一緒に考えよう」と合図を出すことで、サーベイは責任を追及するものではなく、組織の未来をつくるための材料として活かされていきます。
経営者・人事・管理職の役割分担
経営者が「一緒に考えよう」という合図を出したあとは、その思いを具体的な行動に落とし込むことが大切です。
そのためには、三者それぞれの役割を明確にし、リレーのようにつないでいく必要があります。
【経営者の役割】方向性を示し、最終判断を下す
経営者の役割は、サーベイ結果を踏まえて組織の大きな方向を決めることです。
たとえば「今回は業務負荷を優先的に改善する」とテーマを絞ったり、「この施策はやめてこちらに集中する」と判断を示すことです。
経営者が方向を示すことで、サーベイは組織の「未来を決める材料」になります。
【人事の役割】経営と現場をつなぎ、動きを生み出す
人事は、経営と現場の間に立ち、サーベイを「動き」に変える起点をつくります。
数字をどう解釈すべきかを整理して現場に伝えたり、会議で決まったアクションを必ず実行につなげる仕組みを整えます。
人事が橋渡しをすることで、サーベイは単なる報告から「双方向の対話」へと育っていきます。
【管理職の役割】現場に落とし込み、アクションを実行する
管理職は、会議で決まったことを現場で小さく実行し、学びを持ち帰ります。
たとえば、「週1回の1on1をやる」と決まったら必ず実施し、その結果を共有することです。
管理職が小さな実行を積み重ねることで、サーベイは「現場に根づく変化」を生みます。
サーベイを「数字を見るだけ」で終わらせず、次の一歩につなげられるかどうかは、経営者の旗振りから始まります。
サーベイを続けた組織が実際にやっていた工夫
経営・人事・管理職がそれぞれの役割を果たすと、サーベイは数字の共有で終わらず、日々の運用に小さな工夫が積み重なっていきます。
実際にサーベイを続けて成果を出した組織では、こんな工夫が積み重なっていました。
- 結果の共有のしかたを変えた
全社ランキングや部署間の比較はやめ、前回比だけを示すことにした。ネガティブな言い訳が減り、会議が「次にどう動くか」を話す場に変わった。 - 安心して話せる場をつくった
トライがあれば必ず拍手するルールにした。挑戦を歓迎する空気ができ、発言や行動が増えた。 - 短期で検証できる小さなアクションを実行した
「半年かけて取り組む」ではなく「まずは2週間だけ試そう」とした。小さく区切ることで動き出すハードルが下がり、施策の数も学びも増えた。 - 定点観測を続けた
20問程度の状態把握をするものを月1回で続けた。シンプルだから比較がしやすく、単発の数字に振り回されすぎずに傾向をつかめるようになった。
こうした地道な工夫の積み重ねが、組織に変化を根づかせていったのです。
経営者の皆さまにお願いしたい3つのこと
経営・人事・管理職がそれぞれの役割を果たすことが前提ですが、最終的にサーベイを「次の一歩」につなげられるかどうかは、経営者の関わり方にかかっています。
ここからは、経営者の皆さまに特に意識してほしい3つのポイントをお伝えします。
一回で白黒をつけない
サーベイの結果は、あくまで一時点のスナップショットにすぎません。
だから、1回のスコアで制度や人を判断してしまうと、誤った結論につながりかねません。
「計測 → アクション → 再計測」を1サイクルとし、少なくとも3回まわして傾向を見ていくことが大切です。
焦らずに繰り返すことで、数字の裏にある本当の課題や変化が見えてきます。
「なぜできない?」を「一緒にやるなら?」に言い換える
サーベイ結果を前にすると、つい「なぜできないのか」と問い詰めたくなることがあります。
けれども、それでは現場は守りに入り、動きが止まってしまいます。
大切なのは、責任追及ではなく「どうすればできるか」を一緒に考えること。
会議では必ず「誰が・いつまでに・何をするか」を1つ以上決めて終えるようにすれば、サーベイは行動に直結する場に変わります。
サーベイの目的を言語化して、あなたの言葉で宣言する
サーベイはあくまで手段であり、目的を見失うと「ただやるだけ」になってしまいます。
だからこそ、経営者自身が「何のために続けるのか」を自分の言葉で語ることが欠かせません。
「離職率を下げることで、安心して長く働ける環境をつくりたい」
「業務負荷の指標を改善することで、創造的な仕事に時間を使えるようにしたい」
「働きがいの指標を高めることで、挑戦を後押しできる組織にしたい」
など、自社の成果指標と結びつけて発信すると、社員も腹落ちしやすくなります。
経営者の言葉で語ることで、サーベイは会社全体の共通の挑戦として根づいていきます。
この3つを忘れずに、経営者としての言葉と行動で示していただきたいと思います。それが、組織を着実に前へ進める力になります。
ラフールとして、経営者の隣でできること
ここまで見てきたように、サーベイは経営者の旗振りから始まり、人事や管理職と役割を分担して続けることで成果につながります。
しかし現実には「結果が思うように改善しない」「会議が重たくなる」といった場面も多く、経営者が孤独を感じやすいのも事実です。
だからこそ大切なのは、経営者が一人で抱え込まずに進められる仕組みを持つことです。
結果の見せ方を工夫する、現場に小さなアクションを積み上げてもらう、人事が橋渡しを担う――こうした取り組みを支える仕組みがあってこそ、サーベイは継続して力を発揮できます。
私たちラフールはそのプロセス全体を下支えし、経営者が孤独にならずに取り組みを続けられるよう力を尽くしたいと考えています。
データの解釈から、現場への橋渡し、仕組みづくりまでを支えながら、経営者と共に歩んでいきます。
サーベイは、経営者が一人で戦うためのものではありません。
経営者・人事・管理職・従業員、そして私たちラフールが一緒になって取り組むことで、組織は「孤独に戦う場」から「共に考え、共に歩む場」へと変わっていきます。その積み重ねがやがて文化をつくり、組織を望む未来へと導きます。