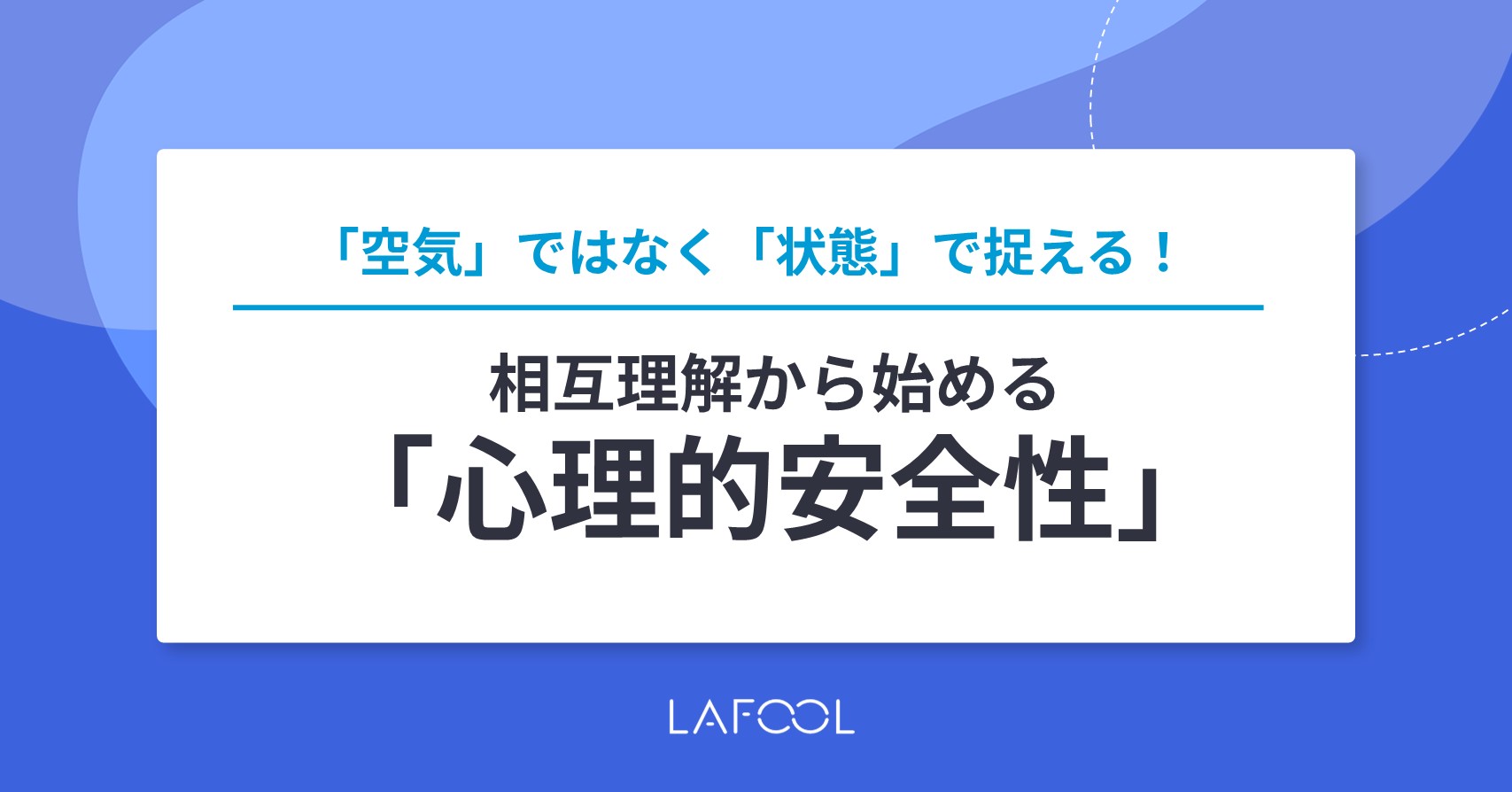「心理的安全性って結局、何なの?」を言語化する
「心理的安全性って、なんとなく“雰囲気が良い”ってこと?」
――そんなふうに、現場でもやもやと感じたことはありませんか?
この数年で大きく焦点があてられる「心理的安全性」ですが、
「じゃあ、何を持ってすれば高いっていえるの?」
「うちの会社の人って仲いいよね、けどそれって心理的安全性が高いの?」
このように、何となく大事なのはわかるけど、良し悪しの判断がつかない感じがありませんか?
「心理的安全性ってよく聞くけど、正直ふわっとしていてよく分からない」。本記事は、そんな方に向けて、ラフールが実際に支援してきた企業の現場での声をもとに、“相互理解”と“可視化”という切り口から、そのヒントをお伝えします。
心理的安全性=“良い関係”ではない
「心理的安全性が高い職場」と聞くと、多くの人が“仲の良いチーム”や“和やかな雰囲気”を思い浮かべるかもしれません。
しかし、それはあくまで結果の一側面であり、本質とは少しズレています。
ラフールでは、心理的安全性を「仲の良さ」ではなく、“本音が発言できる状態”と捉えています。 雰囲気が良くても、逆にその空気を壊さないよう、本音の発言を避けるチームも多く見てきました。むしろ、“言わないことで波風を立てない”という暗黙の同調圧力が働いていることもあるためです。
心理的安全性を高める目的は、社員同士が仲良くなることではなく、本質的な問題提起や対話が促進され、建設的な行動が取れるようになること。
つまり、組織として成果を出すための“前提条件”と捉えることが重要です。
それが崩れると、何が起きるのか?
先ほどまでは心理的安全性が高い状態について触れました。
では逆に、心理的安全性が低い状態とは、具体的にどのようなリスクを抱えているのでしょうか?
まず顕著に現れるのが、「本音が出てこない」という現象です。
メンバーが黙りがちになる、会議で意見が出ない、課題が共有されずに先送りされる。
これは、単なる“会話不足”ではなく、“言えない空気”が定着しているサインです。
その結果として起きるのが、エンゲージメントの低下や離職意向の増加です。
実際にラフールサーベイで見てきた結果でも、心理的安全性にかかわりのあるスコアが低い部署ほど、離職意向との相関が高く見られる傾向があります。
誰にも本音を言えず、誤解や不安が蓄積され、やがて「ここにいても成長できない」「わかってもらえない」と感じ、会社を去る決断につながります。
また、リーダーやマネージャー側にとっても、「メンバーの本当の課題が見えない」ことによる意思決定の誤りや機会損失が発生します。
現場の実情を把握できず、対処が後手に回る。
これは業績や組織風土にも確実に影響します。
さらに活発な議論による新しいアイディアの創出や知見蓄積の絶好の機会です。そうした場を失うことは会社全体にとっても大きな損失となりかねません。
ラフールがこれまで受けてきたご相談でも、心理的安全性の低さが組織課題に大きな影響を及ぼす場面を多く見てきました。
特に問題なのは、その「欠如」に気づきづらいという点です。可視化して初めて、現場の沈黙や離職傾向の背景が見えてくることも少なくありません。
だからこそ、今、あらためて“状態としての心理的安全性”を見直す必要があるのです。
本音が出ない理由は、「信頼の欠如」ではなく「状態の不透明さ」かもしれない
相互理解の欠如こそが、心理的安全性を損なう
本音が出ないのは、「信頼がない」からではありません。相手のことを“よく知らない”からです。
心理的安全性を損なう本質的な要因は、「信頼関係の欠如」ではなく、相互理解の欠如」にあるのです。
たとえば、相手が何を大切にしていて、どんな不安を抱えているのかが分からなければ、「これを言っても大丈夫かな?」と発言をためらい、対話が滞ります。
つまり、「互いに何を考え、何を大切にしているかを理解できていない」状態がコミュニケーションにおける沈黙を生み、これが積み重なると結果的に無意識に「言わない方が無難」という空気を生み出してしまいます。
組織と個人、それぞれの“見えなさ”を可視化する方法
では、この相手の考えや価値観が「見えていない」をどうすれば解消できるのでしょうか?
答えは、相互理解を“感覚”ではなく“データ”でとらえることです。
ラフールサーベイなら、個人と状態や性格特性、組織の傾向などを可視化できます。
- 個人ごとの特性:どんな性格タイプなのか、何にストレスを感じやすいのか
- 組織全体の傾向:どんな価値観の傾向があるのか、どこにストレスや不安の集中があるのか
- 関係性の状態:上司部下間に信頼感があるか、対話が生まれやすい関係性かどうか
こうした“目に見えづらい状態”を定点で把握することで、単なる課題の列挙ではなく、「どこに・どんな対話を入れるべきか」という具体的な打ち手を見つけやすくなります。
「この人は、こういう価値観を大事にしてるんだ」「このチームは今、こういう不安を抱えている」といった理解が深まれば、配慮のポイントが明確になり、対話のきっかけも自然と生まれやすくなるわけです。
実際にラフールサーベイをご活用いただく現場でも、数値の変化をきっかけにして対話が生まれるケースも多くあります。
つまり、サーベイによる可視化は相互理解の入口であり、対話の土台となるのです。
数値で捉えるからこそ、対話が始まる
「対話が足りない」ではなく「対話の材料が足りない」
現場では「対話の時間を増やそう」「1on1をもっとやろう」といった声がよく聞かれますが、本当に必要なのは“対話の量”ではなく“対話の中身”です。
話すべき材料がなければ、せっかくの対話も当たり障りのないやり取りで終わってしまいます。
弊社が支援する現場でも、「1on1はやっているが形骸化している」という声は少なくありません。材料がないと、深い対話にはつながらないのです。
“材料がない”とは、状態が見えていないこと。
ラフールでは、対話の量ではなく「材料」の有無が鍵だと考えています。状態を可視化できなければ、せっかく時間を取っても本質的な話ができず、すれ違いや遠慮が残ってしまいます。サーベイを通じて「今、どこにズレや不安があるか」を明らかにすれば、初めて実のある対話が可能になります。
互いの価値観や状態、関係性についての「共通認識」がないまま話しても、すれ違いが起きやすく、深い話に踏み込めません。
だからこそ、サーベイやデータをもとに「今、何が課題なのか」「何がズレの原因なのか」を見える化することで、初めて実のある対話が始まるのです。
たとえば、
「このチームは“成果重視”の傾向が強い分、失敗を共有しづらくなっている」
「この人は“評価されたい”という価値観が強く、自分自身で抱え込んで不安になりやすい」
などの情報があるだけで、関係性に配慮した対話がしやすくなり、遠慮や誤解の回避につながります。
データによって状態を「可視化」することは、対話を促すための共通言語を持つこととも言えるでしょう。
心理的安全性の改善には、「見る」「話す」「続ける」の循環が必要
ここまでサーベイで状態を可視化することで、コミュニケーションという起点から心理的安全性を高めていく方法についてお話しましたが、一度試してみて終わりでは本質的改善にはつながりません。
大切なのは、「見る → 話す →続ける」という循環を意識して運用することです。
- 見る:サーベイで状態を把握し、組織や個人の変化を客観的にとらえる
- 話す:可視化した結果を材料に、必要な対話を行い、理解を深める
- 続ける:施策を実行し、変化をモニタリングしていく
ラフールが重視しているのは、「やって終わり」ではなく、改善の循環をつくることです。
実際に、サーベイ→施策→変化のモニタリングを繰り返すことで、現場に納得感と変化の実感が生まれていくプロセスを多く見てきました。
心理的安全性は一朝一夕に築けるものではありません。
だからこそ、状態を可視化しながら小さな変化を積み重ねていくことが、最も確実な改善アプローチだといえるのです。
組織づくりに、主観と客観の両輪を
ここまで、心理的安全性をふわっとした「雰囲気」ではなく、「相互理解」と「状態の可視化」という観点から捉え直す視点をご紹介してきました。
心理的安全性は、人と人との関係性が土台となる以上、どうしても主観的な感覚が伴います。
「自分の主観では大丈夫だと思っていても、相手はそうではないかもしれない」
とはいえ、客観的判断だけでは相手とのコミュニケーションが成り立ちませんし、主観で相手の変化に気づくことも重要です。
主観は“気づき”、客観は“裏づけ”です。
メンバーの表情や発言から感じ取る主観的な違和感を、データという客観的視点で補強することで、はじめて的確なアクションにつなげることができます。
「なんとなく大丈夫そう」ではなく、「何が・どこに・どのように課題としてあるのか」が見える状態。この両輪が、再現性のある組織改善を支えていきます。
ラフールは、組織づくりには「主観」と「客観」の両方が必要だと考えています。
この両輪を意識して組織を見つめていくことで、「なんとなく大丈夫そう」ではなく、「実際に、どこに課題があって、どう変わっているのか」が見える状態をつくることができ、再現性のある改善が可能になってきます。
心理的安全性は、“なんとなく”では保たれません。
見えていないことを、見えるようにする。
話せなかったことを、話せるようにする。
その積み重ねこそが、組織の信頼と成果につながっていくのです。
心理的安全性を“状態”として捉え、組織の対話を進めたいと感じた方へ
ラフールサーベイは、
- 個人の状態や価値観
- 組織全体の傾向やストレス要因
- 上司・部下間の関係性や信頼度
などを多角的に可視化することで、職場の“見えにくいズレ”を明らかにし、対話と改善のきっかけを生み出すツールです。
「心理的安全性が気になっているけれど、何から始めたらいいかわからない」
「雰囲気は悪くないのに、本音が出てこない」
そんなモヤモヤを感じている方にとって、まず“状態を見える化”することは、最初の一歩になります。
心理的安全性は、単なる「空気」ではなく、捉え方ひとつで大きく改善できる“状態”です。
ラフールでは、現場に即した可視化と対話の支援を通じて、組織づくりに伴走しています。
ぜひ一度、貴社の現状を「状態」として見直してみてください。
まずは資料をご覧いただき、「空気」ではなく「状態」で組織を捉えるヒントを見つけてみてください。