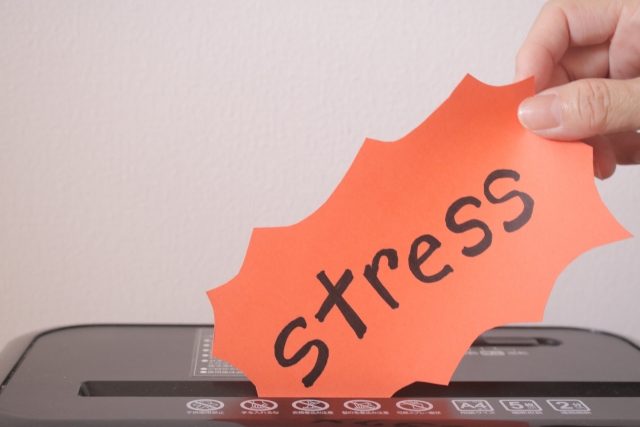仕事のプレッシャーや人間関係の悩み、社会全体の変化に適応する中で、多くの人がストレスを感じています。しかし、ストレスに対して適切に対応する力「ストレス耐性」を身につけることで、精神的な負担を軽減し、より健康的で前向きに働くことが可能になります。
本記事では、ストレス耐性の基本的な概念から、ストレスに強い人の特徴、ストレス耐性を高める実践的な方法、そして企業が従業員のストレス耐性を向上させるための施策について詳しく解説します。ストレスに強くなりたい方や、社員のメンタルヘルス向上を目指す人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
ストレス耐性とは
ストレス耐性の定義
ストレス耐性とは、精神的な負荷に適応し、心身のバランスを保つ力のことを指します。仕事や人間関係、日常生活においてストレスを感じる場面は避けられませんが、ストレス耐性が高い人は、適切に対処しながら心の健康を維持することができます。
ストレス耐性が求められる理由
現代社会では、さまざまな場面でストレス耐性が求められます。
- 仕事のプレッシャー(納期や業績目標などのストレス)
- 人間関係の調整(上司・同僚・取引先との関係性)
- 環境の変化(転職や異動、新しい業務への適応)
ストレス耐性が高いと、困難な状況に直面しても柔軟に対応でき、精神的なダメージを受けにくくなります。
ストレス耐性が低いとどうなる?
ストレス耐性が低い場合、以下のようなリスクが高まります。
- 仕事のプレッシャーを受け流せず、精神的に疲弊しやすい
- 人間関係のトラブルで過度に落ち込みやすい
- 小さなミスや失敗を過大に受け止め、自信を失う
これらの傾向が強いと、仕事の生産性が低下し、最悪の場合、離職やメンタルヘルスの不調につながってしまうこともあります。
ストレス耐性にかかわる6つの要素
ストレス耐性は、下記の6つで決まると言われています。
- 容量
- 処理
- 感知
- 経験
- 回避
- 転換
それぞれ、ストレスの感じ方や対処方法に影響します。
容量
ストレスを溜められる程度を表します。大きさによってストレス反応、ストレスが原因で引き起こされる心身への影響の出やすさが変わります。 容量が大きいと、ストレスを感じてもすぐには不調になるとは限りません。小さいと、ネガティブな感情や持病によらない身体の不調などが起きやすくなります。
処理
ストレスの原因となる出来事に対処する能力です。力は、ストレスを感じにくくするための対応ができるか、原因をなくせるかなどで変わります。 たとえば、残業の多さがストレスの場合。残業時間を短くしたり残業したりしなくても成果を出し続けるために、業務の進め方や時間配分を見直せるなどは、処理能力があると言えます。
感知
ストレスになり得ることに気付くことを意味します。 感知する力が高い、つまり、相手の態度や環境の変化などを感じ取りやすい人ほどストレス耐性は弱く、感じ取りにくい、良い意味で周囲に無関心な人ほどストレスには強いと言えます。
経験
これまでどのようなストレスをどれくらい受けてきたか、ストレスを感じた時どのように対処したかなどを指します。似た体験をするほど、ストレスに強くなるのが一般的です。 たとえば、就職・転職活動中の面接などの場で、最初はうまく行かず「どうしてスムーズに話せないのか」「どこも決まらないかも」と不安でも、回数を重ねると慣れてきて、次の面接に向けて対策をとれるようになった方は多いのではないでしょうか。 ただし、考え方のクセによっては、同じような経験を繰り返して耐性が低くなることもあります。
先の面接で例では、うまくできなかった原因を分析し、次に活かそうと考えられる人は、ストレスに強くなる経験を積める人です。「何回やっても上達しないから成功するはずがない」と考えてしまう人は、経験で耐性が弱くなりやすいタイプと言えます。
回避
ストレスになり得ることを深刻にとらえず、流せることです。物事の割り切りが得意な人は回避能力が高く、完璧主義や几帳面過ぎる人は低い傾向にあります。 また心身が健康だと、能力が高いとも言われています。自律神経系、内分泌系などと回避能力は関連があると考えられているためです。
たとえば、苦手な人とチームを組むことになった時。回避能力の高い人は、「苦手な人がいない人なんてあり得ない」と考え、業務に支障のない最低限の接し方ができるでしょう。一方、回避能力の低い人は、何とか仲良くなろうと頑張り過ぎて、ストレスが蓄積されるかもしれません。
転換
ストレスにつながる出来事をポジティブに捉えられることです。 転換が上手だと、仕事量が多いと感じた時、「残業しないと終わらなそうで嫌」「疲れた」と感じる前に、「仕事の進め方や時間の使い方を見直すきっかけになった」「この仕事をこなせたら、難しいことも乗り越える力がつくだろう」などと考えることができます。
ストレス耐性が低い人と高い人の特徴
ストレス耐性が低い人の特徴
几帳面、完璧主義
ストレス耐性が低い人の多くは、細かいことにこだわりすぎる傾向 があります。完璧な成果を求めるあまり、仕事に時間をかけすぎたり、ちょっとしたミスを極端に恐れたりすることがあります。その結果、常に緊張状態が続き、ストレスが蓄積しやすくなります。【具体的な行動例】
- 何度も書類を見直し、小さなミスを見つけるたびに修正を繰り返す
- 納期ギリギリまで細部を調整し、提出が遅れることがある
- 自分の理想通りに物事が進まないと、強いストレスを感じる
→ 対策 :「80%の完成度でもOK」と考えることで、完璧主義を和らげる習慣をつける
真面目、責任感が強い
責任感が強いのは良いことですが、過剰に責任を背負い込むとストレス耐性が低下 する原因になります。他人の仕事まで引き受けたり、「自分がやらなければ」と考えすぎたりすると、精神的に疲弊してしまいます。
【具体的な行動例】
- 仕事を頼まれると断れず、キャパシティを超えてしまう
- 些細なミスでも「自分のせいだ」と過度に自責の念を抱く
- 上司や同僚の期待に応えようと無理をする
→ 対策:責任の範囲を明確にし、「自分がやるべきこと」と「他人に任せること」を区別 する
協調性が過度に強い
ストレス耐性が低い人は、周囲の人間関係を気にしすぎる傾向があります。相手の気分を害さないように自分の意見を押し殺したり、必要以上に相手の期待に応えようとすることで、精神的に疲れてしまいます。
【具体的な行動例】
- 「NO」と言えずに無理なお願いを引き受けてしまう
- 他人の目を気にしすぎて、自分の意見を言えない
- 人と対立するのを避けるために、無理に同調してしまう
→ 対策:「他人の評価ではなく、自分の価値基準を持つ」ことで、過度な気遣いを減らす
ストレス耐性が高い人の特徴
感情のコントロールが上手い
ストレス耐性が高い人は、怒りや不安を適切に処理し、冷静に対応できる のが特徴です。感情的になるのではなく、理性的に物事を判断し、ストレスに影響されにくい思考パターンを持っています。
【具体的な行動例】
- トラブルが発生しても、冷静に状況を整理する
- 感情的にならず、論理的に解決策を考える
- イライラしたときは、一度深呼吸をして気持ちを落ち着ける
ポジティブ思考ができる
ストレス耐性が高い人は、逆境を前向きに捉える力 があります。ストレスの原因となる出来事を「成長の機会」として捉え、落ち込みすぎずに行動を切り替えることができます。
【具体的な行動例】
- 失敗しても「この経験を活かせば次は成功できる」と考える
- 仕事がうまくいかなくても、「学びのチャンス」と捉えて前向きに対処する
- ネガティブな出来事をすぐに忘れ、気持ちを切り替えられる
物事を客観的に捉えられる
ストレス耐性が高い人は、出来事に対して冷静に分析し、適切な行動を取る力 を持っています。主観的に悩みすぎるのではなく、第三者の視点で状況を把握し、適切な対応を選択できます。
【具体的な行動例】
- 感情に流されず、事実を整理して判断する
- 他人の意見を聞きながらも、自分の考えをしっかり持つ
- ノートに書き出して整理するなどして過去の失敗を客観的に分析し、同じミスを繰り返さないよう対策を立てる
生活習慣が整っている
ストレス耐性が高い人は、心身の健康を維持する習慣 を持っています。食事・睡眠・運動などの生活習慣を整えることで、ストレスに対する耐性が向上し、心が安定しやすくなります。
【具体的な行動例】
- 毎日決まった時間に寝て、規則正しい生活をする
- 適度な運動を取り入れ、ストレスを発散する
- バランスの取れた食事を意識し、体調を整える
相談できる人間関係を持っている
ストレス耐性が高い人は、一人で悩まずに他者と協力しながら問題を解決する力 を持っています。適切な人に相談し、サポートを得ることで、精神的な負担を軽減できます。「困ったら誰に相談するか?」をあらかじめ決めておく ことで、孤立を防ぐことにつながるでしょう。
【具体的な行動例】
- ストレスを感じたら、信頼できる人に話して気持ちを整理する
- 職場の上司や同僚と良好な関係を築き、協力しながら仕事を進める
- 家族や友人と定期的に交流し、精神的な支えを持つ
ストレス耐性を高める実践的な方法

ストレス耐性は、生まれ持った性格や気質だけでなく、後天的に鍛えることができるスキル です。日々の習慣や考え方を意識的に変えていくことで、ストレスに強くなり、仕事や人間関係においても前向きに対応できるようになります。
1. 自分の気持ちや状況を言語化する習慣を持つ
ストレスを感じたとき、自分の気持ちを整理することが重要 です。ストレス耐性が低い人は、漠然とした不安や焦りを抱え込みがちですが、言語化することで「何がストレスの原因なのか」「どのように対処すればよいか」を客観的に考えられるようになります。客観的に自分の置かれた状況を捉えられれば、具体的な対策方法も考えられるようになるでしょう。
毎日5分、日記をつける
- その日の出来事と感情を記録する
- 習慣化することで、ストレスのパターンを把握し、適切な対応ができるようになる
信頼できる人に話す
- 言葉にするだけでも気持ちが整理され、ストレスが軽減される
- 一人で抱え込まず、他者の視点を取り入れることで、問題解決のヒントを得られる
2. 自分に合ったストレス解消法を見つける
ストレスは完全になくすことはできませんが、適切に発散することで心身の健康を保つことができます。ストレス耐性が高い人は、自分に合ったストレス解消法を持ち、定期的にリフレッシュする習慣を身につけています。
運動をする(ウォーキング・ランニング・ヨガなど)
- 軽い有酸素運動によってセロトニンの分泌が活性化され、ストレスが軽減される
瞑想や深呼吸を取り入れる
- マインドフルネス瞑想を行うことで、ストレスを客観視し、冷静に対処できるようになる
- 短い時間であっても深呼吸をすることにより、リラックス効果が得られる
趣味やリラックスできる時間を確保する
- 好きなことに没頭することで、ストレスから一時的に離れることができる
- 音楽鑑賞、読書、映画鑑賞、アロマテラピーなど、自分に合った方法を見つける
自然と触れ合う
- 緑の多い公園を散歩をするなどして自然と接触することにより、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を抑えられる
3. 「他人は他人、自分は自分」と割り切る
職場では、他人と比較したり、周囲の期待に応えようとしすぎることでストレスを感じることが多い です。しかし、ストレス耐性が高い人は、「自分は自分、人は人」 と考え、必要以上に振り回されないようにしています。
SNSや他人の成功話を必要以上に気にしない
- SNSで他人の成功や楽しそうな生活を見て、「自分はダメだ」と落ち込むのはNG
- 「人それぞれのペースがある」と割り切ることが大切
「できること」と「できないこと」を明確にする
- すべてのことを完璧にこなそうとせず、自分の得意な部分に集中する
- 「自分はプレゼンが苦手だが、データ分析は得意」といったように、強みを活かす考え方を持つ
職場の人間関係を必要以上に深く考えない
- すべての人と完璧な関係を築く必要はない
- 「仕事上の付き合いは必要だが、それ以上は深入りしすぎない」と考える
企業が従業員のストレス耐性を高めるための施策
1. 適切な労務管理の徹底
ストレス耐性が高い人でも、過度な労働環境では心身に負担がかかり、ストレスが蓄積されていきます。そのため、企業は労働時間の管理を適切に行い、従業員が無理なく働ける環境を整える 必要があります。
残業の上限を設け、労働時間の管理を徹底する
- 勤怠管理システムを導入し、従業員の労働時間をリアルタイムで可視化
- 必要に応じてノー残業デーを設ける
有給休暇の取得を促進する
- 有給取得率の低い社員に対して積極的に取得を促す
- 組織全体で休みを取りやすい雰囲気を作る
柔軟な勤務体系の導入
- テレワークやフレックスタイム制を導入し、従業員が働きやすい環境を整備
- 特に育児や介護と両立する従業員には、柔軟な勤務形態を選択できるようにする
2. ストレスチェックとフォローアップの実施
厚生労働省が義務化している「ストレスチェック制度」を活用し、従業員のストレス状況を定期的に把握する ことが重要です。単なる診断に留まらず、その結果をもとに具体的な改善策を実施することが企業の責務となります。
ストレスチェックの結果を個人と組織の両方で活用する
- 個人にはフィードバックを行い、必要に応じてカウンセリングを実施
- 組織全体の傾向を分析し、ストレスが高い職場環境の改善策を検討
ストレスの高い従業員へのフォロー体制を整備
- 産業医や専門カウンセラーとの面談を設け、心理的なケアを実施
- 社内相談窓口を設け、いつでも悩みを相談できる環境を整える
メンタルヘルス研修の実施
- ストレス管理の知識を身につけるための社内研修を行う
- 管理職向けの「部下のストレスケア」研修を実施し、職場全体のストレスマネジメントを強化
3. レジリエンストレーニングの導入
レジリエンスとは、「困難や逆境を乗り越える力」のことを指します。ストレス耐性を高めるには、ストレスを避けるのではなく、ストレスに適応し、乗り越えるスキルを身につけることが重要 です。そのために、レジリエンストレーニングの導入が効果的です。
セルフマネジメントトレーニング
- ストレスがかかった際の適切な対処法を学ぶ研修を実施
- 例:「ポジティブ思考のトレーニング」「感情のコントロール方法の習得」
マインドフルネス研修
- 瞑想や呼吸法を活用し、心を落ち着ける習慣を身につける
- ストレスに直面した際に、冷静に対処できる力を育む
チームビルディング活動の実施
- ストレスに強い組織を作るため、チームワークを強化する研修を実施
- 「コミュニケーション力向上ワーク」「リーダーシップ研修」などを実施
4. 社内コミュニケーションの促進
職場におけるストレス発生の要因として、対人関係は大きな位置を占めています。企業は、人間関係の不和によるストレスの発生を抑制するため、チームや組織内においてそれぞれがお互いの理解を深められるような機会を設けると良いでしょう。さらに心理的安全性の高い職場環境を作ることで、ストレス耐性を強化する ことが可能です。
1on1ミーティングの実施
- 上司と部下の定期的な対話の場を設け、悩みを相談しやすい環境を整える
- フィードバックを適切に行い、従業員の成長をサポート
社内イベントや交流会の開催
- 部署を超えた交流を促し、ストレスの発散につなげる
- 例:ランチミーティング、社員旅行、スポーツイベント
メンター制度の導入
- 新入社員や異動したばかりの社員が気軽に相談できる環境を作る
5. 柔軟な働き方の導入と推進
ストレス耐性を高めるためには、従業員が自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を選べるようにする ことが重要です。
テレワーク・フレックスタイムの導入
- 通勤や労働時間の負担を軽減し、ワークライフバランスを向上させる
副業・兼業の許可
- 新しい経験を積むことで、ストレスに対する柔軟な対応力を身につける
育児・介護支援制度の充実
- 育児休暇や介護休暇の取得を推奨し、仕事と家庭の両立をサポート
6. 健康増進プログラムの提供と推進
ストレス耐性は、身体的な健康とも密接に関係 しています。企業が従業員の健康維持をサポートすることで、ストレス耐性の向上につながります。
フィットネスや健康プログラムの導入
- 社内ジムの設置、スポーツクラブの補助金制度の提供
- 定期的な健康診断の実施
栄養バランスの取れた食事の提供
- 社員食堂でヘルシーメニューを提供する
メンタルヘルス支援プログラムの実施
- カウンセリングサービスの提供
- ストレス軽減のためのワークショップを開催
ミライ適性検査「テキカク」で組織と人材のミスマッチを防ぐ
働くうえで、組織と人材のミスマッチは従業員のストレス要因になります。
そこでミライ適性検査「テキカク」なら候補者が自社の目指す組織の今や未来において貢献できる人材かどうかを示し、組織と人材のミスマッチを防ぎます。組織改善ツール「ラフールサーベイ」で蓄積されたサーベイデータと、心理学×データ×AIで導かれた分析による裏付けにより企業と採用候補者のマッチ度を算出することができるのです。
採用段階から早期離職を防止し、自社にマッチした人材に長く活躍してもらいたい!という人事担当者や経営者の方は、ミライ適性検査「テキカク」を詳しくご覧ください。

まとめ
ストレス耐性は、個人の努力で向上させることができ、企業としても 環境整備や教育を通じて社員のストレス対処力を強化する ことが可能です。適性検査を活用しながら、従業員一人ひとりのストレス耐性を把握し、組織全体のメンタルヘルス向上を目指しましょう。