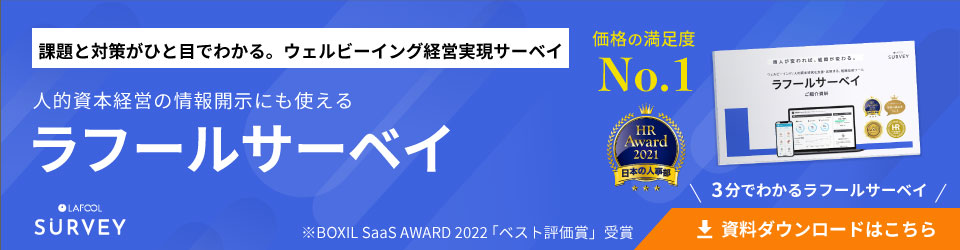近年、企業活動において「サーベイ(Survey)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。特に人事領域では、従業員のエンゲージメントや職場環境の改善に向けた手段として、定期的なサーベイの活用が定着しつつあります。
本記事では、「サーベイとは何か」から始まり、種類ごとの特徴、活用メリット、実施の流れ、効果的な活用方法までを体系的に解説します。
サーベイとは
サーベイ(survey)とは、「特定のテーマに対する意識・実態・状況などを把握するための調査」を指します。ビジネス領域では、あらかじめ設計された質問項目に基づいて対象者に回答を求め、その結果をもとに現状の把握や課題の発見、改善アクションの検討に活用するのが一般的です。
特に人事領域におけるサーベイは、従業員の意識や感情、行動傾向など、組織の見えにくい課題を数値で可視化し、改善施策の立案・検証につなげるための出発点として活用するケースが増えています。
単なる情報収集ではなく、組織の状態をとらえ、改善につなげるためのツールとして継続的に活用する企業も少なくありません。
サーベイとリサーチやアンケートとの違い
サーベイは「調査の一形態」ではありますが、リサーチやアンケートとはニュアンスが異なります。以下のように整理すると違いが明確になります。
| 項目 | サーベイ | リサーチ | アンケート |
|---|---|---|---|
| 目的 | 組織や個人の状態を把握し、課題を可視化・改善に活かす | 特定テーマに関する情報収集や仮説の検証 | 意識・満足度などを簡易的に把握すること |
| 対象 | 従業員・チーム・組織(主に人事領域) | 社会全般・顧客・市場・文献など幅広い対象 | 特定の属性・タイミングに限った集団が多い |
| 特徴 | 目的に応じた設計・継続的運用・改善施策とセットで活用 | 幅広い調査方法・自由度が高く、分析や考察が前提 | 選択式の設問が中心、短時間で完了、単発実施が主流 |
| 調査方法 | 設計された質問項目への回答(定量+定性)をベースに数値化・分析 | インタビュー・文献調査・フィールド調査など多様な手法 | 選択肢ベースの回答をオンラインや紙で収集するのが一般的 |
サーベイは、一般的なアンケートよりも「設計の工夫」や「継続性」、「改善への接続」が求められる点で、より戦略的・実務的な意味合いを持ちます。人事施策の一環として実施する場合には、単なる満足度調査ではなく、組織改善の起点としての設計が必要になります。
サーベイが活用される領域
サーベイはさまざまな分野で活用されています。代表的な領域は以下の通りです。
- 人事領域:従業員の満足度、エンゲージメント、ストレス状況の把握
- マーケティング領域:顧客満足度調査、市場ニーズの把握
- 行政・公共領域:住民意識調査、政策評価のためのデータ収集
- 教育領域:生徒・学生の意識調査、教育改善に向けたフィードバック収集
ここからは、この中でも特に人事領域におけるサーベイの活用に焦点を当て、具体的な種類や導入メリット、運用手順などを詳しく解説していきます。
人事領域で活用されるサーベイの種類と特徴
企業が組織改善や人材マネジメントを行ううえで、サーベイは欠かせないツールとなっています。ただし、目的や状況によって、活用すべきサーベイの種類は変わってきます。
ここでは、人事領域において代表的なサーベイを以下の6種類取り上げ、それぞれの概要と目的、特徴について整理します。
- 従業員サーベイ
- エンゲージメントサーベイ
- モラールサーベイ
- アセスメントサーベイ
- コンプライアンス意識調査
- ストレスチェック
従業員サーベイ
従業員サーベイは、職場環境や働きやすさ、職務満足度など、従業員の意識や状態を把握するための調査で、部署ごとのマネジメント課題や職場環境の実態を明らかにしたいときに有効です。
従業員サーベイは大きく分けて以下の2種類に分類されます。
- センサスサーベイ(全社調査):半年に1回、年1回などの低頻度で、全社規模で網羅的に実施されるサーベイ。組織全体の課題を包括的に把握できるのが特長。
- パルスサーベイ(短期定点調査):月1回や週1回などの高頻度で実施される簡易なサーベイ。変化の兆しや緊急課題の早期発見に適している。
両者を組み合わせることで、広く深くタイムリーに組織状態を把握することが可能になります。
従業員サーベイは、測る対象や目的によって名称や設計が異なります。エンゲージメントやモラールなど、それぞれの視点に特化したサーベイも、広い意味では従業員サーベイに含まれることが多いです。
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、従業員の「組織への貢献意欲」や「仕事への熱意」といった心理的な結びつきを定量化するサーベイです。
たとえば、離職率の高い組織で原因を探りたい場合や、エンゲージメント向上施策の効果を測定したいときに活用されます。
エンゲージメントの高さは離職率や生産性、顧客満足度とも関係が深いとされ、人事戦略のKPIとして設定する企業も増えています。設問は、組織への信頼感、上司との関係、成長機会など複数の観点から構成されることが一般的です。
モラールサーベイ
モラール(Morale)とは「士気」や「モチベーション」を意味し、モラールサーベイでは従業員の感情面・精神面の状態を測定します。
職場の雰囲気や日常的な満足度、ストレス要因を把握したい場面に適しています。
エンゲージメントサーベイと重なる部分もありますが、モラールサーベイはより日常的な満足感やストレス、不満の要因を探る傾向があり、「現場の空気感」に近い情報を得ることができます。たとえば、組織に変化があったときに従業員がどう感じているか、職場文化が健全に保たれているかなどを確認するのに適しています。
アセスメントサーベイ
アセスメントサーベイは、従業員のスキル・能力・行動特性などを測定し、人材の評価や配置・育成に活用するサーベイです。リーダー候補の選抜や、職種適性の見極めなど、個人の育成・評価に特化しています。360度評価や性格診断、リーダーシップ資質の診断なども含まれます。
採用や昇進、リーダー育成といった人事判断に客観性を持たせたいときに導入されるケースが増えており、最近では人材マネジメントの一環として取り入れる企業も多くなっています。
コンプライアンス意識調査
コンプライアンス意識調査は、従業員のコンプライアンス意識や倫理観を測定するためのサーベイです。企業統治(コーポレートガバナンス)や内部統制強化の一環として、定期的に実施するケースが増えています。
設問は、法令遵守に関する理解度、内部通報制度の認知、企業のガバナンスに対する信頼などを確認する設問で構成され、不祥事の予防や、安心して働ける職場づくりに向けた土台づくりに活用されます。
経営層や監査部門と連携しながら取り組まれることが多く、組織としての姿勢が問われる領域でもあります。
ストレスチェック
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づいて実施が義務付けられている、法定サーベイです。
従業員の心理的なストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調の早期発見や、職場環境の改善に活用されます。
ストレスチェックは、主に以下の3つの視点から質問されます。
- ストレス要因(仕事内容、人間関係など)
- ストレス反応(眠れない、気分が落ち込む等)
- 周囲のサポート(上司・同僚・家族など)
回答結果をもとに集団分析を行うことでよって組織単位でのリスク傾向も把握することも可能です。労働環境改善のための一次データとして、継続的に活用されるケースも増えています。
サーベイを導入するメリット
サーベイの導入は単なる「社員の声を集める取り組み」ではありません。経営や人事の意思決定を支え、組織の前進を後押しする有効な手段です。
ここでは、企業がサーベイを導入することで得られる、主な5つのメリットをご紹介します。
組織課題が可視化できる
サーベイの最大のメリットは、表面化しづらい組織課題を「数値」として把握できる点にあります。
たとえば、エンゲージメントが低下している部署、マネジメントに不満が集中しているチームなどを特定できれば、感覚や経験に頼らず、適切に対策を講じることが可能です。
数値化されたデータは、経営層や関係部署との共通認識を形成するうえでも役立ちます。「なんとなく」の属人的な判断から脱却し、組織をより戦略的に改善していくための土台となります。
離職の予防につながる
定期的なサーベイにより、従業員の不安や不満の兆候を早期にキャッチすることができます。
離職につながる要因(上司との関係、将来への不安、業務量の負荷など)を把握し、個別フォローや組織としての対応につなげることができます。
とくにパルスサーベイのように高頻度でおこなうサーベイでは、変化のスピードに対応した柔軟な人事施策を打つことができます。
組織文化の浸透度を測れる
企業理念やバリュー、ビジョンの浸透度を測る指標としても、サーベイは有効です。
たとえば「会社の方針に共感しているか」「行動指針が現場で体現されているか」といった設問を通じて、理念の伝わり方や受け止め方のギャップを可視化できます。
組織文化の醸成は時間のかかる取り組みですが、サーベイの結果をもとにPDCAを回すことで、意図をもって育てていくことが可能です。
人間関係やハラスメントのトラブルを察知できる
サーベイは、表面化しにくい人間関係の問題や職場の不健全な雰囲気の兆候を把握する手段としても活用できます。
匿名性を確保した設計にすることで、従業員が本音を伝えやすくなり、「職場に相談できる相手がいない」「上司からのプレッシャーが強すぎる」といった、ハラスメントにつながる可能性のあるリスクも早期に見つけることができます。
人事施策にデータを活用できる
感覚や過去の経験則に依存しがちな人事施策も、サーベイを通じて得たデータによって「根拠ある改善」が可能になります。
たとえば以下のような場面で、サーベイデータは意思決定の材料となります。
- 配属や異動の判断
- 育成施策の効果測定
- 管理職の評価
- 働き方改革の成果検証 など
このように、サーベイで得た数値データは、異動・育成・評価といった人事施策において、判断の根拠として活用することができます。属人的な判断に頼るのではなく、データに基づいた意思決定へとシフトすることで、より納得感のある人事運営が可能になります。
サーベイを導入する際の注意点・デメリット
サーベイは組織改善に有効な手段である一方で、設計や運用を誤ると期待した効果を得られないどころか、従業員の信頼を損ねるリスクもあります。ここでは、導入前に把握しておくべき代表的な注意点・デメリットを解説します。
従業員の負担が増える可能性がある
サーベイは基本的に全従業員を対象に実施されるため、設問数が多かったり、頻繁に行われると従業員の負担が増えます。
特に業務時間外での回答を求められる場合や、回答に時間がかかると感じられると、不満やストレスの原因になりかねません。結果として回答率が低下したり、質の低い回答が増えてしまうリスクがあります。
改善につながらないと不満が生まれる
サーベイを実施しても、結果を活かした改善が見られない場合、従業員の間で「形だけの調査」「声を聞いてもらえない」といった不満が蓄積します。
これにより、次回以降の回答意欲が下がるだけでなく、組織全体のエンゲージメント低下を招く可能性もあるため、結果の活用とフィードバックは欠かせません。
形骸化を防ぐ運用が求められる
サーベイは一度実施して終わりではなく、継続的な運用が求められます。しかし、運用体制が属人的になったり、目的が曖昧なまま繰り返されると、サーベイが形骸化してしまいます。
形骸化は「回答しても何も変わらない」という空気が生まれ、従業員の協力を得にくくするだけでなく、経営層にとっても貴重なデータ源が失うリスクにもつながります。
サーベイ実施の流れ
サーベイを効果的に活用するためには、明確な手順に沿って計画的に実施することが重要です。ここでは、一般的なサーベイ実施の流れを6つのステップに分けて解説します。
(1)実施目的の明確化
まず最初に、サーベイを実施する目的を具体的に定めます。
例えば、「従業員のエンゲージメント向上」「離職リスクの把握」「ハラスメントの早期発見」など、狙いによって設問設計や対象者、実施頻度が変わるため、この段階で関係者の間で目的を共有し、足並みをそろえておくことがポイントです。
(2)ツールの選定・設問設計
次に、目的に合ったサーベイツールの選定と、調査項目(設問)の設計を行います。
設問は回答者の負担を考慮しつつ、目的達成に必要なデータが得られるようバランスよく設計することが重要です。
また、匿名性の確保や回答のしやすさなど、ツール側の仕様もあわせて確認しておきましょう。
(3)社内への説明・周知
従業員に対して、サーベイの目的や回答方法、回答期間、匿名性の確保などを丁寧に説明します。
事前に十分な情報提供を行うことで、回答率の向上だけでなく、サーベイ結果の信頼性にもつながります。
(4)サーベイ実施と回収
計画に沿ってサーベイを実施します。回答期間中はリマインドを行うなどして、できるだけ多くの従業員から回答を得られるよう促します。
期間終了後は、回収状況を確認し、必要に応じて追加対応を行います。
(5)集計・分析・フィードバック
回答を集計し、設計段階で定めた指標に基づいて分析を行います。
分析結果はグラフや表などで分かりやすく視覚化し、まずは社内の関係者にフィードバックします。
あわせて、従業員にも分析内容の一部を共有することで、「声がきちんと届いている」と実感してもらいやすくなります。こうした透明性のある情報共有は、従業員の信頼を得るうえで欠かせません。
(6)改善アクションの実施
最後に、分析結果を踏まえて具体的な改善策を立案・実施します。
経営層・管理職・現場担当が連携しながら改善に取り組み、必要に応じて進捗をフォローしていくことが大切です。
こうした取り組みを積み重ねることで、次回以降のサーベイにも前向きな変化が表れ、組織の改善サイクルを着実に回していくことができます。
サーベイを効果的に活用するポイント
サーベイを導入するだけでは組織改善にはつながりません。回答率を高め、正確なデータを収集し、結果を組織の課題解決に活かしていくには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、効果的に活用するための具体的なポイントを紹介します。
事前に従業員に十分な説明を行う
サーベイ実施前に従業員へ目的や意図を丁寧に伝え、納得感を持ってもらうことが大切です。
説明内容としては、以下の点を含めるとよいでしょう。
- サーベイの目的と期待される効果
- 回答にかかる負担(設問数や回答期間など)
- 匿名性の担保や個人が特定されない集計方法
- 結果の共有方法と改善に向けた取り組みの約束
こうした説明があることで、従業員の不安や疑問を解消し、率直な回答を引き出しやすくなります。
回答のしやすさと集計精度を両立した設計にする
サーベイの設問設計やツール選定は、回答のしやすさと集計精度のバランスが重要です。負担感が大きいと回答率が下がり、結果の信頼性も低下しかねません。
- 設問数と所要時間の適切な設定
- モバイルやPCなど、デバイスへの対応
- 回答期間の設定とリマインド機能
上記のような点を考慮し、従業員がストレスなく答えられる環境を整えましょう。
結果を共有し、改善アクションにつなげる
集計・分析した結果は速やかに関係者や従業員に共有することが重要です。
- 重点課題とその背景をわかりやすく説明する
- 小規模でも具体的な改善策を提示し、実行に移す
- 改善の進捗や効果を継続的に報告する
これにより、従業員は自分たちの声が組織に反映されていると実感し、次回以降のサーベイ参加意欲も高まります。
継続的に活用できる仕組みにする
サーベイは一度きりの取り組みではなく、継続的な組織改善のツールとして運用することが重要です。継続的に活用するためには、以下のような体制づくりがかかせません。
- 実施頻度を計画的に設定し、定点観測できるようにする
- 運用フローを標準化し、属人化を防ぐ
- 経営層や管理職の協力体制を強化する
このように仕組み化することで、組織の健康状態を長期的に把握し、タイムリーな対応が可能となります。
ラフールサーベイで組織改善がすすむ理由
ラフールサーベイは、サーベイ結果から「なぜそうなったのか」までを可視化し、具体的な改善アクションにつなげることができる組織改善ツールです。ここでは、ラフールサーベイが本質的な組織改善につながる3つの理由をご紹介します。
多面的な設問で組織と個人の状態をまるっと調査
ラフールサーベイは、ストレスチェックや満足度調査だけでは把握しきれない組織と個人の状態を、網羅的に調査できる設計となっています。
組織に関する設問では、エンゲージメントスコアに加えて、仕事へのやりがいや職場の人間関係、eNPS、離職・ハラスメントリスクなど、多面的な項目で組織の状態を分析します。
個人に関する設問では、メンタル・フィジカルスコアやストレス状態に加えて、睡眠に関するデータも把握でき、従業員のコンディションチェックや健康管理に役立ちます。
こうした多角的な設問設計によって、組織課題の全体像を精度高く把握し、適切な改善アクションの出発点を明確にすることが可能になります。
「なぜこの結果になったのか」を構造的に読み解ける
ラフールサーベイは、こうした「なぜこの結果になったのか」という問いをあきらかにするために、スコアの背景にある要因を構造的に読み解くための仕組みを備えています。
たとえば、エンゲージメントの低下が見られた際に、「上司との関係性」「仕事のやりがい」「個人のストレス状態」など、関連する観点を横断的に確認することで、表面的な結果にとどまらず、その背後にある原因に近づくことが可能です。
こうした分析を通じて、サーベイをやりっぱなしにせず、具体的な改善アクションにつなげるための土台として活用できます。
部署・属性別に分解し、構造的な課題を特定できる
設問ごとの結果を関連づけて横断的に確認できるだけでなく、回答結果を部署や職種などの単位で集計・分析することも可能です。
たとえば「上司との関係性に課題がある」というスコアが出たときも、特定の層や部署に集中しているかを確認することで、改善の優先順位やアプローチを検討しやすくなります。
このように、数値の背景にある構造的な要因を分析する視点を取り入れることで、サーベイの結果をそのまま終わらせず、改善施策の優先順位づけや現場との対話のきっかけとして活用できます。
まとめ
サーベイは、組織の現状や課題を数値で把握し、意思決定や改善施策に活かすための基盤となります。離職防止やエンゲージメント向上、職場環境の整備など、さまざまな人事施策の出発点として活用できます。
とはいえ、ただ実施するだけでは十分な効果は得られません。目的に合った設計と、結果をもとにした継続的な運用があってこそ、サーベイは組織の前進を支えるツールになります。
「何を聞くべきか」「結果をどう活かすか」に悩んだときは、ラフールサーベイのように、スコアの背景まで構造的に分析し、具体的な改善アクションに落とし込めるツールを活用するのも一つの方法です。
ラフールサーベイは、個人と組織の両面を可視化し、「なぜその状態になっているのか」まで掘り下げられるツールです。
サーベイを「やりっぱなし」にせず、変化に向き合い、改善につなげる仕組みとして育てていきたい方は、ぜひ以下の資料をお読みください。
▼「ラフールサーベイでできること」「お客様の声」などをまとめた資料はこちらからダウンロードしてご覧いただけます。