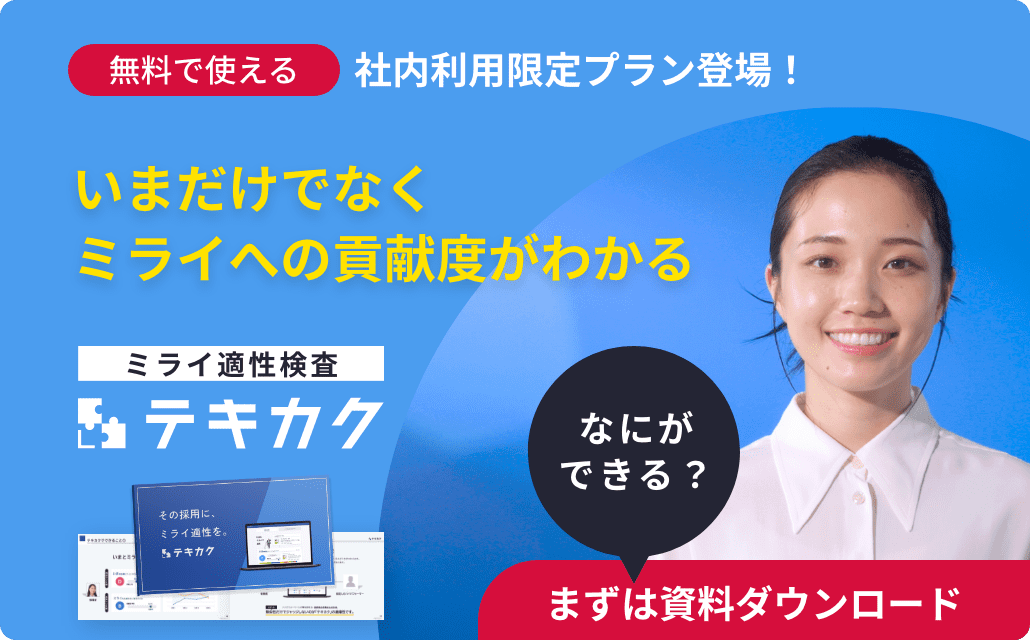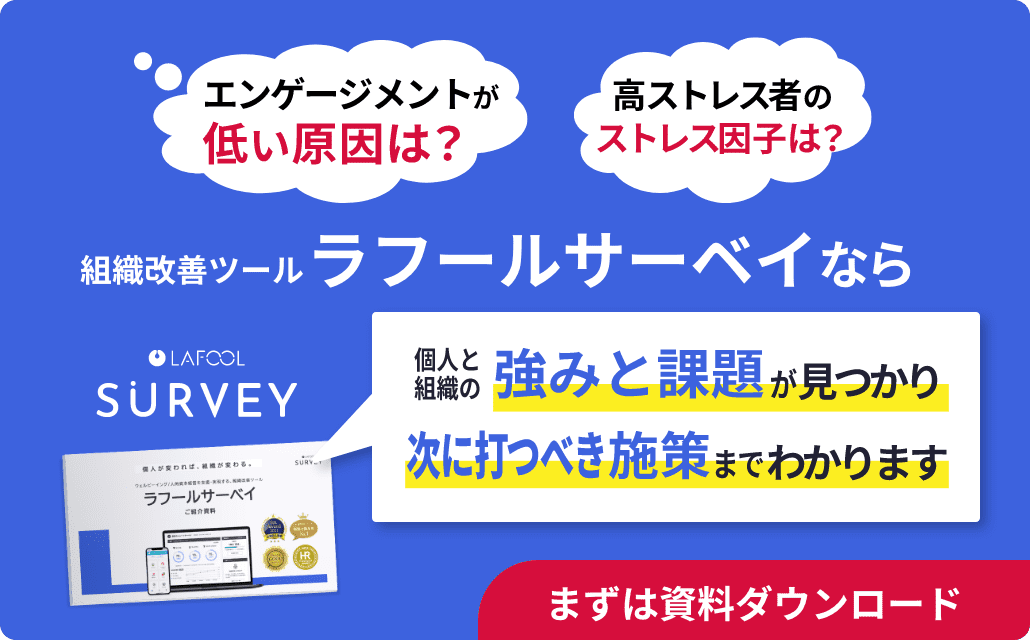変化の目まぐるしいVUCA時代において、市場の変化に迅速に対応するには組織改善は欠かせません。時代に合わせた組織改善を行うことで、生産性の向上だけでなく、従業員エンゲージメントの向上も期待できます。 そこで本稿では、組織改善とはなにか、またその具体的な方法や実際の事例について紹介していきます。
組織改善とは
組織改善とは、組織構造や機能などを変える事で企業が成長を続けられるように「基礎を見直す取り組み」のことです。
組織改善により業務のプロセスや、部署内のコミュニケーションの質など組織ごとの問題を解決・改善することで、業務の効率化や従業員の満足度の向上、そして業績の向上が見込まれ、企業の成長に繫がります。
組織改善の必要性とメリット
企業規模が拡大傾向にある企業では、制度が固定化されていたり、効率的でない業務フローが常態化してしまっている場合も少なくありません。近年は市場の変化が顕著であり、様々な変化が予測しにくいVUCA時代であることから、これに迅速に対応するにはこれに合わせた柔軟な対応が必要となります。そのため、組織改善をもって無駄な業務を削減したり、戦略を新しくする、新たなビジネスモデルに移行するなど様々な改善を行うことは、現代の市場変化への対応と企業の持続的な成長において必要なプロセスです。よって、組織改善は近年とても必要とされ、注目されています。
また、メリットとしては「生産性の向上」「従業員満足度の向上」「戦略実行度の向上」「サービス品質の向上」などが挙げられます。
生産性・従業員満足度の向上
従業員の業務における残業時間や人間関係を把握し、組織改善を行うことで無駄な時間、コミュニケーションを削減することができます。それに伴い、生産性の向上が見込まれるだけでなく、従業員エンゲージメントも高まり、結果的に従業員満足度の向上も見込まれます。
戦略実行度の向上
業績の向上において、ミドルマネージャーに対し経営者がビジョンや戦略をより鮮明に伝えることは非常に重要なポイントとなります。そのため、業績が不審な場合には、経営者のビジョンや戦略等がミドルマネージャーに上手く伝わっていない可能性があります。そのような場合には、ビジョンや戦略をより鮮明に伝えられるように、組織改善を行うことが必要になります。また、従業員エンゲージメントの高さも戦略実行度の向上に大きく関わるため、組織改善によって、従業員エンゲージメントを向上させることで戦略実行度の向上にもつながります。
サービス品質の向上
組織改善により、効率的・効果的なプロセスの導入によって生産性や従業員満足度の向上が起こると、それに伴って、顧客へのサービス提供も改善されます。また、業務効率化に伴い、変化が著しい市場に対してもスムーズにアプローチすることができる事から、サービス品質の向上だけでなく、サービスの革新などにもつながります。
組織改善とエンゲージメント
組織改善には、様々なメリットがありその背景には組織改善による従業員エンゲージメントの向上がしばしば隠れています。
従業員エンゲージメントとは、企業と従業員における信頼や結びつきの深さ、関係性の強さのことで、エンゲージメントが低いという事は仕事に対する意欲・モチベーションが低い状態という事です。従業員エンゲージメントが高い従業員は、仕事への情熱が高く、組織に対して積極的に貢献し、このようなエンゲージメントの高さは従業員の満足度から生まれます。
よって、組織改善により従業員エンゲージメントの向上を目指すことは、組織のパフォーマンス向上やめまぐるしく変化する市場への迅速な対応、そして企業の持続的な成長に非常に重要です。
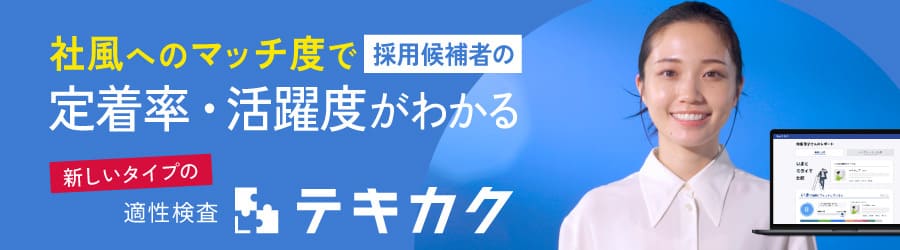
組織改善の種類と進め方

では次に、組織改善の種類と進め方について紹介します。
組織改善の種類
組織改善には「組織行動の整合性モデル」「クルト・レヴィンの3段階」の2種類の手法が広く知られています。大胆な組織改善や組織改革には、社内の混乱や困惑と言ったリスクがあることから、このようなプロセスを参考にして組織改善を行う事も手法の一つとなります。
組織行動の整合性モデル
これは、組織のパフォーマンス向上のためのフレームワークとして1989年にマイケル・タッシュマンとデービッド・ナドラーにより提唱されました。これは組織が直面する問題を1つのフレームワークで分析できる画期的なモデルであり、これを活用して組織改善のためのチーム編成を行うことで、既存業務との兼ね合いを気にせず組織改善に取り組むことができます。
詳しくはこちら:組織に悩む3つのケースから、組織変革の勘所を解説。「コングルエンスモデル(整合性モデル)」で組織は変われるか?
クルト・レヴィンの3段階
クルト・レヴィンの3段階は3段階の組織変革プロセスに分かれており、「解凍(Unfreeze)」、「変革(Change)」、「再凍結(Refreeze)」の3段階に分けて考えるモデルです。
詳しくはこちら:レヴィンの三段階組織変革プロセスに学ぶ、組織変革を進める上での留意事項とその事例
組織改善と7S
次に、組織改善におけるフレームワークである7Sについても紹介します。これは、組織の管理と成長に必要な要素を総合的に評価するモデルで、これも組織改善の時に重宝される手法の1つです。
7Sモデルの3S(ハード)
7Sモデルの3Sはハードのことでコントロールしやすいものです。
・Strategy(戦略):企業の方向性や組織がたてる戦略のこと
・Structure(構造):組織構造、階層や関係性のこと
・Systems(制度):組織の制度、評価や待遇、業務フローのこと
7Sモデルの4S(ソフト)
4Sは、ソフト側のことでコントロールなどに手間がかかるものです。
・Shared Values(共有価値観):ミッションやバリューなど組織全体の価値観
・Skills(技能):組織として有するスキルのこと
・Style(経営スタイル):社風や経営スタイルのこと
・Staff(スタッフ・人材):従業員及びその人の経歴などのこと
7Sモデルをベースにした組織改善
上記の7Sの内容をベースにした組織改善では、まず1. 「Shared Values(共有価値観)」で理念やビジョンを共有します。次に2. 「Strategy(戦略)」で1の実現のための戦略を立てます。そして3. 「Structure(構造)」で戦略に応じて組織の構築を行い4. 「Systems(制度)」で組織としての制度を制定します。そして5.「Staff(スタッフ・人材)」で従業員の募集と育成を行い、6. 「Style(経営スタイル)」で従業員との関係性を構築し、7. 「Skills(技能)」で組織としての能力、スキルを会得します。このような流れを繰り返すことで、組織改善を行うことができます。
組織改善の進め方
では、実際の組織改善の進め方についてです。
1. 現状分析と目標設定
組織改善を行う際は、まず現状分析を行う必要があります。組織の強みや弱点などを評価するために、SWOT分析が一般的に使用されます。これによって、現状把握を行ったのちに、目標を設定しましょう。目標はSMART基準を用いて設定することで、より明確で実行可能な目標を立てることが重要です。
2. 戦略の策定と実行
次に実際に課題を解決するために変更する、組織のプロセスや文化、構造を見直し、解決のための戦略を立てましょう。戦略を立てると同時に担当者も設定し組織改善を実行に移しましょう。
3. モニタリングと評価
次に、実行した戦略の進捗について定期的にモニタリングし、評価を行いましょう。計画通りに進んでいなかったり、組織改善が上手く行っていない場合には、目標や戦略を見直し、適宜修正を行いましょう。
4. 1~3の繰り返し
最後に、1~3を繰り返すことで市場の変化など組織のビジョンに合わせて適宜組織改善を継続しましょう。
組織改善の事例
さて、では最後に企業の組織改善事例について紹介します。
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車では、組織改善によって伝統的な組織風土「教え/教えられる風土」が守られてきました。
2000年代初期、トヨタ自動車は年間販売台数が急激に増加した一方で、人材育成が追いつかず、業績向上を目指し意思決定のスピード化を進めてきたことによってこの組織風土が崩れかけていました。
その後、リーマンショックをはじめとした様々な問題により業績は低迷していきました。
この状況に対して、2014年、豊田章男社長は大規模な教育改革を打ち出し、「教え/教えられる風土」の再構築を目指しました。
具体的には、社員を小グループにまとめ、先輩が後輩を指導しやすい体制を整えると共に、入社4・5年目から10年目程度の社員が「職場先輩」となって、職場ごとにマンツーマンで相談役となる仕組みを構築しました。
また改善に伴い、業務のグローバル化、技術革新によって、先輩も答えを持たない事例の増加、上司の部下に対する「今どきの若者は」という意識などが新たな課題となりました。
しかし、これを踏まえた更なる組織改善の結果、教わる側と教える側が共に成長し、トヨタ自動車の組織全体のパフォーマンスが向上しました。
参考元:当たり前を実現する!トヨタの人材育成の歴史と風土づくり
1980年に戻れ! トヨタの「人の育て方」大改革始動【前編】
株式会社湖池屋
株式会社湖池屋では、「ブランドを強くしていくためには協力を惜しまない」という風土がある一方で、指示待ち社員が常態化していました。
これは、チャレンジして目立つよりも、波風を立てないことを優先する「挑戦がしにくい環境」が課題となっていたそうです。
そこで、2016年に佐藤章社長は「指示待ち脱却」「思考力と主体性を身につける」をテーマとして組織改善を実施しました。
チャレンジがよい事であるという風土の育成と共に、部門間連携の会議を立ち上げ、コミュニケーションを深める仕組みも整えたようです。
これらの取り組みによって、自律的に働く社員を生み出す組織風土がつくられ、次々と新しい商品が生まれました。新しいブランドのヒットは、社員の停滞していた自信を回復させ、社員の主体性が改善されることとなりました。
参考元:働いてみたい注目成長企業”湖池屋が実践!チャレンジする人材と組織をつくる「人事制度改革」
さらに詳しく企業事例を見るにはこちら:組織風土改革の成功事例5選と失敗しないための4つのポイント
まとめ
組織改善は企業の成長に重要なプロセスです。一見難しく感じますが、組織と従業員の現状をしっかり把握し、問題を洗い出すことで組織改善の一歩を踏み出すことができます。組織改善において従業員の現状を把握するためにはサーベイシステムなどの導入が一般的です。特に、ラフールサーベイにおいてはただのサーベイにとどまらず、組織と個人の状態を丸っと調査でき、さらに深堀りすることで根本的な問題の要因を解明することができます。その結果、組織改善だけでなく、離職防止や従業員エンゲージメント向上に直結させることができます。組織改善をお考えの際には、是非ラフールサーベイをご検討ください。