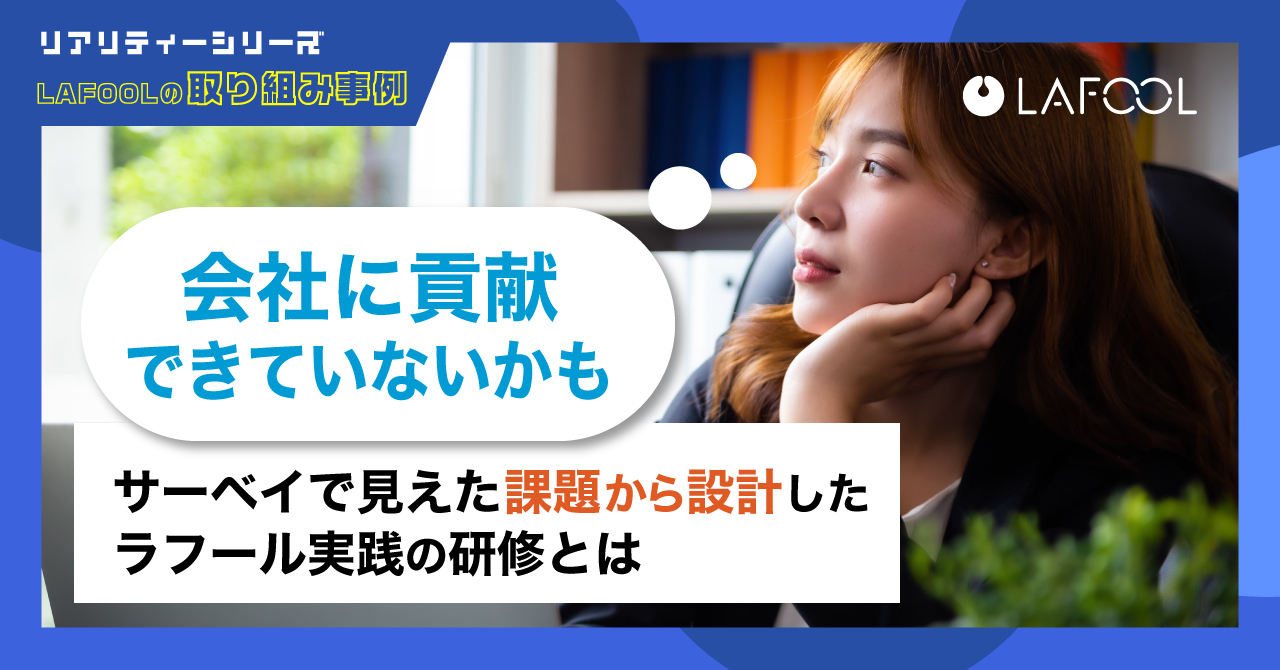組織をより良くするために、研修やワークショップといった施策に取り組んでも、具体的な変化が見えず手応えを感じられない…というのは、多くの人事企画担当者が共通して抱える悩みではないでしょうか。
原因のひとつは、「本当に必要な打ち手が何か?」をつかみきれないまま、企画が先行してしまうことにあります。
ラフールでは、研修を単なる“良さそうな施策”で終わらせず、今ある課題にきちんと向き合うものにしたいと考えています。そのために私たちが大切にしているのが、サーベイによる課題の可視化です。
今回ご紹介するのは、サーベイで見えてきた社内の状態を出発点に、現場に必要なテーマを見極めて研修を設計・実施したラフール社内の取り組みです。
組織課題に向き合った研修を企画したいと考えている方や、サーベイ結果を施策にどう落とし込むか悩んでいる方の参考になれば幸いです。
サーベイで浮き彫りになったのは、社員の「会社に貢献できていないかも」という実感
ラフールでは、ラフールサーベイの結果を起点に、その時の組織課題の解決につながる研修を企画することがあります。今回の研修も、サーベイから見えてきた課題をもとにうまれた企画でした。
サーベイ結果から明らかになったことの中で特に注目したのが、「会社に対する貢献実感」に関する項目です。
「会社で自分が中心となって何かを成し遂げたことがある」「会社の成長や発展に自分が役に立ったことがある」といった設問に対する回答がやや後ろ向きな傾向がありました。

※図:サーベイ画面のイメージ(※実際のラフールでの回答結果ではありません)
こうした状態をそのままにしてしまうと、自分の仕事に対する手ごたえや納得感が薄れていき、前向きに働く気持ちの低下につながりかねない。
そうした懸念から、貢献実感の低さを「今まさに解決すべき課題」と決めたことが研修企画の出発点となりました。
貢献実感の低さの背景にあった「行動量の少なさ」
この結果を受けて、ラフールでは「なぜ貢献実感が持ちづらくなっているのか?」という背景を探っていきました。
その中でひとつの仮説として浮かび上がってきたのが、「行動量」でした。
社員自身が「自分は会社に貢献できている」と感じるには、「自分の行動によって何かが動いた」という手ごたえや達成感があってこそです。ですが、実際の対話や日々の様子からは、次のような傾向も見えてきました。
- やるべきことにはしっかり取り組んでいるものの、新しい一歩には慎重になる場面もある
- 自分の役割を越えて動くことに、戸惑いや遠慮があるように見える
- 周囲への配慮から、発言や行動を控える場面がある
- 「失敗したらどうしよう」という不安から、挑戦に踏み切れずにいる
こうした「慎重さ」や「動き出すことへのためらい」が行動のきっかけをつかみにくくし、結果として手応えを感じる場面が少なくなっているのではないか。
ラフールではそう捉え、「まず動いてみる」ことへのハードルを下げ、行動から得られる手ごたえや小さな成功体験を積み重ねることで、結果的に「自分も貢献できている」という実感につなげていくことができるのではないかと考えました。
仮説に基づいた企画のビジネスゲーム
ゲーム形式で行動量と成果の関係を体感させる研修
行動量の少なさが「自分は会社に貢献できている」という実感を得づらくする要因になっているのではないか。
この仮説に基づき、ラフールでは社員一人ひとりが“行動の量と質が成果にどうつながるか”を体感できる研修を設計しました。
その際、既成のビジネスゲーム型研修プログラムを活用しました。
このゲームは仮想のビジネス環境の中、限られた資源(ヒト・モノ・カネ)を使ってビジネスモデルを組み立て、他チームと交渉しながら“会社を拡大”するというものです。
ゲーム内では、迷っている時間は“機会損失”につながり、素早く動いた人ほど成果を得る。まさに、行動が成果につながる仕組みを疑似体験できます。
行動して見えた、“成果につながる感覚”
研修を通して、参加者は「まず動く」ことの大切さを実感していきました。
ゲームは時間制限がシビアで、悠長に計画を立てる時間はありません。
完璧を目指して考えすぎていると、ライバルに出し抜かれてしまうといった場面も。大きな成果をじっくり考えるよりもとにかく動き、「とりあえず交渉にトライしてみる」、「相手にとってのメリットを素早く提案する」といった一歩が成果につながる体験を通して、「まず動く」ことの意味を体感していきました。

研修後のアンケートでも、「素早い判断が迫られ、チームの行動力についていくのに必死だった」「”当事者意識”についての理解は深まったというより”体験した”という印象が強かった」といった声が寄せられました。
頭で理解するだけでなく、体を使って動いたからこそ得られた実感。この研修は、ただ知識を学ぶだけのものではなく、気づきを自分の中に落とし込む体感型の学びだったといえます。
気づきが生まれたのは、社員自身の課題意識と自然に重なったから
今回の研修で特に印象的だったのは、体験型だったからというだけではありません。研修で得られた気づきが、社員それぞれの中にすでにあった感覚や課題意識と自然に重なっていたことが、大きなポイントでした。
「自分は会社に貢献できているのだろうか」という思いをどこかで抱えていたからこそ、研修で体感した「まず動くことの価値」は、押しつけではなく、自分の中で腑に落ちる学びとして受け止められました。
ラフールサーベイを通じて浮かび上がった「貢献実感の低さ」というテーマが、現場の実感とも重なっていたからこそ、研修での体験はすんなりと腹落ちし、納得感のあるものになったのだと感じています。
劇的な変化がすぐに現れるわけではないかもしれません。しかしアンケート結果からは、意識の変化や行動への前向きな反応が着実に見られました。こうした気づきや変化の積み重ねこそが、組織にとって持続的な変化の第一歩だと考えています。
「とりあえずの施策」から脱却するには、課題の可視化が欠かせない
近年では、社員の育成や組織課題への対応として、研修に取り組む企業も増えてきました。 しかし、目的が曖昧なまま「とりあえず研修をやる」ことが目的化してしまっては、本来の意味を成しません。
本当に意味のある研修にするには、まず「今、自社にどんな課題があるのか」「その背景にはどんな要因があるのか」を把握することが不可欠です。
課題に向き合わないまま内容を決めてしまえば、現場にとっても“やらされ感”が強くなり、研修への納得感や行動変容にもつながりにくくなります。研修はあくまで「組織課題を解決するための手段」です。
だからこそ、「今、自社が本当に向き合うべきテーマは何か?」を正しく見極めることからはじめるべきだとラフールでは考えています。
組織の“本当の課題”に向き合うために。ラフールサーベイという土台
今回のように、「貢献実感の低さ」といった感覚的で言語化しにくいテーマも、ラフールサーベイならスコアや傾向として見える化することができます。
ラフールサーベイの最大の特長は、社員一人ひとりの「状態」を深掘りしながら、それがどのように組織課題に影響しているのかを把握できる設計にあります。
網羅的な設問構成により、エンゲージメントや心理的安全性はもちろん、「貢献実感」「成長実感」「周囲との関係性」など、組織づくりに欠かせない多面的な要素を数値として把握することが可能です。
さらに、組織全体/部門単位/職位別など、様々な切り口からの比較ができるため、「どこで・どのような傾向が出ているのか」といった構造的な課題の特定にも役立ちます。
ただの満足度調査にとどまらず、「だから何をすべきか?」までを導き出す“打ち手設計のヒント”となるデータが得られるのが、ラフールサーベイの強みです。
ラフールサーベイは、組織が“本当に向き合うべき課題”を明らかにし、納得感ある施策へとつなげていく第一歩を支えるツールです。
もし、今「研修の効果が見えにくい」、「組織が変わる実感が持てない」といった不安をお抱えであれば、まずは組織の状態を“見える化”することからスタートしてみてはいかがでしょうか。