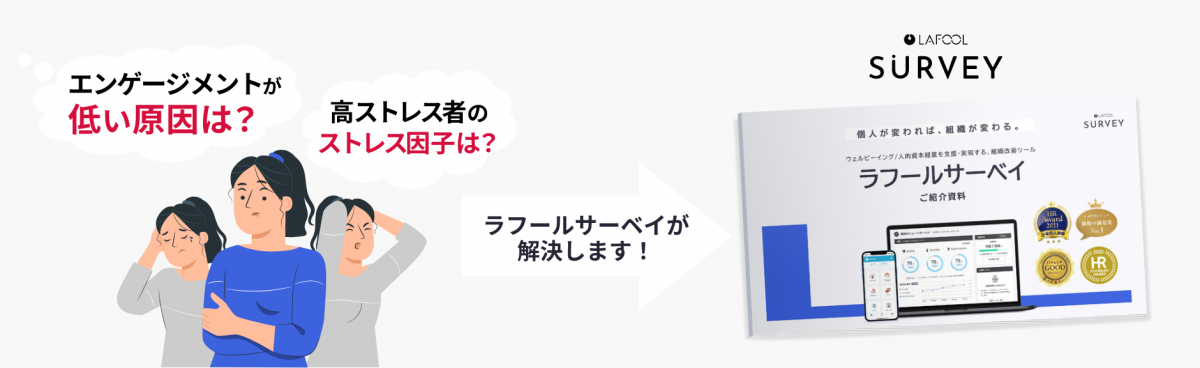会社を辞める人には、共通して表れるサインがあります。退職は唐突に見えることがあっても、多くの場合は悩み抜いた末に決断されているからこそ、日常の中に小さな変化が現れるのです。
こうしたサインをあらかじめ理解しておけば、対応を早めに取ることができます。
今回は「辞めそうな人に見られる特徴」と「その兆候を見逃さないためのポイント」について解説します。
組織の強みと課題が見つかり「次に打つべき施策」がわかる
ラフールサーベイの資料ダウンロードはこちら
なぜ「辞めそうな人」を早めに見つけたいのか
社員の離職は、企業にとって大きなコストを伴います。採用や教育にかけた投資が無駄になるだけでなく、新たな人材を採用・育成するための時間や費用も発生します。
さらに、退職によって業務の引き継ぎが不十分になると、現場が混乱したり、他の社員の負担が一時的に増えたりすることもあります。結果としてチーム全体のモチベーションやパフォーマンスが下がってしまう可能性があります。
だからこそ、辞めそうなサインを早めに察知して対応することが大切です。早期にアプローチできれば、本人が抱える不安や不満を解消でき、退職を防げるチャンスを残すことにつながります。
会社を辞めそうな人の特徴10選
会社を辞めそうな人には様々な特徴がありますが、代表的な10個の特徴がこちらです。
- 挨拶をしなくなった
- 上司や同僚からの評判を意識しなくなる
- やる気がない
- 愚痴や不満ばかり言っている
- 急な早退や休みを申し出る
- 会議などで意見を発言しなくなる
- 服装や髪型がいつもと違う
- 自席にいる時間が増える
- 生産性が低下している
- 仕事後の付き合いをしなくなる
1つずつ具体例を合わせて紹介します。
【辞めそうな人の特徴1】挨拶をしなくなった
これまでとは異なり挨拶を積極的に行わない態度や、避けているような様子が特徴の1つとして挙げられます。挨拶は始業時や業務中、退勤時と1日の中で交わされる機会が多いため、変化に感じやすい特徴とも言えます。
コミュニケーションの基本とも言われる挨拶をしない社員は、何かしらの不満や悩みを抱えている場合もあるでしょう。
【辞めそうな人の特徴2】評価を気にしなくなる
退職を決断した場合、出世や社内での評価に関心がなくなるため、周囲の社員からの評判を意識しなくなります。上司や同僚から認められようと業務に励む姿勢や、周囲を気遣った態度が以前と比べ減ってきた場合、今いる会社よりもこれからの会社への関心が高まっている可能性があります。
【辞めそうな人の特徴3】やる気が見えない
辞めようとしている会社では労働意欲が湧かないことから、やる気のない働き方が特徴として見受けられます。業務に集中して取り組めず従来より進捗が悪い状況や、意欲的な姿勢や発言が見られない社員は、今いる社内での業務にやる気がなくなっていると考えられます。
【辞めそうな人の特徴4】愚痴や不満ばかり言っている
会社を辞めようとする人は転職活動を通し、現状と他社での働き方を比較してしまうことで、今の会社への愚痴や不満が増えます。どの社員でも現状への不満は全くないとは言えず、ある程度不満はあるものです。しかし辞めようとしている社員の場合は不満の割合が大きいため、話題のほとんどが愚痴になりやすい傾向があります。
【辞めそうな人の特徴5】急な早退や休みを申し出る
急な早退や休暇を申請する言動は、会社を辞めようとする人の特徴として多く見られます。転職活動の面接予定で休む場合や、有給休暇の消化、働く意欲がなくなり休暇を取るなど、理由は様々考えられます。これまでは前もって申請をしていたのに、突然早退や直近の休暇申請が増えた場合は、辞めそうな人の特徴として捉えて良いでしょう。
【辞めそうな人の特徴6】会議などで意見を発言しなくなる
会議での発言が減った社員は、会社を辞めたい気持ちから労働意欲が下がり主体性を持って会議に出席できていない状態であることが考えられます。転職先が決まっており、今の会社へ思い残すことがない状態である可能性もあります。また、発言は減っていないが当たり障りのない意見ばかりになった社員も同じようなことが考えられるでしょう。
【辞めそうな人の特徴7】服装や髪型がいつもと違う
これまでとは異なるきっちりとした服装や髪型へ変えて出勤する社員は、転職活動に備えた外観を意識していることが考えられるため、辞めたい人の特徴として挙げられます。具体的には、これまでラフな格好だった社員が落ち着いた色合いのスーツで出勤することや、化粧やネイルが控え気味な日が増えたなどの変化があります。これらは面接の対策として外見に変化が現れている可能性が考えられます。
【辞めそうな人の特徴8】自席にいる時間が増える
自席にいる時間が増えた社員は、意図的に周囲の社員との関わりを減らそうとしている場合があります。具体的には、昼食のタイミングや職場での雑談中に、1人になろうと離れていく言動が見受けられます。理由としては、既に転職先が決まり今の会社の人たちとは関わりにくくなったことや、1人の時間を増やし辞める準備に取り組みたいと考えている可能性があるでしょう。
【辞めそうな人の特徴9】生産性が低下している
業務の効率が下がることや、ミスが増えることによって生産性が低下している状態は、辞めそうな人の特徴として考えられる場合があります。辞めそうな人は労働意欲が低下しているため従来よりも業務の進捗が悪く、結果的に生産性が低下します。その一方で、単なるブランク期間や、成長過程であることも考えられるため、まずは業務上の不安や悩みの相談に乗ることが重要です。
【辞めそうな人の特徴10】仕事後の付き合いをしなくなる
「そのうち会社を辞めるから社内の人と仲良くしても意味がない」といった考えから、仕事が終わると社内の人と関わろうとしない特徴が見受けられます。例えば、よく飲み会に参加していたのに急に控えるようになったなどといった変化が現れます。自分の自由な時間を転職活動や次の会社に向けた準備にあてたいと考えている場合もあるでしょう。
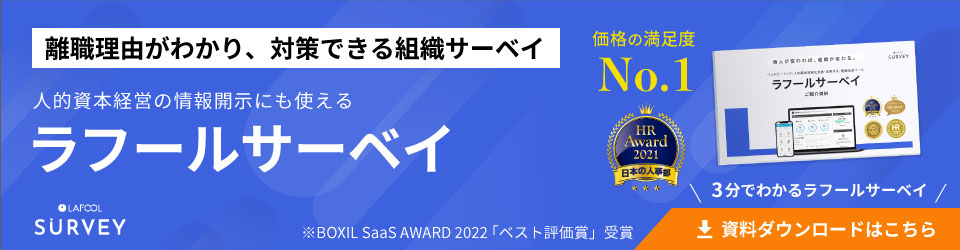
優秀な社員が仕事を辞めたいと思う理由とは?

人手不足が叫ばれる中、社員1人が辞めることはもちろんですが、優秀な社員が辞めることは企業にとって大きな痛手となります。手遅れになる前に、予めその理由を把握しておきましょう。以下の4つの理由が、優秀な社員が仕事を辞めたいと思う理由として考えられます。
- 人間関係で煮詰まっている
- 仕事内容にやりがいを感じない
- 正当な評価が受けられないと感じる
- 給与が福利厚生がよくない
- 残業が多い
それぞれ理由を含め解説します。
人間関係で煮詰まっている
多くの時間を過ごす職場での人間関係が不安定であることで、働く環境を変えたいという気持ちが芽生えます。
例えば、上司に依頼された業務を提出しても後日違う内容を求められることや、上司の主観で気に入られないと評価されないといった状況が挙げられます。高いスキルや能力を持っていても、尊敬できる人や認めてくれる人、相談のしやすい人が周囲にいない環境は、その人のスキルや能力が活かしきれずやりがいも感じられにくいでしょう。
成長ができないと感じられる環境下では労働意欲も低下するため、優秀な社員ほど辞めたいと思う理由になります。
仕事内容にやりがいを感じない
優秀な社員ほど、更なる高みや成長を目指し業務に励んでいるため、やりがいが感じられない業務には不満を感じてしまいます。
具体的には、十分な裁量が与えられない業務や、新たな挑戦ができる機会を提供しない職場であると、働きがいを感じられにくいでしょう。やりがいが感じられないことによって、自分に適した働き方や環境に目を向ける機会が増え、辞めたい理由の1つとなります。
正当な評価が受けられないと感じる
正当な評価が受けられない会社だと感じた場合、優秀な社員は自身の持つスキルや能力を活かし職場を変えようと思い始めるきっかけとなります。例えば、自分の方が目標達成率が高いのに上司に気に入られている社員の方が評価されている状況や、成果を上げているのに昇給や昇格がない場合などが考えられます。理不尽な評価では不満が溜まり、自分自身の努力や成果を正当に評価してくれる会社への転職を検討することとなるでしょう。
給与や福利厚生がよくない
優秀な社員は高い成果を出すことが多いため、見合っていない給与や福利厚生には不満を感じやすくなります。
努力や取り組み、成果の対価として、給与や福利厚生があるため、妥当で適切な対価を得たいという気持ちが生まれます。そのため、「他の会社ではどうなんだろうか」と他社での働きを視野に入れ始め、ひいては辞めたいという理由の1つになります。
残業が多い
残業の増加は、社員の疲労とストレスを確実に蓄積させます。
過労は社員のモチベーションや業務の生産性の低下につながるため、残業をなるべく発生させないように工夫することが大切です。
また、特定の社員や部署への負担がかかりすぎないよう、企業全体で協力して業務を分散させるよう意識すると良いでしょう。
ワークライフバランスを取ることは、人材の長期的な投資につながります。
社員が働きすぎた結果、これ以上働き続けられないと追い詰められて、本末転倒にならないように対策をとりましょう。
仕事を辞めそうな人への対応方法
社員の退職サインに気づいたときは、早めに適切な対応を取ることが大切です。
原因や状況を分析する
まずは、組織改善ツールなどを用いて、辞めそうな社員がどのような点に不満やストレスを抱えているのかを客観的に分析し、仕事を辞めたいと思うようになった原因を特定すると良いでしょう。
また、組織に新しく仲介者役を投入し、辞めそうな人が置かれている状況を客観的に把握することも効果的です。
面談で話を聴く
早い段階で面談を設け、率直な気持ちをヒアリングします。1on1やランチ面談のような和やかな場が効果的です。大切なのは、否定せず傾聴する姿勢です。憶測や押しつけは避け、安心して話せる雰囲気をつくりましょう。
キャリアに沿った対応を考える
もし業務のミスマッチがある場合は、部署異動や担当変更で解決できることがあります。その際は本人の意向を尊重し、一方的に決定しないことが重要です。将来のキャリアビジョンを確認し、実現できる環境を整えることで、働き続けたい気持ちを高められます。
休職を提案する
心身の疲労が強い場合は、退職の前に休職という選択肢を提示します。産業医や外部専門機関と連携しながら、原因を明確にし回復をサポートしましょう。もし過重労働が背景にある場合は、組織全体の労働環境を見直すことも欠かせません。
評価を見直す
待遇への不満が強い場合は、評価制度の透明性と納得感を高めることが求められます。成果やスキルを正しく反映できているかを確認し、必要に応じて360度評価など多角的な方法を導入しましょう。説明不足が原因なら、丁寧に伝えることでも改善が可能です。
管理職が辞めそうな社員を引き止めるときの注意点
辞めそうな社員への向き合い方は、立場によって変わります。直属の上司であればキャリアや業務の提案ができますし、人事であれば客観的な立場から本音を引き出しやすいでしょう。ここでは、引き止めの際に意識すべきポイントを整理します。
議論ではなく傾聴を優先する
社員の考えを変えようと議論するのではなく、まずは傾聴に徹することが大切です。不信感や諦めを抱えている場合もあるため、意見を否定せずに不安や不満を受け止め、一緒に解決していく姿勢を示しましょう。
本音を安心して話せる場をつくる
退職を考えている社員は、本当の理由を隠してしまうことがあります。そのため、聞き手が誠実に向き合い「本音を言っても大丈夫」と思える環境を整えることが必要です。場合によっては、カウンセラーなど評価に影響を与えない第三者との相談機会を用意するのも有効です。
必要に応じて自己開示をする
相手が本音をなかなか話せないときは、聞き手側が自分の悩みを少し共有することで、共感をきっかけに会話が深まりやすくなります。ただし、自分語りにならないよう注意し、あくまで社員が安心して話せるための手段に留めましょう。
周囲に知られないように配慮する
退職の意向が周囲に広まると、当人は居づらくなり、引き止めが難しくなります。業務の割り振りも普段通りにし、面談内容は他言しないことを明確に伝えるなど、精神的な安全を守ることが欠かせません。
部下の辞めそうなサインを日頃から見逃さない方法
退職を防ぐには、日頃から小さな変化に気づける環境づくりが大切です。代表的な方法は次の2つです。
社員と密にコミュニケーションを取る
普段から声をかけたり悩みを聞いたりすることで、変化に気づきやすくなります。小さな悩みも受け止める姿勢を示すことで、社員は安心して本音を話しやすくなり、不満の早期解消にもつながります。
サーベイツールを活用する
ただし、現場での観察やコミュニケーションだけでは把握できない不安や不満もあります。そこで有効なのがサーベイツールです。
アンケート形式で社員の心理を可視化することで、表に出にくい声を拾い上げられます。結果を分析すれば、辞めそうなサインを見逃さず、具体的な改善策にもつなげられます。
組織の状態を可視化し、改善アクションにつなげる「ラフールサーベイ」
辞めそうなサインは、日常の会話や観察だけでは見逃されてしまうことがあります。
ラフールサーベイは、社員のコンディションや組織の状態を定期的に可視化することで、そうした見えにくい兆候を早期に把握できる仕組みです。
また、スコアの良し悪しだけでなく、「なぜその状態になっているのか」という背景にある要因まで把握しやすい設計になっており、チームごとの傾向や構造的な課題の把握にも役立ちます。
退職リスクを未然に防ぐには、個人の変化に気づくだけでなく、組織全体の状態を継続的に確認することが大切です。
そのための仕組みとしてラフールサーベイを取り入れることで、改善アクションへとつなげやすくなります。

組織の強みと課題が見つかり「次に打つべき施策」がわかる
ラフールサーベイの資料ダウンロードはこちら
まとめ
今回は、辞めそうな人に見られる特徴と、そのサインを見逃さないための方法について解説しました。上司が事前に兆候を把握しておくことで、手遅れになる前に対応することができます。
とはいえ、日常の観察やコミュニケーションだけでは限界があるため、組織や社員の状態を定期的に可視化する仕組みも欠かせません。ラフールサーベイは、そうした状態の変化を把握しやすくするツールのひとつです。
日々のコミュニケーションとあわせて活用することで、退職につながるサインを早めに察知し、職場環境の改善に結びつけられるでしょう。